今回紹介する本は、「職場のメンタルヘルスマネジメント-産業医が教える考え方と実践(川村 孝 著 ちくま書房)」です。
本書は、以下の11部構成になっています。
- 勤務は契約
- 部下の管理方法
- 健康的仕事術
- 就業管理に関する会社への提案
- 人の心の多様性
- 職場で見つかる精神症状
- 便宜的に用いられる診断名
- 休職と復職の過程
- 労働衛生推進のしかけ
- 健康管理の実務
- 産業医とは何か
1.勤務は契約
「勤務は契約」では、主に以下のことが述べられています。
- 会社で働く従業員は、「雇用契約」を締結している。
- 会社には労働者の安全や健康に配慮する義務が生じる。
- 労働者にも雇用契約が全うできるよう「自身の心身の状態を良好に保っておく」義務(自己保全義務)がある。
2.部下の管理方法
「部下の管理方法」では、主に以下のことが述べられています。
- 上司の業務を進めるための必要な態度
- 笑顔で接する
- 一般に笑顔で指導した方が部下にはやる気が起きる。
- 笑いで脳機能が向上することも知られている。
- 少なくとも怒りや不機嫌を表に出さない。
- 部下の話をよく聞く
- 定期的に部下との面談時間を設けて、部下が抱えている課題を共有する。
肯定も否定もしない。
- 定期的に部下との面談時間を設けて、部下が抱えている課題を共有する。
- 「よくできた点」と「改善を要する点」の両方を述べる
- 多少なりとも(探してでも)良かった点を述べることが重要。
(人間は、もともと承認を求める)
→お世辞を言うのではなく、的を射たほめ方をする。 - よくできた場合でも、ほめるだけではだめ。
さらによくなるために、これからの課題を告げることが必要。 - 問題点の指摘では、人格を否定する言葉はハラスメントになって即アウト。
- できる部下にはできるなりに、できない部下にはできないなりに、今までの努力を認めつつ、これからの課題を伝えなければならない。
- 多少なりとも(探してでも)良かった点を述べることが重要。
- 発言する言葉を選ぶ
- 結果がよくなるよう、言葉の表現を工夫する。
- ゴールを設定する
- ゴールには「最終到達点」と「当面の目標」がある。
- 最終到達点は、プロジェクト全体の仕上がり像
- 当面の目標は、今日行う仕事の到達点、1週間程度のひとまとまりの仕事の仕上がりでもいい。
- 「いつまでに」「何を」を示す。
人間ゴールが見えれば頑張れる。ちょっと頑張れば到達できるゴールを設定する。
- 人を診る(ラインケア)
- 部下は元気か、疲れているかを診る。
- 疲労の色が濃い場合は、休養や受診を勧奨する。(これも安全配慮義務)
- ”オレ流”を押しつけない
- 人は1人ひとり違うので、自らのやり方を押しつけない。
- 人を変えるのは大変なので、自分が変わった方がよい。
- 管理職としては、部下の特性や能力に合わせて仕事を振ることが重要。
- あるべき管理職像を演ずる
- 課長になったら、あるべき課長像を描き、それなりになりきることが必要。
- 笑顔で接する
- 部下の言動がおかしいと思ったら、記録に残す。おかしいと思ったその時に日付と部下の言動をメモしておく。
3.健康的仕事術
「健康的仕事術」では、主に以下のことが述べられています。
- 課題が振られた時は、「とりあえず手を付けてみる」
- 朝の時間を有効に使う。(残業は朝やる)
- 得意なところで勝負する。
- 返答は肯定系(こうすれば~できます)と返すとよい。
否定形(~できません)で突っぱねない。 - 手を使って喋る方が、喋りやすく内容も伝わりやすい。
- 聞かされる側の身になって発言する。
- 上手な叱られ方について
4.就業管理に関する会社への提案
「就業管理に関する会社への提案」では、主に以下のことが述べられています。
- 多様な勤務形態について
- 1日の労働時間を増やして、休日を増やす等
- 健康状態や私的活動に合わせて「1日4~6時間」や「週3~4日勤務」の正社員があってもよい。
- 機械的に転勤させる制度は、そろそろやめた方がよい。
- 役職を任期制にするか、人の指導や管理が苦手な人は専門職として処遇する。
- 退職者を再雇用して、相談相手にする。
利害関係がなく、会社の事情も良く知っているので最適。
5.人の心の多様性
「人の心の多様性」では、主に以下のことが述べられています。
- メランコリー親和型
- まじめで誠実なタイプ。
責任感がよく物事がうまくいかないときは、「自分の能力や努力が足りない」と自身を責め、抑うつ的になりがち。 - 仕事を頼まれると、目一杯でも引き受けて、頑張りすぎて突然休職になることがある。
- 管理職は、必ず本人の心と体の余裕を確認しながら、仕事を指導しなければならない。
- まじめで誠実なタイプ。
- 神経発達症(発達障害)
- 先天的なもので、自閉症、注意欠如症、限局性学習症、協働運動症などがある。
- 自閉症
- 人の気持ちが直観としてわからないという特性。
- 注意欠如症
- 部分部分は見ることができるが、全体を同時に見ることができないという心性。
舞台のスポットライトの当たっているところは見えるが、光の当たっていないところは見えないといった感じ。
- 部分部分は見ることができるが、全体を同時に見ることができないという心性。
- 神経発達症への会社の対応
- 「合理的配慮」を行う。
- (小さいころからの子育てが原因による)パーソナリティの歪み
A群(妄想)、B群(他罰(攻撃))、C群(回避)に分けられる。- 歪んだパーソナリティへの対処(特にB群)
- 本人と向き合って話を聞く際、冷静さを保ち、相手の周りの感情のみ受け止めること、否定されたり、いきり立ったりしないこと。
- ルールで迫ること
法令や就業規則で規定されたことを守らせ、反すれば懲戒対象にする。 - 必ず複数の管理者で対応し、事実の記録を保管する。
産業医にも相談する。
- 歪んだパーソナリティへの対処(特にB群)
6.職場で見つかる精神症状
「職場で見つかる精神症状」では、主に以下のことが述べられています。
- 抑うつ
- 「ゆううつな気分」と「意欲の低下」の二要素が揃った状態が持続すること。
- 躁及び軽躁
- なんのきっかけもないのにやたらとハイテンション(躁状態)になったり、落ち込んだりする状態(抑うつ状態)が続く病気は「双極症」という。
- 妄想
- 「現実にはないことを、あると確信している状態」のこと。
- 不安
- 不安が必要以上に強くなるタイプがある。
- 不眠
- 不眠が2週間以上連続する場合は、受診を考える。
- ストレス
- 仕事のストレス要因は高温多湿などの自然条件から、上司、同僚や取引先などの人間関係まで多岐にわたる。
- ストレス反応は、発汗、動悸、腹痛、下痢などの身体的なものから、不安、抑うつなどの心理的なものがあり、過食、過飲酒などの行動を含むこともある。
- ストレスは活力を生み出す力になる場合もある。
- トラウマとフラッシュバック
- 生命に影響しかねない事故に巻き込まれたり、激しいいじめにあうなど、非常に大きな恐怖をもたらす出来事によって、心が傷つくことがある。これがトラウマ(心的外傷)
- 誘因となった人や状況が現れると、以前の体験がよみがえって心に当時とよく似た反応が現れる。これがフラッシュバック。
フラッシュバックが持続するものを「PTSD」といい、こうなると専門医の受診が必要となる。
- 解離
- 本来1つにまとまっている自分の意識が複雑に分かれてしまい、複数の意識の間を一方向あるいは双方向に移行する状態をいう。
「二重人格」はその一つ。ある時間の記憶が飛ぶ「健忘」も解離の1つ。
- 本来1つにまとまっている自分の意識が複雑に分かれてしまい、複数の意識の間を一方向あるいは双方向に移行する状態をいう。
- 身体化
- 心の変調なのに、身体の症状として表れること。
- 「いつもと違う」に気づく
- 上司が部下が以前と違う状態であることに気づいたら、産業医に相談する。これがラインケア。
「ちょっとヘン」の段階での対応が何より大事。
- 上司が部下が以前と違う状態であることに気づいたら、産業医に相談する。これがラインケア。
7.便宜的に用いられる診断名
「便宜的に用いられる診断名」では、主に以下のことが述べられています。
- 「うつ状態」「抑うつ状態」:うつ病までとは言えない状態。
- 「不眠症」「睡眠障害」:不眠の原因がつかめていない場合に用いられる。
- 自律神経失調症
- 自律神経の調節機能に問題があって、不合理な自律神経症状が出た場合につけられる。
- 精神疾患があって、二次的に自立神経系の症状を伴う場合も付けられる。
- 適応障害
- 「自分が業務処理能力や心理特性」と「命ぜられた仕事や就業環境」とが、うまく合わなかった状態を表している病名。
本人と職域がうまくマッチしていない。
- 「自分が業務処理能力や心理特性」と「命ぜられた仕事や就業環境」とが、うまく合わなかった状態を表している病名。
8.休職と復職の過程
「休職と復職の過程」では、主に以下のことが述べられています。
- 傷病休暇が一定期間以上になると、会社が一定期間の「休職」を命ずることがある。
休職は、「解雇の猶予」という位置づけ。- 休職はいずれ復職することが前提。
- 病気休職中は、療養に専念する。
- 復職したら、ごく短い配慮期間を除いては、雇用時に結んだ雇用契約の条件が満たされなければならない。(所定労働時間、業務内容等)
職場は、病気のリハビリをする場ではない。 - 復職の申請は、十分に吟味することが必要。
復職させて病気が再発すると、会社も責任を問われる。 - 本人が十分に復職できそうであれば、上司や人事と受入態勢について打ち合わせをし、上司、人事、産業医で復職の成否を決め、記録に残す。
- 近年は復職にあたって、リワークプログラムを用いることが多くなった。
- 半日若しくは全日を週2日~5日、全体として3~6ヶ月続けるタイプが多い。
- 復職先は「元の職場、元の地位」が原則。
但し、元の職場に休業の原因がある場合は、配属先を変更することもある。
9.労働衛生推進のしかけ
「労働衛生推進のしかけ」では、主に以下のことが述べられています。
- 安全衛生を推進する手段として、法令、国際規格、健康経営の3つのアプローチがある。
10.健康管理の実務
「健康管理の実務」では、主に以下のことが述べられています。
- 一般健康診断
- 会社は健康診断を年1回提供しなければならない。
従業員は受診の義務があり、受けなければ減給や配転などの不利益処分があっても文句は言えない。(自分で健康診断を受けて、会社に結果を提出してもよい。)
- 会社は健康診断を年1回提供しなければならない。
- 特殊健康診断
- 有害業務に従事している人は、特定業務従事者健康診断のほかに「特殊健康診断」を受けなければならない。
- ストレスチェック
- 50人以上の会社(事業所)では義務で、それ未満は努力義務。
- 年1回実施。
- 全国22大学が共同で行った「ストレスチェックでその後の精神疾患による休職の予測ができるか」ということを調べる研究では、「休職の予測はある程度可能だが、切れ味はあまりよくない」という結果だった。
- ストレスや疲労を把握する機会の1つと考えておくのが適当。
- 「高ストレス」の判定が出ても、本人が申し出をしなければ面談は行われず、高得点の判定が出たことも、上司や人事には知られない。
- 産業医面談の間に心理カウンセラーや保健師による予備的な面談を挟むのもよい。
予備面談は会社への申し出が必要ないので、ハードルが下がる。
- 保健指導
- 定期健康診断の有所見率は40代、50代が少なからずいる会社の多くで60%以上。その多くが血中脂質や血圧、肝機能の異常。
- 健康相談
- いわゆる「保健室」。会社では設置は努力義務になっている。
- 産業医の委任契約に「従業員からの健康相談に応ずること」という1項を入れておくことが望まれる。
- その他、長時間労働の対応、就業の制限・禁止、健康教育、在宅勤務について述べられている。
11.産業医とは何か
「産業医とは何か」では、主に以下のことが述べられています。
- 産業医とは、会社の依頼を受けて成果物を会社に返す。
- 産業医は、就業のための診断を行う。
- 産業医の立場では、治療は行わない。
- 産業医は、「働く人の健康を守る」ために存在している。
- 産業医は、「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」に加えて、「衛生教育」も行う。(「総括管理」を含めることもある)
- 代表的な職務に「職場巡視」がある。
- 最大の仕事は「面接指導」。
最後に
さらにメンタルヘルス・マネジメントの理解を深めたいと思い、本書を読んでみました。
産業医の立場から書かれており、様々な精神的な症状や会社が取るべき実務について、より詳しく書かれていると感じました。
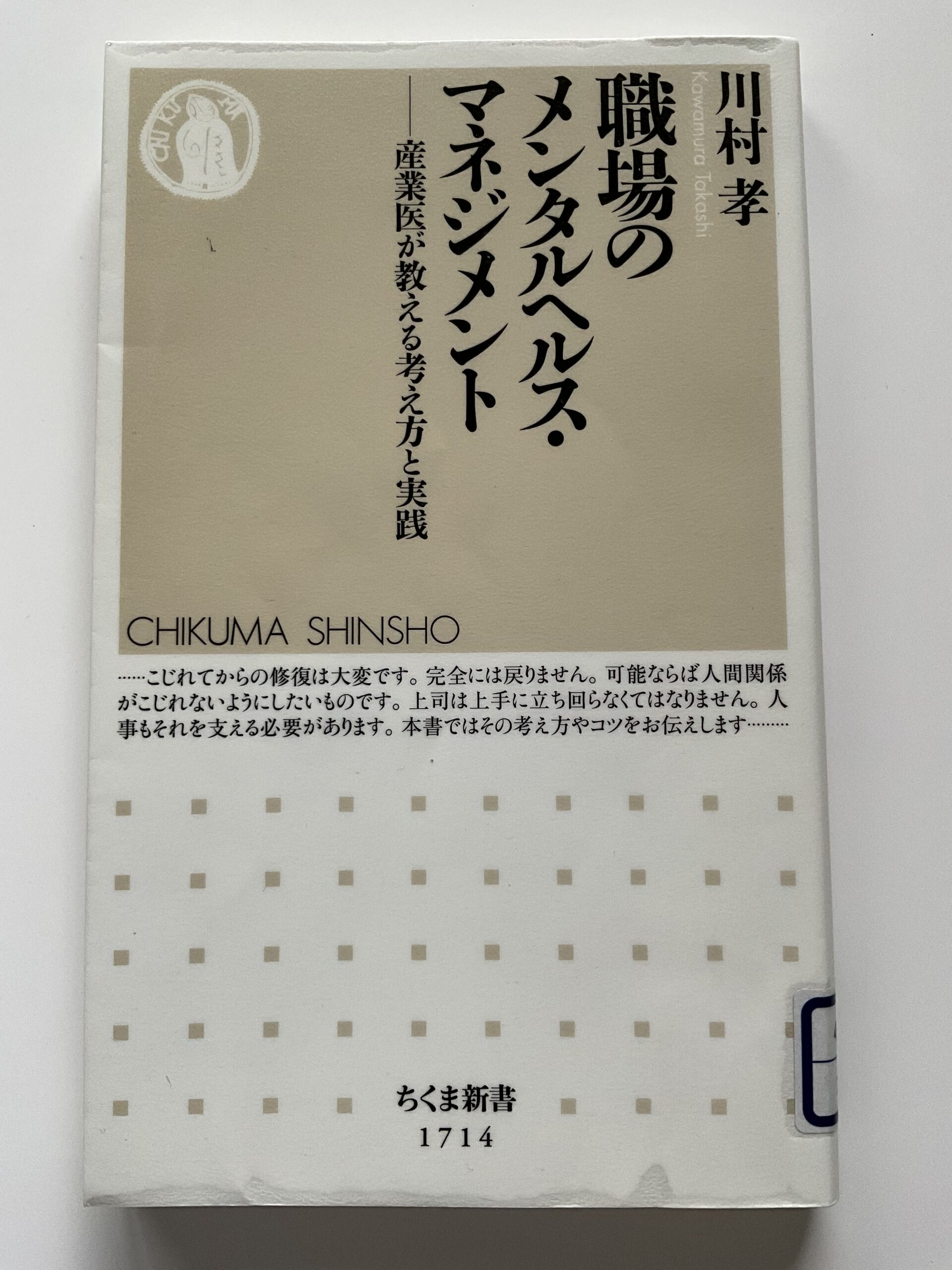
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/474bc9b5.aae640e7.474bc9b6.8b0594b0/?me_id=1213310&item_id=20878347&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5420%2F9784480075420_1_96.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

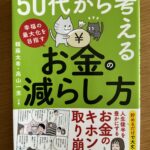

コメント