今回紹介する本は、『「勉強法のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた(藤吉 豊、小川 真理子 著 日経BP)』です。
勉強法の名著100冊のエッセンス1冊にまとめた本で、勉強法の名著100冊に書かれてあった共通のノウハウを洗い出し、ランキングにして書かれています。
本書は、以下の構成になっています。
- 100冊集めてわかった本当に大切な「8つのルール」
- 100冊が進める効率UPの「12のポイント」
- さらにインプット力を高めるための「20のコツ」
- まとめ
- 1.100冊集めてわかった本当に大切な「8つのルール」(ランキング1~8位)
- 2.100冊が進める効率UPの「12のポイント」
- 3.さらにインプット力を高めるための「20のコツ」
- 21位 インプットしたら必ずアウトプットする。
- 22位 「朝」と「夜」を使い分ける
- 23位 合否は「過去問」の使い方で決まる
- 24位 ともに高め合える仲間をつくる
- 25位 疑問を持ったらすぐ調べる
- 26位 音読すると、記憶力がアップする
- 27位 「基礎」の徹底だけでも合格できる
- 28位 他人を気にしない。自分に集中する。
- 29位 継続は力なり。少しずつ積み重ねる。
- 30位 食事も変えると成績も変わる
- 31位 身銭を切る、お金をかける
- 32位 テストでは解ける問題から解く
- 33位 マルチタスクはしない
- 34位 いつやるか? 今でしょ!
- 35位 「圧倒的な量」をこなす
- 36位 勉強内容はこまめに切り替える
- 37位 「自分のレベル」を正しく把握する
- 38位 苦手にこそ「チャンス」がある
- 39位 ルーティンや「儀式」を決めておくと集中しやすい
- 40位 適度なストレスはパフォーマンスを高める
- まとめ
- 最後に
1.100冊集めてわかった本当に大切な「8つのルール」(ランキング1~8位)
「100冊集めてわかった本当に大切な「8つのルール」」では、主に以下のことが述べられています。
1位 繰り返し復習する
- 復習の回数が多いほど、記憶が定着する。
- 1回目の復習は「翌日まで」に。
- イメージやエピソードで覚える。
※脳に「繰り返し覚えたこと」は、忘れにくいしくみがある。
1.復習の回数が多いほど、記憶が定着する
- 記憶は、保持される時間の長さによって「短期記憶」と「長期記憶」に分けられる。
- すべての情報は、一度記憶として蓄積され、その後「重要である」とみなされた情報が大脳皮質に送られ、「長期記憶」となる。
- すぐ忘れるのは、勉強したことが「長期記憶」に移行していないから。
- 「長期記憶」に定着させるためには、「何度も復習」すること。
2.1回目の復習は「翌日まで」に
- 忘却曲線から読み解けること
- すぐに覚え直せば少ない時間で再度思えられる。
- 覚えてから時間が経つほど、もう一度覚えるのに時間がかかる。
- 復習の回数を重ねるごとに、覚える時間が短くなる。
- 復習を繰り返すほど覚えやすくなる。
- 復習のポイント
- 一度覚えたことをそのままにしない。
必ず復習する。 - 1回目の復習は早めに行う。
(遅くとも翌日までに) - 1日後、1週間後、1か月後といったように、間隔をおいて見直しをする。
- 少ない回数で覚えられる人も、たくさん復習しなければ覚えられない人もいる。
自分に合ったペースと回数で復習する。
- 一度覚えたことをそのままにしない。
3.イメージやエピソードで覚える
- エピソードとして覚える。
- 「エピソード記憶」を使うと、忘れにくくなる。
「個人が経験した出来事に紐づく記憶」のこと。 - エピソード記憶の活かし方の例
- 体験を通して学ぶ。実際に自分でやってみる。
- 人に話す。
- 学習マンガを読む。
- 暗記したい内容を用いて頭の中でストーリーを作る。
- 本の記事の内容を頭の中で映像化(ストーリー化)してみる。
- 本の内容、登場人物、世界に入り込みながら読む。
- 「この人物は好き、この言葉は嫌い、この出来事は悲しい」など、感情とともに覚える。
- 「エピソード記憶」を使うと、忘れにくくなる。
- 視覚的な補助を使う。
- 脳は文字よりも、絵や映像といったイメージの方が「覚えやすく、思い出しやすい」ようにできている。
- 関連づけて覚える。
- 新しい知識を覚える時は、自分が知っている知識を関連付けたり、結び付けたりすると覚えやすくなる。
2位 「目的」と「ゴール」を明確にする
- 「どうなりたいか」を考える。
- 「何のために」を考える。
- 「絶対になる!」と強く望む。
- 「なりたい自分」を明確にする理由。
- 勉強に対する意欲が湧く。
- 「何をすべきか」具体的になる。
1.「どうなりたいか」を考える
- 「目標」や「理想」のこと。
- 「なりたい自分」「成功している自分」を強く、リアルに、具体的に思い描くほど、「自信が持てる」「やる気が続く」「理想に向かって行動するようになる。
2.「何のために」を考える
- 「何のために」とは、勉強する「目的」と「理由」のこと。
- 「何のためにこの勉強をやっているのか」という意味付けができているかで、勉強の成果が変わる。
3.「絶対になる!」と強く望む
- 「絶対にそうなる!」「いつまでに実現する!」という立体的な気持が強いほど、成果につながる。
3位 上手な「休息」で学びの「質」が上がる
- 「集中力が続く時間」で区切る。
- 「ポモドーロ・テクニック」で集中のサイクルをつくる。
- 「勉強しない日」をつくる。
- 脳科学の分野では、休憩を挟まずにまとめて勉強する「集中学習」と小刻みに休憩を挟む「分散学習」を比べた場合、「分散学習」の方が記憶に定着しやすいことが明らかになっている。
- 20分~50分に一度の間隔で短い休息を定期的にとる。
- 休憩をとる4つのメリット
- 記憶の定着が良くなる。
- 集中力が保たれる。
- 飽きるのを防げる。
- 肉体的な疲労が緩和される(肩こり、目の疲れ)
- 休憩をとると、「初頭効果」と「親近効果」を活用できる。
- 初頭効果:「最初」に提示された情報は、記憶に残りやすい。
- 親近効果:「最後」に提示された情報は、記憶に残りやすい。
- 「最初」と「最後」の回数が増えるほど、学習効果が高まる。
- 例えば、「3時間勉強」を「50分勉強+10分休憩×3回」に分ければ、「初頭効果」と「親近効果」がそれぞれ3回発揮される。
- 休憩時間の過ごし方の例
- 好きな音楽を聴く。
- ストレッチなどの軽い運動をする。
- 仮眠をとる(目を閉じる)。
- 本やマンガを読む。
- おやつを食べる。
1.「集中力が続く時間」で区切る
- 集中力は個人差があるので、「50分勉強+10分休憩」「45分勉強+15分休憩」「90分勉強+20分休憩」など、自分にあった「勉強+休憩」の組み合わせを見つける。
2.「ポモドーロ・テクニック」で集中のサイクルをつくる
- 「ポモドーロ・テクニック」は、短時間の集中作業を繰り返すことで、1日のうち集中力の高い状態にいる時間を増やし、知的生産性を高める技法。
- ポモドーロ・テクニックのやり方
- タイマーをセットして「25分間」セットする。
- 勉強に没入する。(中断した場合はやり直す)
- タイマーが鳴ったら、5分間休憩する。
- 1~3を繰り返す。
- 「25分間勉強+5分間休憩」を4回繰り返したら、「15分~30分間」休憩する。
- 「これくらい自分が集中し続けられるだろう」と思う時間(30分、45分、60分等)にタイマーをセットする。
↓- タイマーが鳴ったら15分ほど休憩する。
↓ - 同じ方法で再開する。
- タイマーが鳴ったら15分ほど休憩する。
3.「勉強しない日」をつくる
- 「心身がリフレッシュする」「メリハリのついた質の高い勉強ができる」ため、目指す目標が先にある。
- 1週間や3日に1日や半日休む等。
4位 「ごほうび」でドーパミンを活性化させる
- 「ドーパミン」の力を借りる。
- 「ほめ」は勉強の原動力になる。
- 小さな成功体験を重ねる。
- 2種類のごほうび
※ごほうびを受け取るタイミングは結果が出た後。- 目に見えるごほうび:飲食、品物、旅行等
- 目に見えないごほうび:達成感、「ほめられると嬉しい」といった感情的な喜び
1.ドーパミンの力を借りる
- ドーパミンを分泌させる方法のひとつが「ごほうびの設定」。
- 「この勉強が終わったら、ドラマを見よう」「試験に合格したら、旅行しよう」とごほうび設定すると、期待感からドーパミンが増え、勉強の意欲が高くなる。
2.「ほめ」は勉強の原動力になる
- 自分で自分をほめると「自己肯定感が高まる」「自信が出る」「やる気が高まる」
3.小さな成功体験を重ねる
- 問題が解けて「嬉しい」という喜びの感情が湧き上がっている時、脳内にはドーパミンが出ている。
- 勉強のやる気に大切なのは「成功体験」
小さな進歩を積み重ねると、「やればできる」という有能感が得られ、やる気が高まる。
5位 ゴールから「逆算」して計画を立てる
- 逆算して「いつ何をするか」を明らかにする。
- 最終目標と中間目標を立てる。
- 無理はしない。
- 行動計画を立てた方が、立てない時より「学習効果が高くなる」とする説もある。
- 「いつ、どこで、そしてどのようにして自分のゴールに到達するかという計画」を立てた方が目標達成の見込みが高くなる。
- 以下の調査結果もある。
- いつ、どこで勉強するか計画を立てた学生は、立てなかった学生よりも勉強時間が50%長かった。
- いつ、どこで勉強するかを含めた計画を立てていた学生の91%が目標を達成した。
1.逆算して「いつ何をするか」を明らかにする
- 計画を立てる時は、「ゴール(目標)から逆算して考える」のが基本。
- ゴールから逆算して、以下のことを明確にする。
- ゴールと現状の差
- 差を埋めるためにやるべきこと
- 残された日数(勉強に費やせる時間)
- いつまでに何をやるか
- ゴールから逆算して、計画を立てる。
- ゴール(目標)を明確にする。
目標とする点数を設定する。 - 現状を把握する。
過去問を解くなどして、自分の実力を知る。 - ゴールと現状の差を把握する。
目標と現状の点数差と差を生んでいる原因を明らかにする。 - 差を埋めるために「何が必要か」を考える。
何を、どれだけ勉強すれば目標に届きそうか、はっきりさせる。 - カレンダーに「行動計画」を落とし込む。
- 年、月、週、1日の行動計画を立て、タスクを割り振る。
- 休息もあらかじめ決める。
- ゴールから逆算して、いつまでに何をやるか、どんな知識を習得するかを考える。
- ゴール(目標)を明確にする。
2.最終目標と中間目標を立てる
- 最終目標に向かう途中で、中間目標(小さな目標)をいくつか設定する。
- 行動計画を逆算して作る時、年間の行動計画を月単位、週単位、1日単位に落とし込むのは、「過程を短く区切った方が着実に前進できる」「達成度を把握しやすい」。
- 例
- 問題集の数が「3冊」、受験日まで残り「3ヶ月」だとすると、問題集1冊にかけられる日数は「1ヶ月」。
- 3ヶ月÷3冊=1ヶ月に1冊
- 勉強ができるのが「1日2時間」だとすると、1ヶ月の勉強時間は60時間。
2時間×30日=60時間(休みなしの時間)- 問題集のページ数を「60時間」で割れば、「1時間で解くページ数」がわかる。
- 180ページなら1時間で3ページ(180ページ÷60時間=3ページ)
- 問題集のページ数を「60時間」で割れば、「1時間で解くページ数」がわかる。
- 問題集の数が「3冊」、受験日まで残り「3ヶ月」だとすると、問題集1冊にかけられる日数は「1ヶ月」。
- このように、目標を細分化して、小さな達成感を積み重ねることで、「次の中間目標も達成しよう」となる。
3.無理はしない
- 行動計画をつくる時は、「無理な計画は立てない」ことが大切。
- 計画を立てる時の注意点
- 「計画は多少崩れるもの」という前提で、余裕を持って計画を立てる。
- 無理に詰め込まず、調整日を設けておく。
- 優先順位の高いものから予定を組む。
- 「予定通り進んでいるか」を確認しながら進める。
進んでいない時は、原因を突き止め、計画を作り直す。 - 目標が高すぎる(低すぎる)時は、軌道修正する。
6位 スキマ時間を活用する
- 「スキマ時間に何をやるか」を決めておく。
- 「スキマ時間に何をやらないか」決めておく。
- スキマ時間とは、待ち時間や移動時間などの、「予定と予定の間の短い時間」のこと。
- 勉強時間を確保するには、スキマ時間の活用が不可欠。
「長い時間」ではなく、「多くの時間」をつくることを意識する。
1.「スキマ時間に何をやるか」を決めておく
- スキマ時間を上手に活用する3つのポイント
- ノルマ(目標)を決めておく
- 「1日これだけする」「スキマ時間を使って英単語を覚える」など、ノルマ(目標)を決める。
- 「できること」をリストアップする。
- スキマ時間にできることをあらかじめ考えておく。
「5分空いたら」「10分空いたら」「30分以上あるなら」と時間別にできることを決めておく。
- スキマ時間にできることをあらかじめ考えておく。
- 必要なものを準備しておく(カバンに入れておく)
- 必要なものを持ち歩くようにする。
- ノルマ(目標)を決めておく
2.「スキマ時間に何をやらないか」決めておく
- スキマ時間を効率よく活用するためには、「やること」と同様に「やらないこと」を決めるのも重要。
- 「時間がない」は、やらなくてもいいことをやっているから。
- 「勉強時間を増やす」には、「勉強以外の時間を減らす」こと。
- 「無駄な時間をなくす」「やらないことを決める」のが時間管理の基本。
7位 「集中しやすい空間」をつくる
- 「気が散る状況」を避ける。
- 音楽を聴くなら「歌詞なし」で。
- たまには「いつもと違う場所」を選ぶ。
- 環境が変わると集中力も変わる。
1.「気が散る状況」を避ける
- 集中しやすい環境をつくるには、「気が散るものを遠ざける」「集中を妨げるものを最小限にする」ことが大切。
- 集中できる環境づくりの7つのポイント。
- 「自分を誘惑するもの」を目に入れない。
- 雑音、騒音を遠ざける。
静かな状態をつくると、知的作業に有効。 - 今の勉強に必要な参考書だけ置く。
- 机と椅子の高さを合わせる。
椅子に深く腰掛けて、手が机に届く状態で、肘、腰、膝の角度が「90°」になるように椅子の高さを調整する。 - 室内を適温に保つ。
- 「好きな香り」を使う。
アロマオイルには、集中力アップやリラックス効果が期待できる香りがある。 - 定期的に机や部屋を片付ける。
物の整理は思考の整理に通じている。
2.音楽を聴くなら「歌詞なし」で
- 音楽を聴きながら勉強するのは、できればやめた方がいい。
- 音楽を聴きながら勉強するときの注意点
- 日本語の歌詞のない音楽を選ぶ
- 歌詞付きの音楽を流すと、歌詞と勉強の2つの情報が脳内に流れる為、脳の情報処理負担が大きくなる。
- 勉強を始める「10~15分前」と「休憩時間」に聴く。
- 「勉強前に聴く→やる気が出る→勉強する→休憩時間に音楽を聴く」といった繰り返しであれば、音楽を上手に活用できる。
- 聴くのは「復習の時だけ」(単純な勉強の時だけ)にする。
- 日本語の歌詞のない音楽を選ぶ
3.たまには「いつもと違う場所」を選ぶ
- 勉強する場所を変えると、気分転換や集中力アップが期待できる。
- 環境選び、場所づくりで大切なのは、「自分にとっての集中環境」をしること。
8位 一夜漬けはしない。よく眠る。
- 一夜漬けはしない。
- 理想の睡眠時間は、7~8時間。
- 眠れないときの対処法を身につける。
- 仮眠で効率を上げる。
- 睡眠の主なメリット
- 記憶が定着する。
- 記憶が整理される。
- 物事の理解が深まる。
- 体が休まる。
- 癒し効果がある。
- 起きている間の記憶が整理されたり、定着したりするのは寝ている間。
- 眠い時は眠る。その方が勉強には効率がいい。
1.一夜漬けはしない
- 睡眠には「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」がある。
- レム睡眠
体は休み、脳は活発に動いている。浅い眠りの状態。 - ノンレム睡眠
体も脳も深く休んでいる。深い眠りの状態。
- レム睡眠
- レム睡眠中、脳は活発に動いて、昼間入ってきた記憶を整理したり、一時的に覚えていた記憶を永続的な記憶に交換したり、理解を深めたりする。
2.理想の睡眠時間は、7~8時間
- 睡眠は「長すぎず、短すぎない」のが良い。
3.眠れないときの対処法を身につける
- 寝る前に「やったほうがいい」こと。
- 寝る時は、部屋を暗くする。
- 寝る時間の3時間前には食事を済ましておく。
- お風呂は寝る90分前に入る。 等
4.仮眠で効率を上げる
- 長時間の眠りに加え、昼寝(仮眠)をするとことで、「能力が上がる」「認知能力が高まる」と指摘する著者も複数あった。
- 昼寝のメリット
- 脳が休まる。
- 思考の切り替えになる。
- 集中力が上がる。
- 昼寝や仮眠の時間は、著者の多くが「30分以内」。
- 昼寝をするのに大切なこと。
- 目覚めた時にすぐに勉強に取り掛かれること。
- 夜もしっかり眠ること。
- 昼寝をするときの4つのポイント
- 布団には入らない。
- タイマーや目覚まし時計を活用する。
- 寝る前にカフェインをとる。
(カフェインの効果は、摂取から30分~1時間後) - 耳栓やアイマスク等を利用し、音や光を遮断する。
- 睡眠時間、昼寝時間とも個人差があるので、自分で試してベストな時間を見つける。
2.100冊が進める効率UPの「12のポイント」
9位 ノートづくりは「活用」を意識する
- 板書は「考えながら」写す。
- 教科書や参考書を「ノート化」する。
- 「読書ノート」は読み終わったあとで書く。
- 後で活用できるようにする。
1.板書は「考えながら」写す
- 授業中はあえてノートを取らず、話に集中する。
- 話を理解することに集中するのも一つの手。
- あとで活用できるノートをつくる。
- 授業中にノートをとる場合は、「何がポイントか」を考えながら、あとで「見てわかる」「見返したくなる」「活用できる」ノートをつくる。
- あとで書き込めるように余白を多く取る等
- 授業中にノートをとる場合は、「何がポイントか」を考えながら、あとで「見てわかる」「見返したくなる」「活用できる」ノートをつくる。
2.教科書や参考書を「ノート化」する
- 使っているテキストや問題集などに「直接書き込む」こと。
- 「本に直接書き込む」ことの意外なメリット。
- 教科書、参考書、ノートをあちこち見る時間を節約できる。
- 書き写す時間の節約になる。
- 節約して生まれた時間は「覚える」「思い出す」ことに使える。
3.「読書ノート」は読み終わったあとで書く
- ノートやメモを取りながらの「ながら読み」はしない。
10位 学びの基本は「人から教わる」
- 「みんなで教わる」とモチベーションが続く。
- 「成功している人」の話を書く。
1.「みんなで教わる」とモチベーションが続く
- 塾等通うメリットもあるが、合わない場合は無理に通う必要はない。
2.「成功している人」の話を書く
- 「合格体験記」を読むのもおすすめ。
- 「合格体験記」を読む際の注意点
- できるだけ複数の「合格体験記」を読む。
- うのみにしない。
- 自分に合うか見極め、真似できるものは真似する。
11位 スピードや暗記より「内容理解」
- 「理解できるかどうか」が参考書選びの基本。
- 「理解度」を最優先に考える。
- 理解すると記憶しやすい。
- 合格するための必要な「3つの力」
- 「理解力」
- 内容、意味がわかったと心から実感できる力。
- 人間の脳は、理解できないことは、情報として正確にインプットしない。
- 「記憶力」
- 物事を覚えておく(思い出す)力。
- 情報として貯蔵しておくためには、復習や反復学習が必要。
- 「解答力」
- 正解を導き出す力
- 「理解力」
1.「理解できるかどうか」が参考書選びの基本
- 自分に合った理解できる本、参考書を選ぶことが大切。
2.「理解度」を最優先に考える
- 理解せずに先に進んだり、丸暗記をしても、逆に無駄になることもあるので、「着実に理解する」ことが大切。
- 理解しようとしても、どうしても理解できないときは、先に進む。
その時は理解できなくても、ほかの事柄について知識が増えた後で理解できることがある。
12位 学ぶ対象に「興味」を持つ
- 勉強は能動的に。
- 「好きなこと」から掘り下げる。
- 「なんだろう?」思ったら調べる。
- 好奇心を持ち、勉強を楽しんだり、インプットする物事に関心を持ったりすると次のようなメリットがある。
- 「好奇心を持つ」3つのメリット
- 記憶しやすくなる
- 「おもしろい!」「楽しい!」と感動すると、脳は覚えやすくなる。
- 興味を持つとシータ波が出やすくなり、それが神経細胞の増加、記憶力の向上につながる。
- 集中できる
- モチベーションを維持できる
- 興味のあることには、なかなか疲れを感じない。
- 興味のある課題に取り組む人は、活力の高い状態を維持できる。
- 記憶しやすくなる
1.勉強は能動的に
- 受け身で勉強するより、自分の意志で「やろう!」と取り組む方が効率的で勉強は楽しくなる。
- 能動的に勉強をすコツ
- 「自分で」教材を選ぶ。
- 「自分なりの」勉強法で学ぶ。
2.「好きなこと」から掘り下げる
- 勉強に興味を持つには、まず好きになること(勉強以外も可)を見つけること。
見つけたら掘り下げる。新しい目標が生まれて勉強する必要が生じる。
3.「なんだろう?」思ったら調べる
- 「なんだろう?」と疑問に思ったことは調べる。調べて理解できると「そうだったのか!」と気づく。気づくと感情が湧き、覚えやすくなる。
13位 失敗しても反省しすぎない
- 否定的な言葉は使わない。
- 間違えたときこそ「これも学び」と前向きにとらえる。
- 勉強のプロたちは、失敗や思い通りにいかなかったことをポジティブにとらえて、逆に「パワーに変える」ことの大切さを訴えている。
- 記憶とは「失敗」と「繰り返し」によって形成される。
1.否定的な言葉は使わない
- 「無理だ」「できない」と考えると脳が情報にマイナスのレッテルを貼ってしまうので、思考力や記憶力はダウンする。
2.間違えたときこそ「これも学び」と前向きにとらえる
- 失敗したり、間違えた時は「またひとつ学んだ」「勉強になった」と前向きにとらえる。
14位 「人に話す」と記憶が定着する
- 「話す相手」は誰でもいい。
- インプットは「人に話す前提」で。
- 子供の学習能力アップには「質問」が効く。
- 多くの勉強法の名著で「人に話す」「人に教える」ことの重要性に触れている。
- 直接「人」に話すだけでなく、「自分で自分に話す(自分に説明する)」「記憶を頼りに勉強したことを書き出す」だけでも効果はある。
- 「人」や「「自分」に話す効果。
- 理解が深まる。
- 「わかっていないのはどこか」が明らかになる。
- 記憶できる。
- 覚えた情報を整理できる。
1.「話す相手」は誰でもいい
- 「話す相手のレベル」によって、「得られる学び」が変わる。
- 相手が自分より知識レベルの高い人。
自分の知識の足りないところを指摘してもらったり、補ったりしてもらえる。 - 相手が自分より知識レベルの低い人。
何の知識もない人にしっかり説明できれば、自分の理解が深まる。 - 自分と同じ知識レベルの人。
教え合うことで理解を深められる。
- 相手が自分より知識レベルの高い人。
2.インプットは「人に話す前提」で
- 「人に話す前提」でインプットするだけでも効果がある。
- 情報を意識的に脳に入れるためには、基本的にその情報を出力する、いかに人に伝えるという前提が必要。
- 人に伝えることを前提として情報をとること。
- たくさんの情報を思い出すことができる。
- その記憶は時間が経っても消えにくくなる。
3.子供の学習能力アップには「質問」が効く
- 「人に話す」「人に教える」と理解が深まるのは、子供も同じ。
15位 「合わないやり方」に固執しない
- 「みんなと同じ」で疑う。
- 「自分に合う方法」に変えていく。
- 「タイプ別勉強法」で合うやり方を探す。
- 自分に合っていない方法を続けると、なかなか成果につながらない。
- 「自分に合ったやり方」をしたときの4つのメリット
- 勉強していても疲れにくい。
- 勉強がはかどる。
- 楽しく勉強ができる。
- 効率よく集中できる。
1.「みんなと同じ」で疑う
- 疑った上で「自分に合っている」「使えそうだ」と思えば、取り入れる。
- 自分に合わないと思えばやめる。取捨選択をしながら、自分に合った方法を見つけることが大切。
2.「自分に合う方法」に変えていく
- どのように変えていけばいいか、ポイントは次の3つ。
- 「勉強法の変え方」の3つのポイント
- 考え方を変える
- 苦手なポイントを洗い出し、これまでのやり方や考え方を変えてみる。
- ひとつのやり方に執着せずに組み合わせてみる。
- 「守破離の法則」で自分なりの勉強法を極める。
- 守破離とは、物事を学ぶときの順序や基本的な姿勢を意味している。
- 守る :言われたとおりにする。
- 破る :違ったやり方を試してみる。
- 離れる:自分ならではのやり方が完成する。
- 本に書かれている方法を試す→しっくりこなければ他の方法を試す→うまくいったものは続けて、うまくいかなかった場合は、元に戻したりして、うまくいった方法を自分なりに極める。
- 守破離とは、物事を学ぶときの順序や基本的な姿勢を意味している。
- 考え方を変える
3.「タイプ別勉強法」で合うやり方を探す
- 子供のタイプに合わせて、勉強法を探す。
16位 速読を身につける
- 本は「必要なところだけ」理解すればいい。
- 目的によって「本の読み方」を使い分ける。
- 勉強法の名著の多くは、勉強における「速読」をすすめている。
1.本は「必要なところだけ」理解すればいい
- 「わからないところは飛ばしていい」「わからない用語は無視」「必ずしもすべて理解しなくていい」「大事なところだけ熟読する」
2.目的によって「本の読み方」を使い分ける
- 「本の内容によって読み方を変える」:目的によって超速読と普通の速読、熟読する。
17位 タイムリミットを設けると集中力と記憶力が高まる
- 目標には期限を設ける。
- 期限は細かく区切る。
- 「勉強に制限時間」を設けた方がいい理由は次の4つ
- 集中力が高まる。
- 記憶力が高まる。
- やるべきことが明確になる。
- 自分を追い込める。
- 期限を設ける時のポイント
- 目標は期限とセットで決める。
- 期限はっ細かく区切る。
1.目標には期限を設ける
- いつまでに〇〇する。
(1ヶ月以内に〇〇する、今年中に○○するなど) - 目標設定は、できるだけ具体的にする。
(数字を入れるなどした方が、目標が明確になる。)
2.期限を細かく区切る
- 〇分以内に英単語の〇個を覚えるように期限を設ける。
- 1日も午前、午後、夜の3つに分け、それぞれにやることリストを作成する。
18位 やさしい参考書、入門書から始める
- 「薄い」「わかりやすい」「速く読める」ものを選ぶ。
- 入門書は複数読む。
- 児童書やマンガが「いい入口」になる。
- 選ぶ本のレベルを徐々に上げていく。
- 何も分からない状態から学ぶ場合、難しいものから始めると理解ができず、長続きしない。
- 「やさしい参考書」「入門書」から始めるメリット
- 基礎を固められる。
- 速く理解できる。
- とっつきやすい。
- 全体像をつかめる。
1.「薄い」「わかりやすい」「速く読める」ものを選ぶ
- 選び方のポイント
- コンパクトにまとめられている「薄いもの」
- 専門用語が解説されているもの
- 版を重ねているものは、安定した支持を集めている 等
2.入門書は複数読む
- 複数読むとバランスよく概要がつかめる。
3.児童書やマンガが「いい入口」になる
- 勉強の敷居を下げる。
4.選ぶ本のレベルを徐々に上げていく
- やさしい参考書や入門書で基礎を固めたら、徐々に難易度を上げていく。
19位 「運動」が脳を鍛える
- 運動すると記憶力が高まる。
- 効果的なのは有酸素運動。
- 有酸素運動は「1日1回15分」
- 運動は勉強に欠かせない。
1.運動すると記憶力が高まる
- 運動が勉強にもたらす6つの効果。
- 集中力が高まる。
- 学習効果を向上させる。
- 頭がすっきりして注意力が高まる。
- やる気が出てくる。
- 記憶力を高める。
- ストレスに対する抵抗力が高まる。
- 運動すると脳が活性化される。
2.効果的なのは有酸素運動
- ウオーキング、ジョギング、ストレッチ、筋トレ等、一番多く取り上げられていたのは「ウオーキング」。
- 記憶力向上に最も有効なのは、有酸素運動。
3.有酸素運動は「1日1回15分」
- 名著を精査すると、「1日15分程度、有酸素運動する」のがよさそう。
20位 「五感」総動員して学ぶ
- 「五感」をできるだけ「同時」に使う。
- 「視覚記憶」を鍛える。
- スキマ時間は耳から学ぶ。
- 五感を使って学ぶと記憶が定着しやすい。
1.「五感」をできるだけ「同時」に使う
- 五感を同時に使うと脳がフル回転して記憶しやすくなる。
- 働かせる感覚器官が多いほど、長期にわたって記憶されやすい。
2.「視覚記憶」を鍛える
- 「視覚記憶」が強くなれば、映像として覚えておくことができるので、「エピソード記憶」を鍛えることにもつながる。
3.スキマ時間は耳から学ぶ
- 音声コンテンツ
3.さらにインプット力を高めるための「20のコツ」
21位 インプットしたら必ずアウトプットする。
- インプットよりアウトプットに時間を割く。
- アウトプットすることで、脳は「この情報は重要である」と判断し、長期記憶に保存する。
- アウトプットが大切な理由
- 記憶に定着しやすくなる。
- 覚えたつもりがなくなる。
- 覚えた知識の活用方法がわかる。
- インプットしきれていない箇所がわかる。
- インプット:2,3割、アウトプット:7,8割が目安。
22位 「朝」と「夜」を使い分ける
- 夜はインプット、朝はアウトプット中心で
- 「朝」に適した勉強
- 文章問題等、思考力や想像力が求められる勉強、前夜の復習、アウトプット等
- 「夜」に適した勉強
- 暗記等の勉強、思考力をそれほど使わない勉強。
- 記憶は寝る直前に頭に入れ、朝起きてすぐに復習することで脳に定着する。
23位 合否は「過去問」の使い方で決まる
- 過去問が重要な4つの理由
- 出題傾向がわかる。
- 自分の「苦手」がわかる。
- 記憶の定着に効果がある。
- 試験当日の予行演習になる。
- 過去問の使い方
- 同じ過去問(問題)を繰り返して解く。
- 参考書より先に過去問で勉強する。
- 「いつまでにどんな勉強をすればいいのか」イメージでき、勉強の計画が立てやすくなる。
- 最初は問題を解かずに、先に答え(解説)を読む。
- 「この問題はこういう問題になるんだ」という感じで腑に落ちる。
- 過去問は「最新年度」から解く。
- 最新の傾向がつかめる。
24位 ともに高め合える仲間をつくる
- 「自分と同じレベル」の仲間をつくる。
- 仲間をつくるメリット
- モチベーションが保たれる。
- 情報の入口がり広がる。
- 強制力が働く。
- 問題を出し合うことで、理解が深まる。
25位 疑問を持ったらすぐ調べる
- わからないことをそのままにしない。
- 「わからない」という脳の反応の鮮度が高いうちに調べた方が、記憶に残る。
26位 音読すると、記憶力がアップする
- 繰り返して脳に刺激を与える。
- 音読によって、前頭葉を刺激すると、記憶力、集中力、注意力が鍛えられる。
- 音読の注意点
- 立ったあとは座って音読する等、やり方を変え、脳に刺激を与える。
- 何度も繰り返すことが大事。1,2回では効果が見込めない。
- 朝音読すると「入力」→「情報処理」→「出力」と脳のウオーミングアップになる。
- 「人にきかせるつもり」で呼んだ方が、脳が活性化し、音読の効果が高まる。
- 読むスピードを速くすると頭の回転速度が上がる。
- 英文の「棒読み」は意味がない。
- 子供に音読させる時は、途中で遮らない。
27位 「基礎」の徹底だけでも合格できる
- 基礎が完成されていれば、応用問題も解ける。
- 基礎が大切な理由。
- テストの5、6割は基礎問題が出る。
- 応用問題は、基礎問題の組み合わせ。
28位 他人を気にしない。自分に集中する。
- 周囲とではなく、「過去の自分」と比較する。
- 他人の成績を気にしない。
- 過去の自分と比較して、自分が少しでも進んでいれば、脳は喜びを感じる。
- 他人に否定されても気にしない。
- 大事なのは「自分がどうなりたいか」。
29位 継続は力なり。少しずつ積み重ねる。
- 「週末まとめて」ではなく、「毎日少しずつ」。
- 勉強を継続する3つのコツ。
- 週末集中型の勉強はしない。
- 毎日少しずつ行う。
- 「短時間」で構わない。
- 毎日少しずつでいい
- 「簡単な問題」で構わない。
- 「解けた」「わかった」という経験を積み重ねた方が、勉強は楽しくなる。
- 週末集中型の勉強はしない。
30位 食事も変えると成績も変わる
- カフェインは記憶力を高める作用がある。
- カフェインを摂る時の2つの注意点
- 「起床後90分」以上経ってから
- 起きてすぐだと脳への刺激が強くなりすぎる。
- 飲みすぎない。
- オメガ3脂肪酸(DHA、EPA、ALA)、ビタミンB1を摂る。
- オメガ3脂肪酸は「記憶力が改善する」という報告例がある。
- ビタミンB1が欠乏すると、海馬の働きに異常が起こり、記憶できなくなる。
- オメガ3脂肪酸(DHA、EPA、ALA)、ビタミンB1を摂る。
- 「起床後90分」以上経ってから
31位 身銭を切る、お金をかける
- お金を払って自分を追い込む。
- 勉強にお金を投資するメリット。
- お金を払ったことで、自分を追い込める。
- モチベーションが上がる。
- 一度身につけた知識や教養は一生ものになる。
32位 テストでは解ける問題から解く
- テストでは、見直す時間を必ず確保する。
- 解ける問題は確実に解いて、見直した上で、絶対に点数につなげることが大切。
33位 マルチタスクはしない
- 優先順位をつけて、不要なことはやらない。
- 脳科学の知見から、「人間の脳はひとつのことしか処理できない」。
- ひとつのことに集中するメリット。
- やる気が出る。
- ひとつのことをやるとよい点が取れ、自信につながり、やる気が出る。
- 効率的に作業ができる。
- ひとつのことに集中すると、効率的に作業が進む。
- やる気が出る。
34位 いつやるか? 今でしょ!
- 少しでもいいからとにかく始める。
- 時間は有限。どんな時でも「すぐに勉強にとりかかる」。
- すぐに取りかかるための3つのポイント
- 勉強までの段取りを短くする。
- 机のまわりを片付け、すぐにとりかかれるようにする。
- 少しでもいいから始める。
- やる気がなくても作業を開始すると、脳の側坐核という部分が興奮してやる気が出る。
- ちょっとだけやってみようと取りかかる。
- 簡単な勉強から始める。
- 勉強までの段取りを短くする。
35位 「圧倒的な量」をこなす
- 学習の作業量を増やす。
- 「量をこなす」ことの大切さに触れている本が多数ある。
- 量をこなすことによる3つの効果。
- 自分に「役立つもの」と「役立たないもの」がわかってくる。
- 集中力が持続する。
- 結果が出やすい。
36位 勉強内容はこまめに切り替える
- 飽きてきたら、ほかの勉強をした方が効果的。
- ひとつのことばかりやり続けると、脳が飽きてしまい。集中力が落ち、生産性が下がってしまう。
- 複数の分野を組み合わせる3つの方法
- 疲れてきたら教科をがらりと変える。
- 複数の分野を1時間ずつ交ぜて学ぶ
- あらかじめ時間を決めて計画的に複数の分野の勉強をする。
- 複数のスキルを組み合わせて学ぶ
- 英語なら、ライティング(30分)→文法(30分)→リスニング(30分)→休憩
(時間は均等に割り振る)
- 英語なら、ライティング(30分)→文法(30分)→リスニング(30分)→休憩
37位 「自分のレベル」を正しく把握する
- 勉強についていけなくなったら、理解できているところまで一度戻る。
- 自分のレベルが高い時は、どんどん先へ進む。
- ついていけなくなったら、思い切って戻る。
- 勉強でも本でも理解できないものを選ぶと、時間の無駄。
自分のレベルに合った勉強をすることが大切。
38位 苦手にこそ「チャンス」がある
- 何がわかっていないのか、自分を見つめる。
- 苦手なことを勉強する2つのメリット。
- 苦手を克服すると、全体的な力がつく。
- 苦手科目こその伸びしろがある。
- 苦手なことを克服する3つのポイント
- 何につまづいているか考える。
- 急いで克服しなくていい。
- どこがわからないか、自分で見つめる。
- どうしても苦手向き合うのがつらい場合は、自分を無理に追い詰めて克服しなくていい。
39位 ルーティンや「儀式」を決めておくと集中しやすい
- 勉強に集中力が高まる行動をする。
- 勉強や仕事の前にルーティンや「儀式」を決めておくと集中力が上がる。
- ルーティンや「儀式」のメリット。
- 集中力を高める。
- 勉強を習慣化しやすい。
- 「勉強を始める!」というスイッチになる。
- 脳のパフォーマンスを上げる。
- ルーティンの決め方の2つのポイント。
- 「動作をしたら、大事な作業に取り組む」と決めておく。
- 食事と服装はルーティン化しやすい。
- いくつかにしぼって、ローテーションする。
40位 適度なストレスはパフォーマンスを高める
- 小さな我慢を自分に課す。
- ストレスは適度であれば逆にパフォーマンスや集中力を上げる効果が期待できる。
- 勉強をやめたくなったら、あと5分だけやってみる等、自分に少しずつ負荷をかけることで集中力が鍛えられる。
まとめ
- 学びの6つの段階にランキングをあてはめてみると以下の通り。
- 勉強前の準備
- 2位、5位、7位、10位、18位、39位
- 勉強にたいせつなこと
- 9位、11位、15位、16位、17位、20位、23位、25位、26位、27位、33位、34位、35位、37位
- 休憩と気分転換
- 3位、8位、22位、36位
- 学んだ後、復習
- 1位、4位、13位、14位、21位、38位
- テスト中
- 32位
- 心構え、思考力、記憶力などの脳の力の向上など
- 6位、12位、19位、24位、28位、29位、30位、31位、40位
- 勉強前の準備
- 結局は、「自分に合った勉強法」を探すのが近道。
目的を明確にした上で、記憶のしくみにもとづいた方法を試して、自分に合った勉強法を探す。 - なぜ勉強をするのか:自分を広げるため。
最後に
勉強法の名著100冊に書かれていたノウハウをランキングにしたもので、それなりに説得力のあるものでした。
ただ、40位までは多く、試してみることを考えると、20位くらいまでをまとめても良かったのではないかと思います。
自分に合うかどうかやってみないとわかりません。
読んだ時点で、これは自分には向かないなというものもありました。
著者も本の中でのべていますが、まずは試してみて、自分にあった勉強法を見つけることが大事になってくるとと思います。
その選択肢としては、大いに参考になると思います。
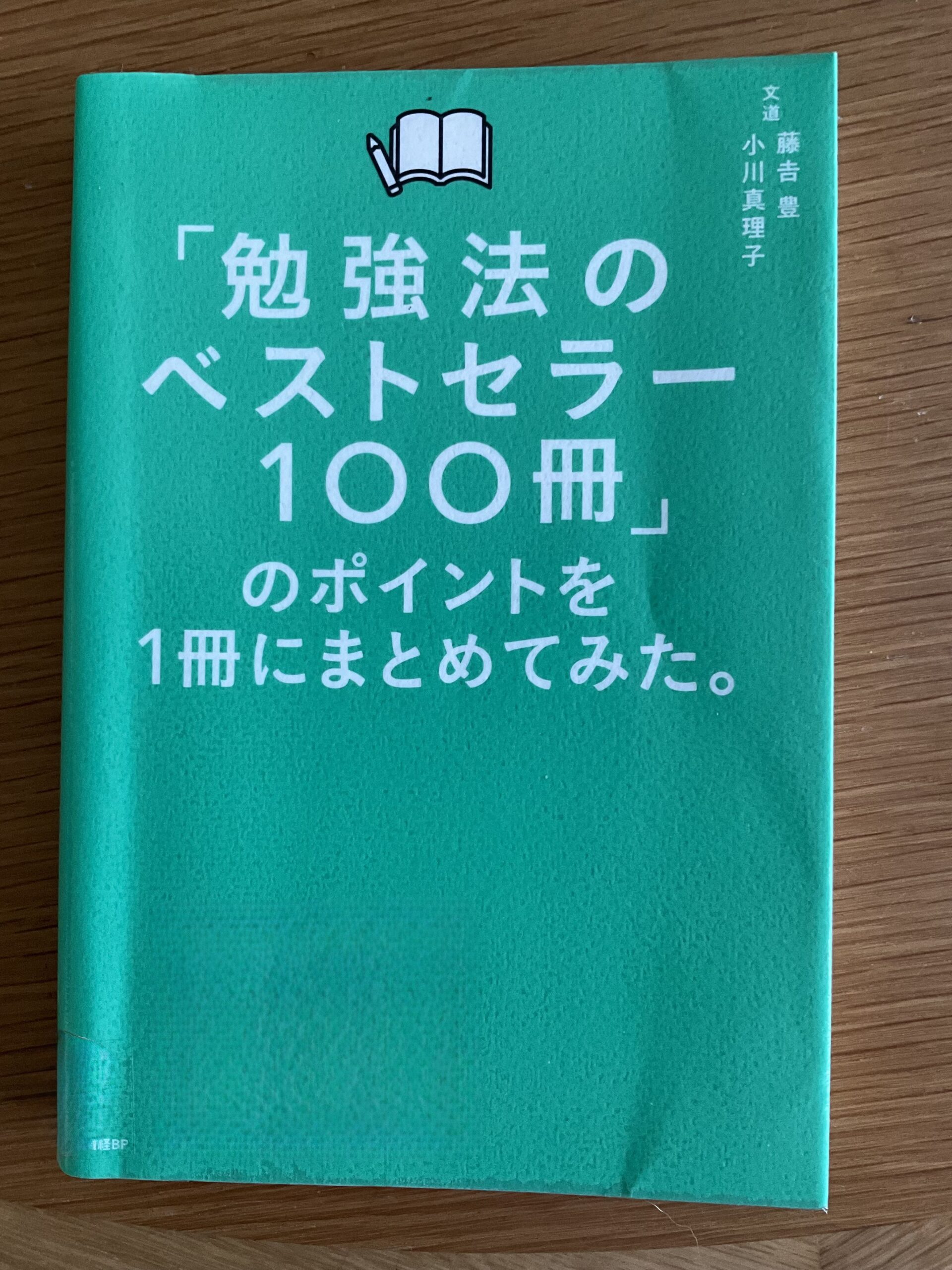
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/474bc9b5.aae640e7.474bc9b6.8b0594b0/?me_id=1213310&item_id=20758941&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1026%2F9784296001026_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

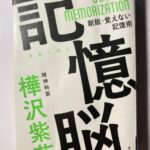

コメント