今回紹介する本は、「一生頭がよくなり続けるもっとすごい脳の使い方(加藤 俊徳 著 サンマーク出版)」です。
本書は、以下の構成になっています。
- 基礎体力がないマズイ脳の状態とは
- 一生頭がよくなり続ける脳のすごい準備運動
- 他人と差をつめる大人のすごい勉強法
- 大人が試験に合格するためのすごい勉強計画
- 脳の基礎体力を上げ続けるすごい習慣術
- この本は、『大人の脳の基礎体力を上げて、「ずっとやりたかったことを最後までやり切る」力を与える書』と著者は述べています。
- 年齢を重ねてくると、自分がやりたいと望むことなのに行動に移せない、実行力の弱った大人が増えていく。
- 脳科学の観点からは、実行力の衰えは、左脳の思考系脳番地の働きが落ちていると言い換えることができる。
- 左脳の思考系を刺激して、実行できる自分を取り戻すことが必要。
- 脳は最初の一歩を踏み出すときに、多くのエネルギーを消費するため、脳の基礎体力がないと実行力はついてこない。
- やりたかったことを始める前に、脳の準備運動が必要。
そして、脳の基礎体力上げておかなければならない。
基礎体力がないマズい脳の状態とは
「基礎体力がないマズイ脳の状態とは」では、主に以下のことが述べられています。
- 脳は初めてのことに挑戦するときに、大量のエネルギーを消費する。
- あまり動かしていない脳番地を意識的に動かすことが大切。
そうすることで、脳の基礎体力を底上げできる。 - 8つの脳番地を動かすトリガーは、体を動かすこと。
- 脳番地の連携が取れないと、集中力、理解力、記憶力などすべての力が弱ってしまい、物事を自らの力で推し進めていくことができなくなる。
一生頭がよくなり続ける脳のすごい準備運動
「一生頭がよくなり続ける脳のすごい準備運動」では、主に以下のことが述べられています。
- 脳内の電気信号が活発になった状態を脳科学では「発火」と呼ぶ。
もっとすごい脳を手に入れるためには、この発火をコントロールすることが重要。 - 入力される情報にインパクトがあればあるほど強い発火が起こる。
- 目や耳から情報がインプットされると、視覚系や聴覚系の脳番地が発火(ファイアリング)する。
- 最初のファイアリングが強ければ強いほど、記憶として残りやすくなる。
- 脳のファイアリングには、短期反応・中期反応・長期反応の3種類ある。
- 入力による最初のファイアリング/短期反応(最初の発火)→ネットワークファイアリング→中期反応(2度目の発火)→ネットワークファイアリング→長期反応(3度目の発火)という順番。
- 短期反応では、視覚系・聴覚系・運動系+感情系の一部が動く。
- 何かを見て反応すれば視覚系脳番地がファイアリングし、聞こえてきた物音に反応すれば、聴覚系脳番地がファイアリングする。
(短期反応は、情報収集に長けた入力系の脳番地が担当しているため、「入力系ファイアリング」と呼ぶ。)
- 最初の入力系ファイアリングで強い短期反応があった後は、そのままネットワークファイアリングが起き、中期反応(2度目の発火)へと引き継がれる。
- 中期反応からさらにネットワークファイアリングが起こると、記憶系や感情系の長期反応(3度目の発火)が起こる。
- 脳の枝ぶりをよくしておくと、理解力、思考力、決断力などが向上するため、短期反応→中期反応→長期反応がスムーズになる。
- 長期反応まで辿り着けば、感情も動いて記憶に残りやすくなる。
- 大切なのは、最初の入力系のファイアリングをいかに強くするか、連携プレーを行うために、各脳番地の働きをいかによくしておくかです。
- 聴覚系と視覚系のファイアリングの強さが大きいと次の脳番地のファイアリングも強くなり、結果として脳がフル回転する。
しかし、興味も関心も小さい情報のファイアリングだと、他の脳番地まで伝達されない。 - 視覚系脳番地のファイアリングを強化するトレーニング法としては、物事をゆっくり、注意深く見ること、眼球をよく動かすこと、波や雲など流動的に形が変わるものを見ること、インテリアについて考える等、空間や奥行きを意識することが挙げられる。
これによって、視覚系の注意力が高まる。 - 聴覚系が仕入れた情報は、視覚系よりも優位に記憶にアクセスする。
- 聴覚系脳番地はさまざまな種類の音に反応して成長していくため、聴覚系全体の働きをよくしたいと思うのであれば、話し声や街の音、音楽など、色んな種類の音を聴くことがポイントになる。
耳を澄ませるなど、意識して聞こうとすると反応が強くなる。 - 思考系脳番地のファイアリングが弱いと実行力が弱まり、傍目にはやる気がないように見えることがある。
- 視覚系が動かないと、思考系もぼーっとしてしまいがち。
- 頭痛がする等痛みがあると、痛さを感じることで、思考系の70%くらい使われてしまい、他のことができなくなってしまう。
- 五感でキャッチして感情が動いたものなど、思考系はそれと連動してファイアリングが起こるので、あちこちに気が向いてしまいやすい。
- 気がかりなことがあれば、思考系が多く支配される。
- 勉強に集中して取り組みたい、自分とじっくり向き合う時間が欲しい、そんなときは入力系ファイアリングのトリガーとなる、音、匂い、目に入ってくるものを極力減らす。
- 思考系をファイアリングさせて強化したい場合のキーワードは、「対比」と「時間軸」。
- 「対比」するものがあると、思考系はファイアリングしやすい特徴がある。
- 考えていることを書き出して見える化すると、それをどう改善していきたいかの「対比」が明確となって思考系が動きやすくなる。
- 「時間軸」は、時間的に階層を分けて考えることで、ファイアリングしやすくなることを利用する。時間を”見える化”することがポイント。
- 思考系ファイアリングで欠かせないのが、好奇心や未来への希望。
- 未来へのスケジュールを立てることで、思考系はファイアリングしやすくなる。
- 「1日」や「1週間」などの短い期間でスケジュールを立てると、他の7つの脳番地を動かしやすくなる。
- 理解系脳番地は、目や耳から入ってきた情報を理解したり、わからないことを推測して理解しようとするときに働く。
- 理解系は、自身が興味を持って考えたりすると働くので、「これについて学ぶぞ」と”基準”を明確に持つことで、強いファイアリングが起こせる。
- 理解系のトレーニングとして有効なのが、「茶々を入れる」こと。
- 「それって本当?」って茶々を入れ、自分なりの事実を検証する。
- 想像力を広げることとして、写真を撮る、図を描く、絵を描くなどの行動も想像力を刺激し、特に右脳の理解系の強化に役立つ。
- 人目のない場所なら、ぶつぶつ独り言を言うのも効果的。
「今度の休み〇〇へ行こう」「何で行きたいと思ったのか」等、自己分析を交えて独り言を言うと、自分への理解が深められて、一石二鳥。 - 記憶系ファイアリングは、海馬をいかにコントロールするかにかかっている。
- 海馬が働かなくなると、一気に注意力が散漫になる。
- 海馬がファイアリングするためには、理解系がしっかり働いて、「この刺激は昔の刺激とここが違って面白い」と違いを説明することが重要。
- ぼーっとしがちな時は、海馬が低酸素に陥っている可能性が大なので、海馬を休ませる。
- 計画を立てることで、運動する以上に運動系脳番地は働きだす。
- 運動系脳番地は他の脳番地をファイアリングさせるトリガー。
運動をおろそかにしていると、脳全体のファイアリング能力が低下して、頭はよくならない。 - 運動系脳番地のファイアリングは、海馬を含めた長期記憶とも繋がりやすいため、記憶力の向上という面からも運動は欠かせない。
- デスクワー クの人は、1日最低1時間歩くといいが、まずはいつもより多く歩く意識を持つこと。
- 歩く以外にもストレッチや筋トレ、音読でもファイアリングする。
- 運動以外でも、行動計画を立てることも運動系をファイアリングさせる。
- 運動系脳番地で大きな領域を占めているのが、「運動企画」という分野。
- 運動企画は、スケジュールを組んだり、行動計画を立てたりするときに働く。
- 目標が目標で終わる人は、思考系を働かせるところで終わっていることがほとんど。
- 運動企画を使って、目標を達成するための道筋を考えて、行動できる人が賢くなれ、試験合格までの最短ルートを歩める。
- 日常生活の小さなことや1日のスケジュールから行動計画を立てるようにして、トリガーである運動系をファイアリングしやすい状態にする。
- 言語化力を鍛えることで、感情系脳番地をコントロールする。
言語化に苦手意識を持つ人ほど、感情系を上手にファイアリングできていないし、他人に同調しやすくなる。 - 自分の言葉で感想等伝えるのは左脳の感情系、苦手な人はここが弱い傾向にある。
- 左脳の感情系をファイアリングさせて強化するには、日記を書くのがおすすめ。
- 文字化して、可視化することでファイアリングしやすくなる。
- 自分の心に声を傾けて、感じていることをそのまま文字にする。この時なぜそう感じたのか考えてみるとよい。
- ネガティブな要素を取り除くことも重要。美しい景色、音楽に触れるのもよい。
- 伝達系脳番地は、文字や言葉で誰かに何かを伝えるなど、アウトプットするときにファイアリングする。
- 独り言を言う、日記や音読でもファイアリングする。
- 伝達系脳番地がファイアリングすると、視覚系、聴覚系、運動系、理解系も連動して働くため、伝達系の強化はネットワークファイアリングの強化にもつながる。
- ファイアリングもオフしないと、脳が疲弊して、調子が上がりにくくなる。
- 脳の疲れを感じる前に、20~30分に1度は意識的に脳シフトを行うと、特定の脳番地の酷使を回避でき、脳のコンディションキープに役立つ。
他人と差をつめる大人のすごい勉強法
「他人と差をつめる大人のすごい勉強法」では、主に以下のことが述べられています。
- 大人になるほど落ちているのは記憶力ではなく、検索力。
記憶したことを引っ張りだしてくる力が弱くなっている。 - 長期記憶も復習して繰り返し引っ張りだしてくることで、記憶にアクセスした際の検索上位にすることができる。
- 勉強している時は、ワーキングメモリという箇所が働く。
- ワーキングメモリは、限られた時間内で作業をするときに使用する脳内の時空間のようなもの。
- ワーキングメモリは、一時的な作業空間でしかない。
- 長期記憶から繰り返し引っ張りだしてくる復習のタイミングは、朝学んだことを日中に何度も思い出しながら、こまめに出し入れすること。
- 小刻みな学習ができない場合は、遅くとも「72時間(3日以内)」に復習を2回する。
3度目の復習のタイミングは「168時間(7日)以内」。 - 勉強するときは、「1テーマ1本勝負」が基本。
- 1度に複数のことをすると、情報の干渉が起こる。
- 脳は特性を考えると、長時間ダラダラと勉強するのは非効率的。
- 大人脳を効率的に働かせるには、時間は必要ない。
- 大人脳にとって効率のいい勉強は、次の3つ。
- 飽きっぽい脳の特性に合わせて、1回の勉強の目安を20分くらいまでにした「小刻み学習」をする。
- テーマ学習で長期記憶のフォルダを作りながら勉強する。
- 学んだことを脳内でクルクル回す「余韻学習」も含めて、勉強時間を設定する。
- 長時間勉強は、脳の準備運動がしっかりできていて、基礎体力が身についている人でないと、脳がファイアリングせず、効果が出ない。
- 大人脳が効率よく勉強するための時間の目安は、20分。
20分で区切りをつけて、脳をリフレッシュさせてから、また20分取り組むその繰り返しがベスト。 - 週末に120分勉強するより、1日10分を12日間続けた方がよい。
- 脳の特性からも、小刻み学習を会得しないと、長時間勉強を脳は受け付けてくれない。
- 脳は飽きやすく疲れやすいので、長時間の勉強では、小さなファイアリングが少ない回数しか起こらない。
強いファイアリングを起こすためには、短時間の学習で新鮮さを脳に与え、ファイアリングのピークを何度も起こすのが効果的。 - それぞれの脳番地を効率的に働かせるポイントは5分弱のクイック休憩。
5分弱の短い休憩をこまめに取る。 - 「最大20分の小刻み学習+5分弱のクイック休憩」の組み合わせが大人脳にとっては効率がいい。
- 休みすぎると、勉強を再開したいときに、脳番地は働こうとしない。
- 一気に複数のテーマを並行して勉強するのはNG。
その時間に勉強することは、1テーマに絞ることが、小刻み学習の鉄則。 - 平日は朝に決めた1テーマを1日かけて小刻み学習する。
- 朝5分、10分でもいいので、テーマにした問題に取り組んだり、テキストを読んだりできると、朝のクリアな脳にしっかりインプットできる。
- その日にこまめに思い出して、思考を巡らせることで、小刻み学習になる。
- 「もう少しでわかりそうなのに」という状態で中断されると、脳の中でネットワークファイアリングしやすくなる。その結果、記憶が定着しやすくなる。
- 1日1テーマを強く自分に言い聞かせて実行する。
- 勉強+ウオーキングの「余韻学習」がもっとすごい脳を育てる。
短期反応+中期反応+長期反応とファイアリングは伝導していくが、3番目の長期反応の「余韻」をうまく利用すれば、簡単にすごい脳を育てていける。 - 長期反応を起こすコツ(30分勉強時間が取れる場合)
- 勉強時間20分設定し、残りの10分でウオーキングする。
(10分のウオーキングが「余韻学習」)
- 勉強時間20分設定し、残りの10分でウオーキングする。
- ウオーキングは運動系脳番地を刺激して、脳全体を活性化させる効果がある。
歩きながら直前に勉強した内容を脳内で振り返り、考えることで、学んだことの脳への定着率が格段にUPする。 - 学んだことを脳内で繰り返す頻度が高いほど、長期記憶に刻まれやすい。
- ウオーキングできない場合は、5分~10分程度程度背伸びや肩を回したり、軽くストレッチをして、運動系脳番地を刺激して、脳内で振り返るといい。
- たった5分さえも集中できないときは、割り切って諦める。
- 大人の勉強には、「切り上げ力」が求められる。
切り上げるという強い自力オフができると、脳はリフレッシュできる。
- 大人の勉強には、「切り上げ力」が求められる。
- 初めて目にするものを理解すること、苦手な分野を学習することが、脳は得意ではない。
- 初めての分野、苦手な分野を勉強するときのコツは、超ゆっくり学ぶ「スーパースロースタディ」。
超ゆっくり学んだ方が、最終的に効率が良くなることが多い。
- 初めての分野、苦手な分野を勉強するときのコツは、超ゆっくり学ぶ「スーパースロースタディ」。
- 初めてのことや苦手なことを学ぶ時は、スピードを追い求めてしまうと、大切な情報や細かな情報を見落としてしまう。
- 勉強もまずはゆっくり取り組んで、その情報に慣れ、見極める目を育てていく時間が必要。
- 自分の中で芽生えた疑問や閃きなどの自家発電をエンジンにして学ぶことで、自然と理解度は深まり、勉強との親和度が高まってくる。
そうなってくると、視覚系や聴覚系の情報収集能力の精度が高まり、必要な情報を入手しやすくなる。 - まるっきり歯が立たない問題に出会ったときも、その1問にじっくり時間をかけて取り組む「スーパースロースタディ」が有効。
- 違う問題を100問やるより、10問の問題を10回やる。
- 学んだことを記憶に送り込むためには、1つのテキストを最低3回は繰り返して学習する方が、深い理解が得られる。
- 取り組んだ項目は、テキストの目次に日付を入れて、”時間軸”を可視化する。
- 勉強した日付を入れることで、学習を思い出として残すことができるため、エピソード記憶として、長期記憶に残りやすくなる。
- テキストの2回目も日付を入れる。
- 目次に日付を入れるとき理解度を◎、〇、△、×を記入すると理解不足がわかり、その後の学習を進めやすい。
- 3回目がおわったら、△、×をスーパースロースタディで学んでいく。
- 朝は、脳がファイアリングしやすい最高のタイミング。
朝、10分学習を毎日続ける。 - 朝に情報や知識を与えることで、強いファイアリングが起きると、中期→長期反応の自家発電能力が高まって、日中や夕方以降まで学習能力が高まる。
- 本当に苦手なものがあればあるほど、対面で話を聞くことが、苦手意識を払拭する鍵になる。
大人が試験に合格するためのすごい勉強計画
「大人が試験に合格するためのすごい勉強計画」では、主に以下のことが述べられています。
- 資格試験合格を目指す場合において欠かせないのは、運動系脳番地が管理している「運動企画」。
- 運動系は計画や企画立案などの方が得意。
計画を立てることで、運動系が活発に働き、その勢いに負けて思考系も動かざるを得なくなる。 - 具体的なスケジュールの組み立て方
- 土日が休みの社会人の場合
- 〔平日の勉強時間×日数+土日の勉強時間×日数=総勉強時間〕を割り出す。
- 例:平日:30分×5日間=150分、土日:60分×2日間=120分
※1週間に費やせる勉強時間は270分
- 例:平日:30分×5日間=150分、土日:60分×2日間=120分
- 〔平日の勉強時間×日数+土日の勉強時間×日数=総勉強時間〕を割り出す。
- テキストの内容と自分の現状の理解度、理解するまでのスピードを考慮して、スケジュールを立てていくことがスタート地点になる。
- モチベーションを維持しつつ、脳が働きやすいようにスケジュールを立てるポイントは「100日」で区切ること。
- 最も重要なのは、最後の100日の使い方。それ以前は、最後の100日のための助走期間のようなもの。
- 年間スケジュールの立て方
※1年365日を「65日+100日+100日+100日」に分けて考える。- 勉強スタート時に模擬テストを実施。
- テストの出題形式と自己の現在の理解度を把握する。
- 最初の65日は脳のペースアップに費やす期間。
- 勉強する内容と親密度を高めていく。
- 最初の100日でテキストの全範囲を履行する。
- 2回間の模擬テストを実施。
- 次の100日でカテゴリー学習をする。
- 3回目の模擬テストを実施
- 最後の100日で合格に必要な点数を確実に取れるようにしていく。
- 勉強スタート時に模擬テストを実施。
- 「1」について、
- アウトプットの形式を事前に知って、そこに向かって勉強していくのが最も効果的。
- 模擬テストが終わったら、問題のカテゴリーごとにパーソナルスコアをつける。
- 絶対に間違えない:◎
- ほぼ理解しているが、出題形式によっては間違えることがある:〇
- 理解があいまいで、解答に迷う。間違えることもある:△
- ほぼ理解できていない、運よく正解することもある:×
- 「2」について、
- 脳が日中にきちんと働く生活サイクルに少しでも近づけて、脳のペースアップを図る。
- 自分を勉強する内容との親密度を高めておく。
- テキストをパラパラ見て、興味のある所から親密度を高める。
- 「3」について
- 本格的に勉強を進めていく。
- 模擬テストは100日おきに実施するのがおすすめ。
- 合格ラインと自分の距離がどれくらいあるかを把握することが、脳のエンジンになる。
- 思考系脳番地は、可視化されたものにファイアリングしやすい。
- 模擬テストの結果が、脳を定期的にファイアリングさせてくれる。
- 人間の長期記憶は、だいたい3ヶ月で埋もれてしまうので、100日おきにテストを繰り返すことで、記憶を更新し、自分が今何を学ぼうとしているのか見失わないようにしておくことが大切。
- パーソナルスコアも必ず更新する。
- 最初の100日では、試験に必要な勉強を1周するのが目標。
- この100日で全範囲を履修するための計画を立てる。
- テキストを進めるのは、テープごとに区切って取り組むのが鉄則。
- テーマの塊ごとに勉強すると、長期記憶に保管される際のフォルダが作られて、AやBというラベルを貼り付けたわかりやすい状態で保管できる。
すると、記憶を引き出しやすくなる。 - テキストの目次に日付を入れておくのもおすすめ。
- 好きなテーマから始めてもよい。
- 「4」について
- 再度模擬テストを実施する。
- テーマごとに、◎、〇、△、×をよりクリアにはっきりさせておく。
(◎:確実にできる、〇:できる、△:曖昧、×:できない) - 最初にすべきなのが、「なぜできない」の分析ではなく、「なぜできたのか」の分析。
- ◎、〇の問題が「なぜできたのか」分析する。
- この100日の目標は、「できない:×」を可能な限りなくし、「曖昧:△」までは昇格させる。(△が〇なら理想)
- △、×問題は、「カテゴリー学習」をする。分野やテーマごとに勉強内容を区切る。
- 今自分が取り組む課題を明確にしながら、△が〇になるまで繰り返す。
- どうしてもできない問題は、「スーパースロースタディ」で時間をかけて理解につなげていく。
- 「5」について
- ラスト100日、合格に必要な点数を確実にしていくプロセス。
- 模擬テストを実施する。
- テストの後には、パーソナルスコアもつける。
- △を〇や◎にする。
- なぜ、その答えになるか説明できれば「〇」。
- テスト本番に確実に点数を取るためには、冷静に「曖昧:△」を見極めることが重要。
- 7日前にも模擬テストを実施する。
- 曖昧な△を潰していくことに注力する。△を〇にした方が得点に結びつきやすい。
- 7日前からの学習では、1日1カテゴリーや1教科を目安に総復習する。
- カテゴリーが10個なら、10日前から総復習を開始する。
- 最後の7日間でしっかりカバーすることで、長期記憶がら学習したことを引っ張りだしてきて、ワーキングメモリを働かせ、学んだことの長期記憶の取り出しやすい場所に仮置きする。
- 3日前くらいまでに「◎」の復習は終わらせて、前々日と先日に「〇」に近い「△」や自信のない「△」に取り組む。
- テストと同じように、同じ制限時間で模擬テストをする。
- ラスト100日、合格に必要な点数を確実にしていくプロセス。
- 持ち時間が3ヶ月の場合、30日単位でスケジュールを区切る。
- 日数が少なくなっても、カテゴリーごとの塊で学習するのが肝心。
- 30日前になったら、模擬テストを受ける。
- 残り30日間は、曖昧な「△」を減らし、「〇」と「◎」を増やす。
- 「△」や「×」を潰していくとき、効率よく「◎」に昇格させていくポイントは、テキストや過去問から間違った問題のみピックアップして横断的に問題を解く。
- 土日が休みの社会人の場合
- 勉強を効率よく進めるためには、脳をリフレッシュさせることも必要。
我慢ばかりでストレスを溜めることは、脳にはプラスに働かない。 - 脳は、勉強以外の色んな体験をすることで刺激を受け、8つの脳番地がバランスよく働く。
脳の基礎体力を上げ続けるすごい習慣術
「脳の基礎体力を上げ続けるすごい習慣術」では、主に以下のことが述べられています。
- 最初に取り組むことは、睡眠を見直し、脳を活性化しやすいベースを整えること。
- 夜型は長期的には損をしている。
- 夜の脳トレはしっかり眠ること。
- ちゃんと眠っていないと、学習してインプットしたことが記憶に定着されにくく、勉強に費やした時間に対するリターンが得られない。
- 眠気がなくなるだけで、思考系脳番地のパフォーマンスは格段に上がり、脳全体がしっかり働くようになる。
- 思考系が最も休めるのが、ノンレム睡眠。
- 夜は難しい課題に取り組むのは諦めて、さっと寝るのが得策。
- 日中にしっかり体を動かさないと、寝ても脳はしっかり休めていない。
- 日中の脳の使い方が睡眠に影響を与えている。
- しっかり眠ることで、日中のパフォーマンスが上がり、日中を活動的に過ごして、夜もまたよく眠れる。このサイクルに持っていくこと。
- 座りすぎると不健康になる。
- 日頃から歩くなどして、活動量を増やすことが大事。
- 思考系、運動系を活性化させる方法の1つとしておすすめなのは、わざと負けるゲームをすること。
- いちばん簡単な方法は、「1人後出しジャンケン」でわざと負けるようにすると、より強いファイアリングを起こせる。
- 右手でグーを出したら、1拍遅れて左手でチョキ、そのまま続けて右手でパーを出したら、左手でグー。
リズムよく続けると、脳の柔軟性と機動性の向上が期待できる。 - 「脳スイッチ呼吸法」
- 体の力を抜いて目をつむり、鼻から5秒かけて息を吸い、口から10秒かけて息を吐く。
吸って、吐いてで15秒の呼吸を何度か繰り返す。 - この呼吸法は、脳のコンディションを整えるのに最適、
朝・昼・夜に3~5分続けるとよい。 - 試験本番前にこの呼吸法をすることで、集中力と注意力をアップさせられるので、ケアレスミス対策にも効果的。
- 体の力を抜いて目をつむり、鼻から5秒かけて息を吸い、口から10秒かけて息を吐く。
最後に
前著に続けて、さらに脳のトレーニングについて理解を深めたく本書を読んでみました。
本書では、脳の基礎体力を上げることと、脳のファイアリングについて主に述べられていました。
本を読みながら、これは自分が取り入れるとしたら合わないなという事例もありましたが、まずは、自分に合う方法を取り入れて実践してみると効果が感じられるかもしれません。
いくつになっても勉強しつつ、脳を効果的に使い、さらに認知症にならないように努めていく大切さを改めて感じました。
関心のある方は、手に取ってみてください。
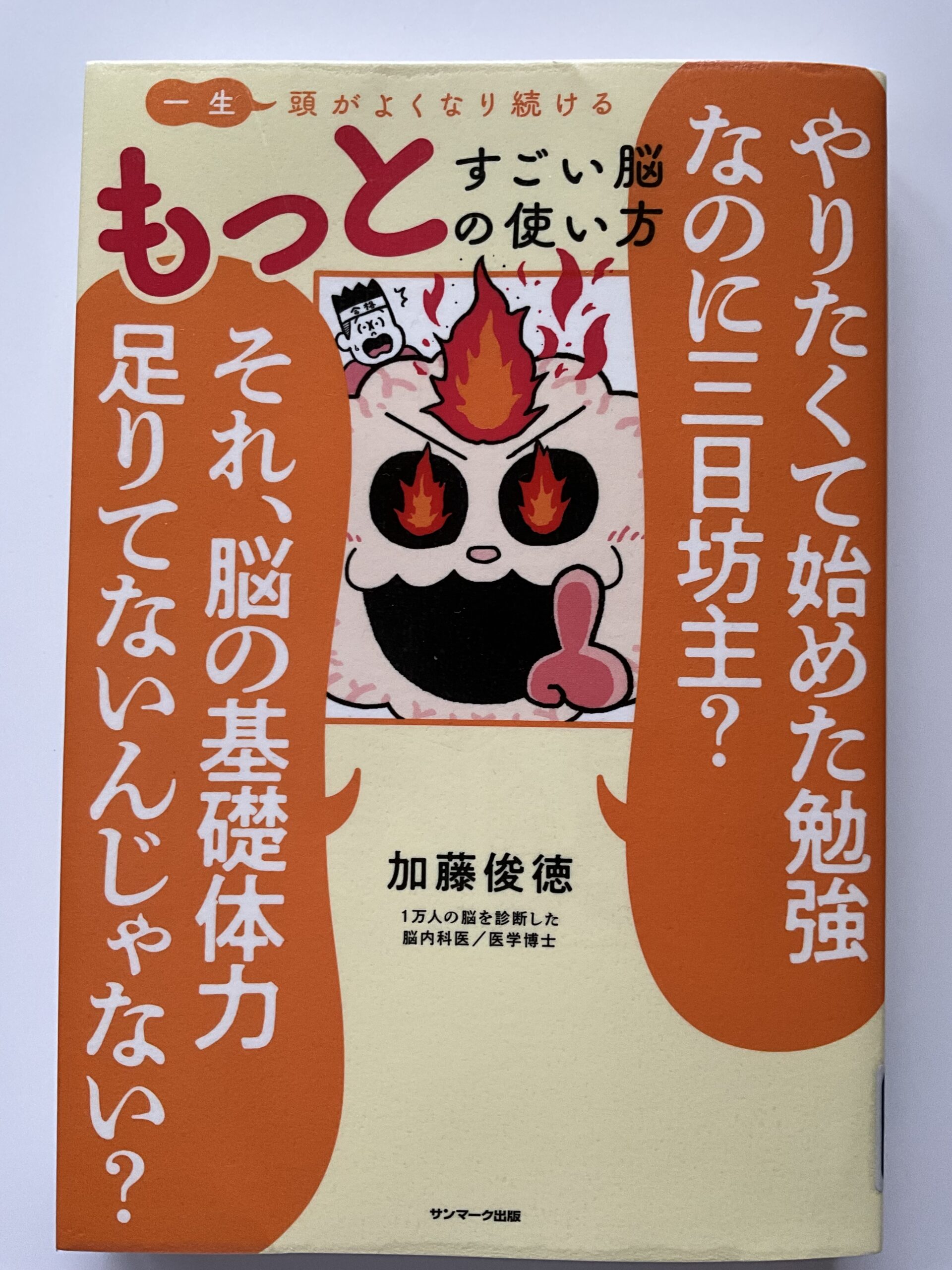
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/474bc9b5.aae640e7.474bc9b6.8b0594b0/?me_id=1213310&item_id=21213155&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1392%2F9784763141392_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

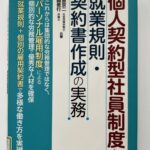

コメント