今回紹介する本は、「1万人の脳を診断した名医が教える 「物忘れしなくなる!脳の使い方辞典」(加藤俊徳著 永岡書店)です。
本書は、以下の構成になっています。
- 脳の役割ごとに8つの「脳番地」に分かれている
- 「一瞬、やることを見失う・・・」系もの忘れ
- 「人の名前が出てこない・・・」系のもの忘れ
- 「できていたはずなのに・・・」系のもの忘れ
- 「ついうっかり忘れもの・・・」系もの忘れ
- 「言葉がでてこない・・・」系もの忘れ
- 「仕事でのミスが増えた・・・」系の心配事
- 「ときめきがなくなった・・・」系の心配事
- エピローグ
脳の役割ごとに8つの「脳番地」に分かれている
『脳の役割ごとに8つの「脳番地」に分かれている』では、主に以下のことが述べられています。
- 8つの脳番地は、お互いに連携して動いている。
- 脳番地は、どこか衰えても、物忘れやうっかりミスなどの「脳の小さな問題が起こる」。
- 8つの脳番地について
- 思考系脳番地:「こうしたい」「ああなりたい」を発信する司令塔。
- 思考だけでなく、意欲、創造、集中、判断、計算などの高度な機能に関わっていて、「脳の司令塔」として、他の脳番地を動かしている。
- 感情系脳番地:喜怒哀楽や好き嫌いを生み出し、他人の感情を理解する。
- 記憶系との関わりが深く、感情が伴う経験は深く記憶に残る。
- 老化が遅いのも特徴で、感情豊かな日々を送っていれば、一生涯成長し続ける。
- 伝達系脳番地:人とのつながりを豊かにするために欠かせない脳番地。
- 自分の気持ちや考えを人に言葉で伝えるときや、ジェスチャー、絵、図等で意図を伝達しようしようとする時も、この脳番地が働いている。
- 人とのつながりを豊かにするために欠かせない役割を果たしている。
- 理解系脳番地:見聞きした情報を集めて、その内容を理解する。
- この脳番地を成長させるカギは好奇心。
好奇心を持っている人は、高齢になってもこの脳番地をうまく育てていくことができる。
- この脳番地を成長させるカギは好奇心。
- 運動系脳番地:体がスムーズに動くのは、他の脳番地と連携がとれている証拠。
- あらゆる動作を他の脳番地と連携して行う。
- 聴覚系脳番地:音や言葉を「情報」として脳にインプットしている。
- この脳番地が衰えてくると、音や言葉を認識しづらくなる。
- 意識して「聞く」姿勢が、大切になる。
- 視覚系脳番地:目に入る大量の情報を脳にインプットしている。
- 文字、光、形、空間、色などを判別して、それらの情報を集めてインプットしている。
- 「見る力」をつけるには、目的を持って主体的に見る姿勢が大切になる。
- 記憶系脳番地:思考系や感情系とつながりながら、記憶情報を采配する。
- 記憶中枢の「海馬」を中心に情報を記憶として定着させたり、蓄積した記憶を引き出したりする働きをしている。
- 思考系脳番地や感情系脳番地とのつながりが強いのが特徴で、思考系をさかんに使って得た知識や感情を大きくゆり動かした出来事は、記憶に定着しやすい。
- 思考系脳番地:「こうしたい」「ああなりたい」を発信する司令塔。
「一瞬、やることを見失う・・・」系もの忘れ
『「一瞬、やることを見失う・・・」系もの忘れ』では、主に以下のことが述べられています。
「いま、何をしようとしてたんだっけ?」というもの忘れ
- 「あれやらなきゃ」「こうしたい」「こうしよう」といった、”自分のやること”は前頭葉の思考系脳番地で生み出されている。
- 前頭葉の思考系の力が落ちてくると、マルチタスクで物事を進めるのが困難になり、同時にふたつのことをやろうとしたときに、どちらか一方を忘れてしまう傾向も目立ってくる。
- 立ち上がった瞬間、何をしようとしていたのか忘れてしまった。
- 「立ち上がる」という動作を挟むことで、思考の連続が途絶えてしまう。
- 思考系から運動系へと脳の働きがシフトした瞬間に思考が途切れ、「やろうとしていたこと」がふっと消えてしまう。
- 「弱くてあいまいなタスク(やるべき作業)」は、何らかの動作が挟まって思考が一瞬途切れただけでも消えてしまいやすい。
- 「あれ、いま何をしようとしてたんだっけ?」という事態があまりに頻繁に起こるようなら、それは思考系脳番地や記憶系脳番地などにおいて、「脳の連続性を維持する力」が落ちてきたサイン。
- 何を探しに来たのか忘れてしまった。
- 2階に何かを取りに来たのに、何をしに来たのか目的を忘れてしますのも、「階段を上がる」という強めの運動刺激が介在したことが原因。
- 海馬が関係しているが、海馬の記憶保持機能は、ずっと注意を向け続けないと眠ってしまいやすい特徴がある。
- 何かずっと注意を向け続けるか、注意をそらすような強い刺激を挟まないようにする。
- 「立ち上がる」という動作を挟むことで、思考の連続が途絶えてしまう。
- おすすめのトレーニング
- 先の展開を読んで、脳内リハーサルをしておく。
- 行動の一連の流れを事前にシミュレーションしておく。
- 何をしようとしていたかを忘れがちなのは、その「何か」をちゃんと記憶していない点が大きく影響している。
- 「あれやらなきゃ」と思い立った際、行動に移す前に「やること」をしっかり脳にインプットする。
- 行動の一連の流れを事前にシミュレーションしておく。
- やることを付箋にメモして目立つところに貼っておく。
- 何か思いついた時は、その場でメモして目立つところに貼っておく。
- 「緊張」や「うわの空」は「メタ認知」で予防する。
- 緊張で頭の中が真っ白になったり、心配事があってうわの空になったりして、やろうとしていたことが頭から飛んでしまう時の対処。
- 自分を別角度から客観的に眺めて見る。(メタ認知)
- 緊張で頭の中が真っ白になったり、心配事があってうわの空になったりして、やろうとしていたことが頭から飛んでしまう時の対処。
- 先の展開を読んで、脳内リハーサルをしておく。
「人の名前が出てこない・・・」系のもの忘れ
『「人の名前が出てこない・・・」系のもの忘れ』では、主に以下のことが述べられています。
- 記憶系脳番地の低下が深く関係している。
- 日々、思考系や感情系の少ないマンネリした生活を送っていると、記憶系の力も低下しやすくなる。
- 右脳で「顔の記憶」は引き出せているのに、左脳で「名前の記憶」を引き出せない。
逆もある。(名前はわかるが、顔がわからない。) - 話している人が誰か思い出せない。
- 歳をとると、「記憶を取り出す力」自体が低下する。
- 「思い出そうとする努力」を怠らなければ、検索エンジンの力を落とさずにキープしておくことも可能。
- 昔の古い記憶もたまに思い出すようにすれば、スムーズに取り出せるようになってくる。
- 歳をとると、「記憶を取り出す力」自体が低下する。
- 仕事相手の名前を間違える。
- 固有名詞を記憶する際に、周辺の情報や特徴などをプラスして刷り込んでおく。
- 固有名詞が出ずに、すぐスマホで検索していまう。
- スマホに頼らず、なるべく自前の脳を使って思い出す姿勢が大切。
- 毎日会っている同僚の名前がすぐ出てこない。
- ニックネーム等で記憶していると、記憶の優先順位で本名が後ろになり、思い出すのに時間がかかる。
- 本名で呼んでいるのに、名前が出ないのは脳の老化が相当進んでいる。
- ニックネーム等で記憶していると、記憶の優先順位で本名が後ろになり、思い出すのに時間がかかる。
- おすすめのトレーニング
- 名前に意味を持たせる。
- 特徴的なイメージやワードをひもづけて記憶しておくと、その「ひも」を引っ張ることで名前と顔をスムーズに引き出せる。
- 普段から関連づけを習慣にする。
- 例えば、この人は以前お世話になったAさんに似てるな、と知り合いと関連付ける。等
- 1日10分間の「暗記タイム」をつくる。
- 「暗記」は、記憶系脳番地を活性化させるのに有効な作業。
- 「思い出し日記」をつけてみる
- 思い出すという行為は、記憶系脳番地ほかの力を維持するために不可欠。
- その日起こった出来事に限らず、最近よく思い出すや昔の思い出を日記に書き記す。
- 名前に意味を持たせる。
「できていたはずなのに・・・」系のもの忘れ
『「できていたはずなのに・・・」系のもの忘れ』では、主に以下のことが述べられています。
以前は問題なくできていたことができなくなる。
(迷いやすくなった。漢字が書けなくなった。暗算ができなくなった。)
- 多くの脳番地の力が複合的に低下して、「こんなはずじゃ-」につながっていく。
→普段使わない脳番地の力が低下する。 - アイドルの個別認識ができにくくなる。
- 視覚系と記憶系の脳番地連携による「資格記憶」の衰えが影響している可能性がある。
- 興味や好奇心が加齢とともに低下してきたものもそうとう影響している。
→いろいろなことに幅広く興味や関心を持つようにする。
- 自分の車をどこに停めたかわからなくなる。
- 空間認知能力は、普段から使っていないと歳とともに衰えやすい。
→目印を覚えておくようにする。
- 空間認知能力は、普段から使っていないと歳とともに衰えやすい。
- 何度も来ているのに道に迷った。
- 場所や時間などの状況を把握することを「見当識」という。
→久しぶりの場所だとちょっとしたことで混乱しやすい。
- 場所や時間などの状況を把握することを「見当識」という。
- 漢字を忘れてしまう。
- 漢字を書く手順には運動記憶が深く関係している。
「手で書くという運動」をしていないと、記憶がどんどん失われていく。 - 手書きで書くという行為は、運動記憶を使いながら、脳を広範囲に働かせる高等作業。
- 漢字を書く手順には運動記憶が深く関係している。
- 暗算が面倒で、計算機をつかってしまう。
- 暗算は、脳のワーキングメモリー機能が使われる。
普段から使っていないと低下する。
- 暗算は、脳のワーキングメモリー機能が使われる。
- おすすめのトレーニング
- 「気になる場所」に勘を頼りに行ってみる。
- 視覚記憶を頼りに目的物を捜しに歩くトレーニング。
捜し歩くうちに空間把握能力や見当識を鍛えることになる。
- 視覚記憶を頼りに目的物を捜しに歩くトレーニング。
- 配置図を書いてから部屋の模様替えをする。
- 空間を把握するのは、右脳サイドの理解系脳番地の役割。
- 理解系脳番地の空間認識能力だけでなく、思考系脳番地や運動系脳番地など、幅広く鍛えられる。
- 自分で鉛筆を削り、その鉛筆で日記を書く。
- 脳が手の動きを指示し、何を書くか思考を重ねる。
- 思考系、運動系、理解系、伝達系など、広範囲に脳を使うことになる。
- ウオーキングしながら頭の中で引き算する。
- 「歩きながら暗算」を行うと、計算処理に脳のワーキングメモリーが使われ、ワーキングメモリーの力を維持・向上させることができ、同時に運動系脳番地も刺激することができる。
- 「気になる場所」に勘を頼りに行ってみる。
「ついうっかり忘れもの・・・」系もの忘れ
『「ついうっかり忘れもの・・・」系もの忘れ』では、主に以下のことが述べられています。
- 注意力や記憶力が落ちてきたサイン。
しょっちゅうあるなら、思考系脳番地や記憶系脳番地などの力が低下して、注意力や集中力、記憶力が落ちてきたと考えるほうがいい。 - 買うものを忘れないためにメモを書いたが、そのメモを忘れてしまった。
- 頻繁に起こるようだと脳の衰えが心配になる。
- おすすめのトレーニング
- メモと筆記用具を常にポケットに入れておく。
- 忘れないようにしないといけないことがあった時に、その場メモができるようにしておく。
- メモは、記憶力、集中力、注意力、発想力、思考力など、さまざまな力を引き出してくれる最高の脳活性化アイテム。
- 写経や瞑想にチャレンジする
- 落ちついて注意が払えるように、「般若心経の写経をしてみる」「1日10分瞑想タイムをつくる」「腹式呼吸を取り入れてみる」とか、自分に合うものを続けていく。
- 出かける前の5分間で鞄の中身を整理する。
- 人間の脳は、時間制限を設けると注意力や集中力を発揮するようになる。
- 出かける前の5分間で鞄の中身を整理するのを習慣にしていると、うっかり系のもの忘れやミスを防ぐトレーニングにうってつけ。
等
- メモと筆記用具を常にポケットに入れておく。
「言葉がでてこない・・・」系もの忘れ
『「言葉がでてこない・・・」系もの忘れ』では、主に以下のことが述べられています。
- 脳の衰えの傾向はコミュニケーションに表れやすい。
- 積極的に人に話しかけたり、つながっていく姿勢が大切。
- 「いま、何言おうとしたんだっけ?」のもの忘れ
- ふと頭に浮かんだことの記憶保持時間は非常に短く、内容が飛びやすい。
- 大事な思いつきを留めておきたいなら、常にメモと筆記具を携帯しておいて、思いついたときにすぐ書き留めておくのがいちばん。
- 常時、年月日や曜日が分からなくなったら、認知症の可能性大。
- 「今日は何日、何曜日」という時間の座標軸をしっかり持って生活する姿勢は大切。
- 人と話さなくなった。
- 「人と話をする」ことは、脳のさまざまな部分を広範囲に使って行われる高次アウトプット。
- 言葉数の減少やコミュニケ―機会の減少は、人の脳の衰えに直結する。
→積極的に言葉を出すようにする。
- おすすめのトレーニング
- お店の人に話しかけてみる
- 地域で「話ができる人」を増やす。
- 「ミニ・コミュニケーション」を普段から意識して行っていれば、それだけでも伝達系脳番地がかなり鍛えられる。
- 「プチ漫才」にチャレンジする。
- 夫婦間で「あれ」「それ」の会話が増えたり、会話自体が少なくなってきたら、掛け合いを行っていると、思考系、聴覚系、伝達系などの脳番地が広く刺激され、格好の脳になる。
- 音読する。
- 伝達系の能力低下を防ぐトレーニングには、「音読」をするのがうってつけ。
- お店の人に話しかけてみる
「仕事でのミスが増えた・・・」系の心配事
『「仕事でのミスが増えた・・・」系の心配事』では、主に以下のことが述べられています。
- つまらないミスが増えたり、頭がうまく働かなかったり、スランプで成績が上がらなかったり、仕事での不調やミスが多い場合は、脳の衰えが絡んでいる可能性がある。
→休息などの対策を取るのも良い。 - 大事な会議を忘れてしまったりする。予定をダブルブッキングする。
→1週間の仕事の予定を週頭などに確認し、おおまかにシミュレーションしておく。 - 会議で意見を求められても、何も思いつかず、沈黙してしまうことが多い。
- 日頃あまり積極的に話しかけたり、意見を言ったりしない人は、左脳の伝達系の脳番地の活動がすごく低下している。
- いつもルーティンの仕事ばかりこなしている人は、こういう咄嗟の対応ができにくい。
- 何も答えられず黙ってしまうのは、脳の反応性、応答性が落ちている可能性もある。
- 複数の仕事に追われると、いつも焦りまくって思考停止してしまう。
- 思考停止に陥りやすいのは、「不測の事態」に見舞われたとき。
→不測の事態に備えて、ある程度余力を残して、自由な時間を確保しておく。
- 思考停止に陥りやすいのは、「不測の事態」に見舞われたとき。
- 30個購入したはずが、300個届いた。
- この手のミスが日常的に続く場合、過労、睡眠時無呼吸症候群、うつ病、認知症などによる脳力低下の可能性が疑われる。
- 人の話が耳に入らず、大事なことを聞き逃すことが多くなった。
- 「聴覚系脳番地」はいつの間にか衰えやすく、進むと認知症になる。
- スマホ画面ばかりを見て、視覚刺激ばかりに偏って、いつの間にか聴覚系の脳番地の血流が下がってしまう。
→「人の話を聞く」「その話を理解する」という基本をおろそかにしてはダメ‼
- おすすめのトレーニング
- 「ひとり後出しじゃんけん」でわざと負ける。
- 「ひとり後出しじゃんけん」は、脳の思考系や運動系を刺激して、とっさの反応や応答性を高めるのに適したエクササイズ。
しかも「わざと負ける」ようにすると、より脳を活性化させることができる。
右手で色んな手を出して、左手が常に負けるようにする。
- 「ひとり後出しじゃんけん」は、脳の思考系や運動系を刺激して、とっさの反応や応答性を高めるのに適したエクササイズ。
- 会議中の発言を早書きメモする。
- 会議での早書きメモは、脳を効率よく鍛える作業。
- 人の話に集中する力、人の話を聞く力、その内容を瞬時に理解して、スピーディーに記録する力などがトータルに鍛えられる。
- 聴覚系脳番地の力は飛躍的に上がる。
- 寝る前にラジオを聴く
- 聴覚系脳番地を鍛える方法として、「寝る前にラジオを聴く」
等
- 聴覚系脳番地を鍛える方法として、「寝る前にラジオを聴く」
- 「ひとり後出しじゃんけん」でわざと負ける。
「ときめきがなくなった・・・」系の心配事
『「ときめきがなくなった・・・」系の心配事』では、主に以下のことが述べられています。
- マンネリ生活による意欲低下が脳の衰えを進めてしまう。
- 感情面の変化は、感情系脳番地、記憶系脳番地、思考系脳番地などの他の脳番地の力の低下が影響している。
感情系脳番地の制御ができなくなると、感情が不安定になる。
→マンネリ生活から脱却する。 - 若い時と比べて、何かに感動することがなくなった。
- マンネリが進んでいるサイン。
- 日々の生活がマンネリ気味の人は、日常のルーティンワークを見直して、新しい感動やときめきの栄養を脳に注入していかなければならない。
- うまく感情を表現できず、無表情になっている気がする。
- 感情表現が希薄になるのは、相当まずい。
→感情系や伝達系の脳番地の力がかなり衰えてしまっている。 - 人と交わってよくしゃべったり感情を表したりするのは、脳の機能を健康に維持するために非常に大切なこと。
- 感情表現が希薄になるのは、相当まずい。
- おすすめのトレーニング
- 朝、鏡の前で笑顔をつくる。
- 表情が乏しくなると、感情系や運動系の脳番地への刺激が少なくなって、自分の考えや気持ちを表現できにくくなる悪循環に陥る場合もある。
- 表情筋がやわらかくほぐされるうえ、感情系脳番地や運動系脳番地が効率よく刺激される。
- 朝、鏡の前で笑顔をつくる。
エピローグ
「エピローグ」では、主に以下のことが述べられています。
- マンネリで刺激の乏しい生活を送っていると、40代、50代くらいから人や物事に対する好奇心や意欲が落ちて、脳の活力がじわじわ低下してしまう。
- 「マンネリで刺激の少ない毎日」を「刺激的でわくわくするような毎日」に変えていけば、脳の老化を食い止めて、脳細胞をイキイキと成長させていくことができる。
- 脳の成長させるために「整えるべき条件」はやはり”刺激”。
最後に
物忘れが気になっていたため、本書を読んでみました。
読み進めると、自分に当てはまる”もの忘れ”が多く記載されてろり、思い当たることが多くありました。
日常的にさまざまの箇所(脳番地)の脳を積極的に使う必要性を痛感しました。
おすすめのトレーニングとして書かれている内容が、なかなか実施しずらい内容のものもかかれていますが、自分にできるものから取り組むとよいかもしれません。
なお、私の普段の生活は、マンネリ生活ではないと自分では感じていますが、刺激は乏しい生活を送っているのかな、と本書を読んで感じましたので、刺激的な毎日を送れるように、何か見つけてみたいと思います。
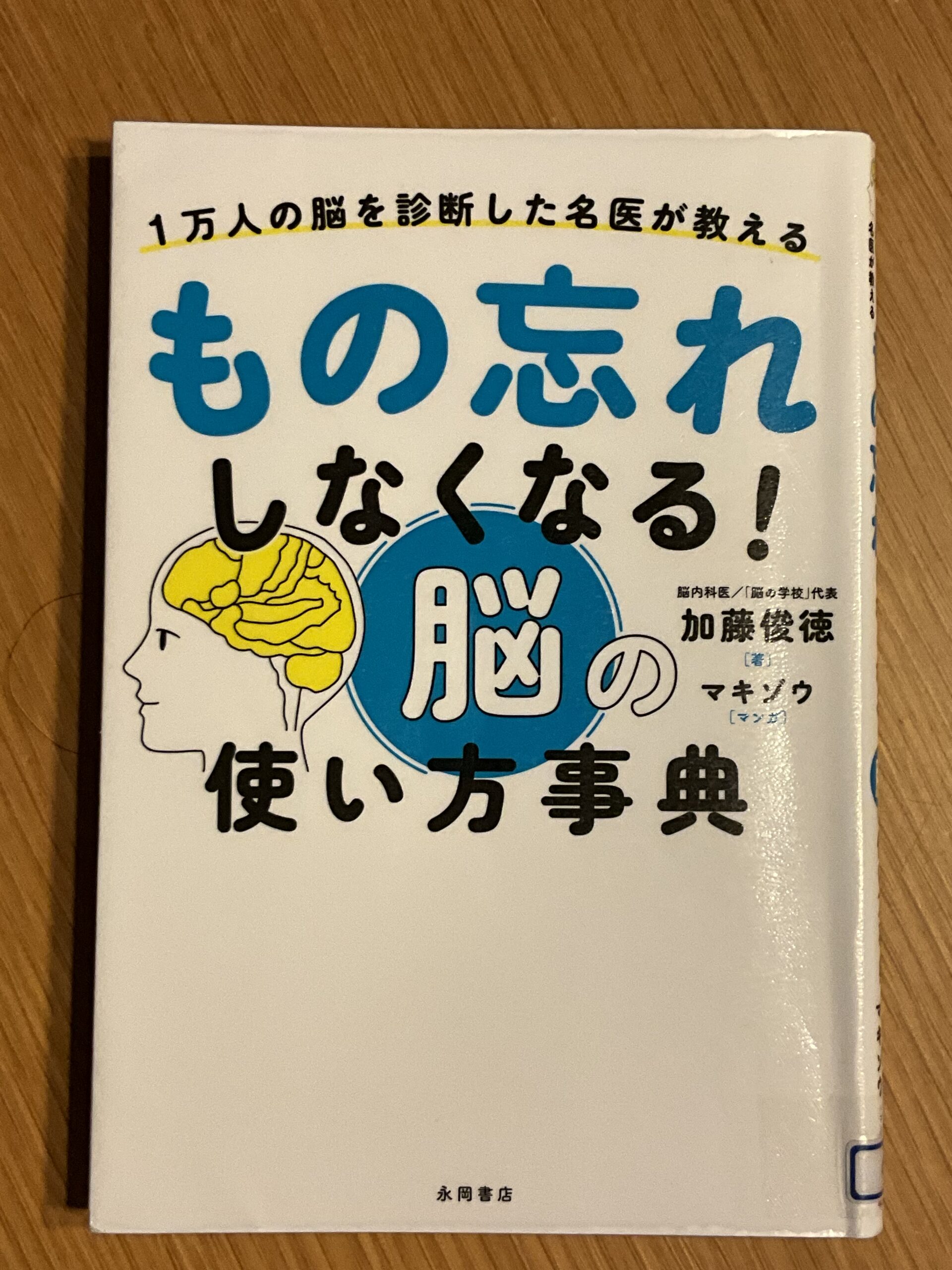
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/474bc9b5.aae640e7.474bc9b6.8b0594b0/?me_id=1213310&item_id=20819404&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9975%2F9784522439975_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


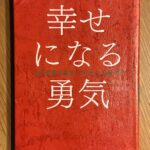
コメント