今回紹介する本は「限りある時間の使い方」(オリバー・パークマン著 かんき出版)です。
タイトルが気になったので、読んでみました。
本書は、以下の14部構成になっています。
- なぜいつも時間に追われるのか
- 効率化ツールが逆効果になる理由
- 「時間がある」という前提を疑う
- 可能性を狭めると自由になれる
- 注意力を自分の手に取り戻す
- 本当の敵は自分の内側にいる
- 時間と戦っても勝ち目はない
- 人生には「今」しか存在しない
- 失われた余暇を取り戻す
- 忙しさへの依存を手放す
- 留まることで見えてくるもの
- 時間をシェアすると豊かになれる
- ちっぽけな自分を受け入れる
- 暗闇のなかで一歩踏み出す
1.なぜいつも時間に追われるのか
「なぜいつも時間に追われるのか」では、主に以下のことが述べられています。
- 時間が限られていることではない。本当の問題は、「限られた時間をどう使うか」
- 時間を支配しようとする者は、結局は時間に支配される。
- 時間をコントロールしようと思うと、時間のなさに一層ストレスを感じる。
- 制約に逆らうかわりに、制約を味方につける。限界があるので直視して受け入れる。
- 「何もかもできない」と認める。すべてをやっている時間はない。
- 意識して選択する。何に集中し、何をやらないのか。
2.効率化ツールが逆効果になる理由
「効率化ツールが逆効果になる理由」では、主に以下のことが述べられています。
- 省力化のために機械化しても、社会の期待値が上がり、省力化のメリットを相殺してしまう。
- メールの処理能力を高めても、ゴールはない。
受信箱を空っぽにしてもすぐメールがやってくる。
返信すればするとそれに対する返信が来てまた返信するというのが無限に続く。 - メールを処理することで、メールがさらに増えるという悪循環を生む。
- これがいわゆる「効率化の罠」でどんなに高性能な生産性ツールを取り入れても、どんなにライフハックを駆使しても時間は決して余らない。
→選択肢:「もっと効率的にやれば忙しさから逃れられる」という希望をあえて捨てる。 - どんなに効率的にやっても忙しさは終わらない。
- これがいわゆる「効率化の罠」でどんなに高性能な生産性ツールを取り入れても、どんなにライフハックを駆使しても時間は決して余らない。
- 「全部できる」という幻想を手放して、ひと握りの重要なことだけに集中する。
- 効率化の罠の本当の怖いところは、量だけでなく、質にも影響する。
- 全て効率的にこなそうとするのではなく、すべてをこなそうという誘惑に打ち勝つことが必要。
- 効率的の追求には、目に見えにくい問題が潜んでいる。
- 「便利さ」という危険な誘惑。
- 便利なツールで自由になった時間を作ったとたん、その時間は別のやることリストで埋まってしまう。
- 便利なツールで自由になった時間を作ったとたん、その時間は別のやることリストで埋まってしまう。
3.「時間がある」という前提を疑う
『「時間がある」という前提を疑う』では、主に以下のことが述べられています。
- 時間は有限であり、死がいつどの瞬間にやってくるかわからないので、時間の使い方は徹底的に制約されている。
- 時間は有限で、無限に続かないから価値がある。
- 大切な人たちと過ごす時間が特別なのは、それが永遠に続かないから。
- 夏休みが無限にくるなら、特別な価値はない。
- 時間の使い方が重要な問題。
- 「限られた時間の中で何をするか」というのが重要。
- 一つのことをすると、何かをあきらめなければならないか、何かひとつしか選べないことは敗北ではなく、決められた時間の中で「あれ」ではなく、「これ」をするという前向きなコミットメント。
自分にとって大事なことを主体的に選びとる行為。
4.可能性を狭めると自由になれる
「可能性を狭めると自由になれる」では、主に以下のことが述べられています。
- やりたいことが全部できるわけではないので、上手に先延ばしするスキルを学ばなくてはならない。
- 大事なのは先延ばしをなくすことではなく、何を先延ばしするかを賢く選択する事。
- 本当にやりたいことが出来るように、その他をあえて放置する。
- タスクを上手に減らす3つの原則
- まず自分の取り分を取っておく
- まず必要な時間を先に確保しておく。
- 「進行中」の仕事を制限する
- 同時に進行する仕事の数を削れるところまで削る。
- 「進行中」の仕事を3つまでに制限する。
- 最も重要な3つのことを選択したら、そのうち一つが完了するまで他の仕事は一切やらない。
- 優先度「中」を捨てる
- 優先度が中くらいのタスクは邪魔になるだけで、いつかやろうと思わないで、ばっさり切り捨てる。
- まず自分の取り分を取っておく
- 人は後戻りできない状況に置かれたほうが、選択肢があるときよりも幸せになるというデータがある。
- 手持ちのカードを多く残しておくよりも「これしかない」という状況の方が満足感が高まる。
5.注意力を自分の手に取り戻す
「注意力を自分の手に取り戻す」では、主に以下のことが述べられています。
- 限られた時間がどんなに有効に使おうと思っても、次から次へと気が散る情報が入ってきてはうまくいかない。
- 注意力は「限りある資源」。
意識的に注意を向けることができるのは、脳内に氾濫している情報のうちわずか0.0004%程度。 - 時間と同じく注意力にも限界がある。
自分の注意を完全にコントロールすることは不可能だが、ある程度まで意識的に注意をコントロールできる。 - 「トップダウン型」の注意、つまり自発的な注意力でトップダウン型の注意をうまく使えるかどうかで人生の質は左右される。
6.本当の敵は自分の内側にいる
「本当の敵は自分の内側にいる」では、主に以下のことが述べられています。
- 目の前の苦痛から逃れるために気を紛らせてくれる何かを探してしまう。
- 仕事中にSNSをつい開いてしまうのもそのため。
- 嫌な現実から逃れたいという自身の欲求
- 現実から逃れるのをやめれば苦痛が和らぐ。
- 「現実は思い通りにはならない」ということを本当に理解したとき、現実のさまざまな制約はいつの間にか苦にならなくなっている。
7.時間と戦っても勝ち目はない
「時間と戦っても勝ち目はない」では、主に以下のことが述べられています。
- どんな仕事であれ、つねに時間は予想以上にかかる。
計画通りにいかないだけでなく、余裕を持って計画すればするほどいっそう遅れの幅が大きくなる。 - 先のことを心配するとき、その奥は「未来を確実なものにしたい」という願いがあるが、どんな未来を心配しても時間との戦いに勝てるわけがない。
「未来は決して確実ではない」という事実を受け入れると不安から解放される。 - 過去は変えられず、未来はどうなるか分からない。
8.人生には「今」しか存在しない
『人生には「今」しか存在しない』では、主に以下のことが述べられています。
- 「時間を使う」と考えるとき、時間は単なる道具になる。
- 何か別なことをするための手段となる。
- 時間の「道具化」と呼べる問題。
- 「いつか何かをしたら」というマインドの人々は、まだ大事なことが達成されていないせいで、現在の自分が満たされないと考え、問題が解決したら人生は思い通りに動き出し時間に追われることなくゆっくりと生きられると思っている。
→いつまでたっても満たされることはない、現在を永遠に先延ばしする考え方
→未来のために現在を犠牲にしている。 - 人生は有限であり、必然的に二度とない体験に満ちている。だからどんな経験もそれが最後の機会であるかのように大切にするべき。
- 時は訪れては去っていき、残りの時間はどんどん少なくなる。この貴重な瞬間をいつか先の時点のために踏み台としてぞんざいに扱うなんてあまりにも愚かな行為。
- 今を生きるための最善のアプローチは、今に集中しようと努力することではない。「自分はここにいる」という事実に気づくこと。
「今を生きよう」というとき、自分を「今」から切り離したうえで、今をうまく生きられたかどうか判断しようとしている。
これもまた今の瞬間を何らかの目的に従わせようとする道具化のアプローチ。 - 今を生きるとは、今ここから逃れられないという事実を、ただ静かに受け入れることかもしれない。
9.失われた余暇を取り戻す
「失われた余暇を取り戻す」では、主に以下のことが述べられています。
- 時間をできるだけ有効に活用しようとすると、余暇まで生産的に使わなければならなくなる。
何にもせずにのんびりとするのが余暇の目的だったはずなのに、それだけでは足りない気がしてくる。 - 余暇を有意義に過ごそうとすると、余暇が義務みたいになってくる。
10.忙しさへの依存を手放す
「忙しさへの依存を手放す」では、主に以下のことが述べられています。
- 自分の望むスピードで速く動かそうとすると、逆効果を引き起こすことが多い。慌てて作業をするとミスが増え、修正に余分な時間を取られる。
- 物事は必要なだけの時間がかかるもので、どんなに急いでも不安が減るわけではない。
- 世界のスピードを思い通りに動かすことは不可能。急げば急ぐほどもっと急がなければならないという不安が増す。
- 「物事が進むスピードは自分ではコントロールできない」という真実に直面し、不安を押さえようとする努力をやめたとき、不安は何か別のものに変化する。
困難で時間のかかる仕事に取り掛かることは、もはやストレスの引き金ではなく、すがすがしい選択になる。
例えば、難解な長編小説を読むことは、苦行ではなく楽しい時間になる。耐えること、じっと持ちこたえて次の一歩を踏み出すこと、そうしたことに価値を見いだす。
11.留まることで見えてくるもの
「留まることで見えてくるもの」では、主に以下のことが述べられています。
- 忍耐が強みになる場面が増えた。
- 誰もが急いでいる社会では、急がずに時間をかけることが出来る人が得をする。
大事な仕事を成し遂げることが出来るし、結果を未来に先送りすることなく、行動そのものに満足を感じることが出来る。 - 忍耐とは単に心の平穏をもたらすものではなく、実生活に役立つスキル。
- 忍耐を身につける3つのルール
- 「問題がある」状態を楽しむ
- 何ひとつ問題がない状態は不可能。
- 問題のない人生をにはやるべきことがなく、意味がない
- 問題とは、自分が取り組むべき何か。
取り組むべきことが何もなくなったら、人生は全く味気のないものになる。 - 「すべての問題を解決済みにする」という、達成不可能な目標をあきらめる。
そうすれば人生とは一つ一つの問題に取り組み、それぞれに必要な時間をかけるプロセスであるという事実に気づく。
- 小さな行動を着実に繰り返す
- ほんの少しの量を毎日続ける。
たとえエネルギーがあふれていても、決めた時間以上やらない。その方が長期的に見ればずっと高い生産性を維持できる。
- ほんの少しの量を毎日続ける。
- オリジナルは模倣から生まれる
- 模倣から個性的な仕事が始まる。
- 人真似だと言われてもくじけずに粘り強く技術を磨き、経験を積むことのできる人だけでたどり着く。
初期段階であきらめては、決してオリジナルの作品は作れない。
3時間絵を見るのと同じで、その場に立ち止まり、現実を速めようとするのをやめる。
かけがえのない成果を手に入れるには、たっぷりと時間をかけることが必要。
- 「問題がある」状態を楽しむ
12.時間をシェアすると豊かになれる
「時間をシェアすると豊かになれる」では、主に以下のことが述べられています。
- 時間があってもひとりぼっちでは、あまり意味がない。
- 時間を意味あることに使うためには、他人と協力することが不可欠。
たとえ時間がありあまっていても共に過ごす人がいなければ全く意味がない。
時間は人と共有してこそ価値が生まれる。 - 一人で休むより、みんなで休んだ方がリラックスできる。
- まわりと共有する時間を作ることも大切。
- 時間は自分たちのものになりすぎないくらいが、実はちょっといい。
13.ちっぽけな自分を受け入れる
「ちっぽけな自分を受け入れる」では、主に以下のことが述べられています。
- 並外れたことをやろうという思いはきっぱりと捨て、自分に与えられた時間をそのまま味わった方がよい。
人生をありのままに体験する。
14.暗闇のなかで一歩踏み出す
「暗闇のなかで一歩踏み出す」では、主に以下のことが述べられています。
- 時間を支配しようとする態度が僕たちが時間に苦しめられる原因
- 限られた人生の中では、すべての重要な計画を成しとげるなんてどんなに頑張っても絶対に不可能。
- 限られた時間を思い通りにコントロールできず、正確に予測することもできない。
- 快適な衰退よりも、不快な成長を目指した方がいい。
- 無限にやってくる要求に全て対応できるほど効率的なやり方は存在しない。
- 仕事や家庭などに「充分な」時間を費やすことは、まず不可能。
- 無理な基準は全部地面に投げ捨て、そのがれきの中から重要なタスクだけをしっかり拾い上げ、今すぐ始める。
- 「こうあるべき」というプレッシャーから自由になれば、今ここにいる自分と向き合うことが出来る。
- たとえ経験や自信がなくてもやるのを諦める理由はない。
尻込みしていても仕方ない。今すぐやりたいことをやり始めよう。 - 「次にすべきこと」を実行するのが、自分にできる唯一のこと。
たとえ正解が分からなくても、次にすべきことをやるしかない。 - 「それしかできない」ということは、「それしかしなくていい」ということ。
- 大事なのは自分だけの次の一歩を踏み出すこと。
有限性を受け入れるための10のツール
- 「開放」と「固定」のリストを作る
- 何かを捨てることは避けられないという前提に立ち、うまく選択することに集中する。
- やることリストを「解放」と「固定」の2種類に分ける。
- 開放リストには、抱えているタスクを自由に突っ込む。
但し、それに取り組む必要はない。
リストが出来たら開放リストから固定リストにダスクの一部を送り込む。
なお、固定リストの量は、「最大10個」のように上限を決める。
→固定リストのタスク数は、決してそれ以上増やさない
→一つのタスクが終わるまで別のタスクを追加しない - 固定リストのタスクにだけ集中する。
日々の仕事に時間制限を設ける。(8:00~17:30まで等)
時間の制約を意識して賢く行動できる。
- 開放リストには、抱えているタスクを自由に突っ込む。
- 先延ばし状態に耐える
- 一度に取組むのは一つのプロジェクトに限定する。
そのプロジェクトをやり遂げるまで、他のプロジェクトには手を付けない。 - 本当に重要なプロジェクトだけに取り組み、着実な成果を出す。
- 一度に取組むのは一つのプロジェクトに限定する。
- 失敗すべきことを決める
- 人の時間とエネルギーには限りがあるので、失敗は避けられないと思った方がよい。
- 大事なのは戦略的に失敗する事。
- 失敗してもいいことを事前に決めておく。
例:失敗リストに「芝生の手入れ」を入れると、芝生が伸び放題でも自分を責めなくてよい。
- 失敗してもいいことを事前に決めておく。
- できなかったことではなく、できたことを意識する。
- 全てが終わることは決してない。
- 昨日できなかったことを今日やり、夕方までに何とか負債をゼロにしようと頑張るけれど、また一部が終わらず負債が積みあがる。
- こうした負のサイクルへの対抗策としては、「やっとことリスト」が有効。
- 毎朝、リストが空っぽの状態から始めて、1日のうちに達成したことを少しずつ記入していく。
- 小さな勝利を経験すると、モチベーションが上がり、やがて大きな成果がついてくる。
- 全てが終わることは決してない。
- 配慮の対象を絞り込む
- SNSの戦略に惑わされず、自分が配慮すべき問題を意識的に選びとる。
(たとえば、今後2年間は地域の食糧支援に力を注ぎ、他は気にしない)
- SNSの戦略に惑わされず、自分が配慮すべき問題を意識的に選びとる。
- 退屈で機能の少ないデバイスを使う
- スマホやタブレットは気晴らしの誘惑にかられてしまうので、デバイスをできるだけ退屈なものにする。
→SNSアプリを削除する。画面をグレースケールにする等
- スマホやタブレットは気晴らしの誘惑にかられてしまうので、デバイスをできるだけ退屈なものにする。
- ありふれたものに新しさを見いだす
- 年齢を重ねると時間の経過が早くなる。
子供のころは日々の全てが新しい体験で1日が長く感じられたが、歳をとると生活は同じことの繰り返しになり、人間関係や仕事にも変化がなくなり、新鮮さが失われる。 - 日常の内側に新しさを見つける。
散歩してみたり、いつもと違うルートで通勤したり、写真を撮ったりしてみる
- 年齢を重ねると時間の経過が早くなる。
- 人間関係に好奇心を取り入れる
- 「自分の時間を確実にコントロールしたい」という欲求は、親しい人との関係性に多くの問題を引き起こす。
- 他人に対して好奇心を持つ。
- 好奇心を持っていれば、相手の行動を自分基準で判断せず、ニュートラルに受け入れることが出来る。
- 親切の反射神経を身につける
- 他人に親切にしたいと思ったときは、即座に実行する。
- 親切な行動は、自分自身を確実に幸せな気分にする。
- 何もしない練習をする
- 自分の4,000週間を有意義に過ごすためには、「何もしない」能力が欠かせない。
- 急ぐ必要のないことを急いでやろうとしてストレスを感じたり、将来に役立つことをやらなければと思い込んで、楽しみや満足をいつまでも先送りしてしまったりする。
- 何もしないことが出来る人は、自分の時間を自分のために使える人
- 心を落ち着かせ、自分だけの限られた時間をじっくり味わおう。
最後に
この本は、時間をできるだけ有効に使うことが書かれているが、単なるタイムマネジメントの本ではありません。
文章はやや難しい表現で書いてあるところがあり、すんなり理解とはいかず、じっくり読んで作者の意図を読み取る必要があると思います。
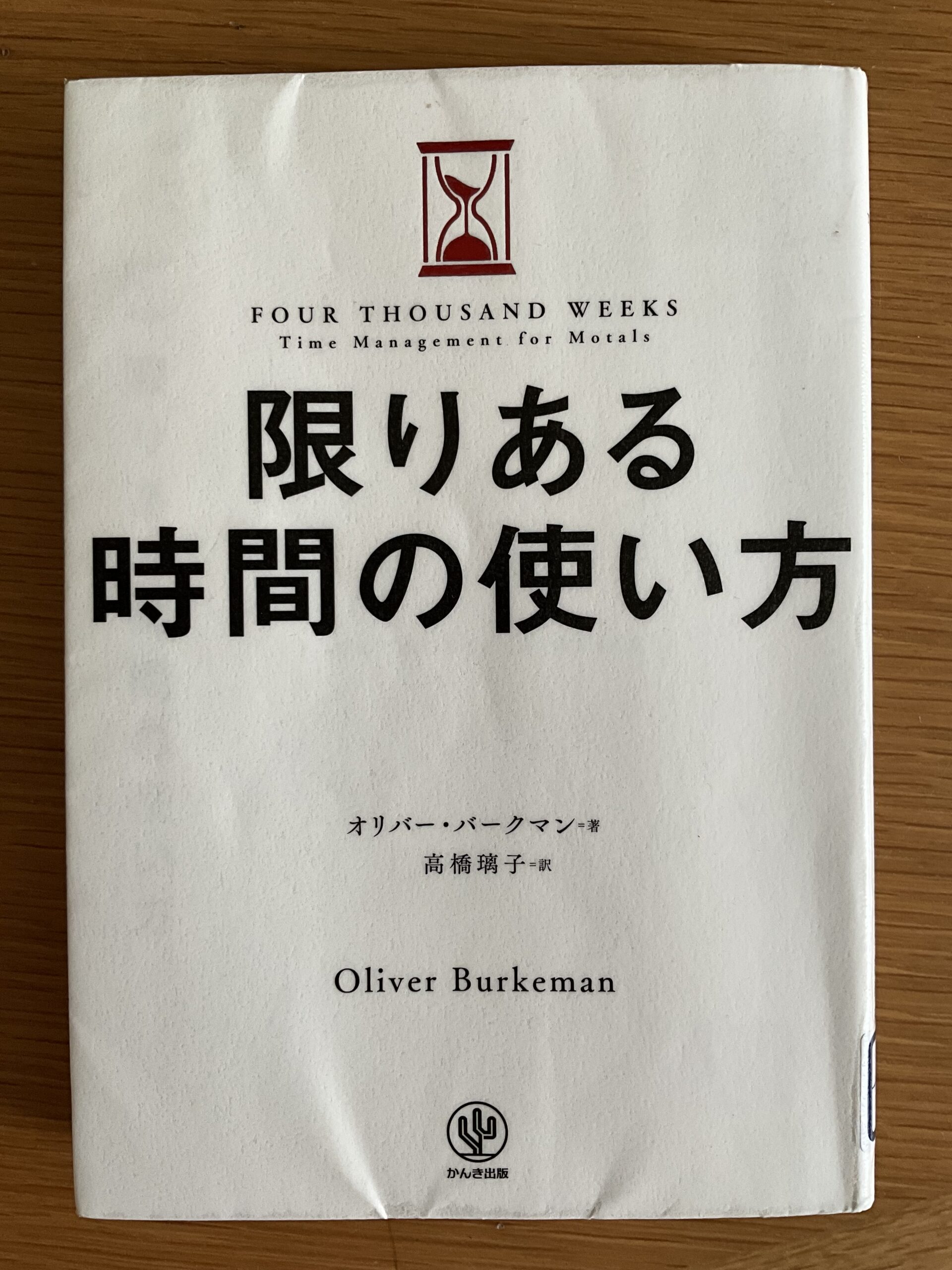
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/474bc9b5.aae640e7.474bc9b6.8b0594b0/?me_id=1213310&item_id=20693913&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6157%2F9784761276157_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

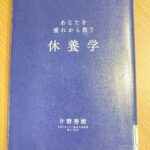

コメント