EIICHIです。
以前、化学物質の新たな法規制についてお話ししましたが、今回は「化学物質管理強調月間」についてお話ししたいと思います。
「化学物質管理強調月間」の創設について
2024年4月から化学物質に関する新たな法規制が施行されましたが、規制対象となる化学物質(リスクアセスメント対象物質)は今後順次拡大される予定です。対策をしなければならない事業場の範囲が大幅に拡大され、業種、規模に関わらず化学物質を製造又は取り扱う全ての事業場において、化学物質を管理する必要があるため、化学物質の重要性に関する意識の高揚と化学物質の管理活動の定着を図ることを目的として、「化学物質管理強調月間」が創設されました。
第1回の「化学物質管理強調月間」は2025年2月に実施され、第2回目が2026年2月に実施されます。
なお、強調月間中、各事業者には以下の実施が求められています。
- 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
- スローガン等の掲示
- 化学物質管理に関する優良職場、功績者等の表彰
- 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
- 化学物質管理に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労化学物質管理への意識高揚のための行事等の実施
- 日常の化学物質管理の総点検
化学物質創設に関する詳細は、こちら(厚生労働省:化学物質管理強調月間の創設について)を参照ください。
第2回目「化学物質管理強調月間」について
第2回目の「化学物質管理強調月間」は2026年2月1日から2月28日の間実施されます。
スローガンは、「慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い⽅」です。
なお、各事業者に求められている重点実施項目は以下の通りです。
- 下記の重点事項について、日常の化学物質管理の総点検を行う
- リスクアセスメント対象物を製造又は取り扱う際の化学物質管理者の選任、職務権限の付与、化学物質管理者の氏名の掲示等労働者への周知、化学物質管理者と総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等との連携
- 製造し、又は取り扱っている化学物質の把握及び、化学物質の安全データシート(以下「SDS」という。)等による危険有害性等の確認
- ラベル表示・SDS交付、リスクアセスメントの実施、リスクアセスメントの結果に基づくばく露低減措置の実施等
- 製造者・流通業者が化学物質を含む製剤等を出荷する際のラベル表示・SDS交付等の徹底及びユーザーが購入した際のラベル表示・SDS交付等の状況の確認
- SDS等により把握した危険有害性に基づくリスクアセスメントの実施とその結果に基づくばく露濃度の低減や適切な保護具の使用等のリスク低減対策の実施
- リスクアセスメントの実施にあたって、業種別・作業別の化学物質管理マニュアル(建設業、ビルメンテナンス業、食料品製造業など)の活用
- 化学物質の自律的な管理の実施状況について衛生委員会での調査審議
- ばく露低減措置の内容や労働者のばく露の状況について、労働者の意見を聞く機会を設けるともに、記録の作成・保存
- ラベル・SDSの内容やリスクアセスメントの結果に関する労働者に対する教育の実施
- 皮膚接触や眼への飛散による薬傷等や皮膚からの吸収等を防ぐための適切な保護具の使用や汚染時の洗浄を含む化学物質の取扱上の注意事項の確認
- 労働者に保護具を使用させる場合における、保護具着用管理責任者の選任、職務権限の付与、保護具着用管理責任者の氏名の掲示等労働者への周知
- 危険有害性等が判明していない化学物質を安易に用いないこと、また、危険有害性等が不明であることは当該化学物質が安全又は無害であることを意味するものではないことを踏まえた取扱物質の選定、ばく露低減措置及び労働者に対する教育の推進
- 濃度基準値設定物質のリスクアセスメントにおいて、ばく露濃度が高いと見積もられた場合に個人ばく露測定によるばく露濃度の確認の実施
- 特殊健康診断等、必要な場合のリスクアセスメント対象物健康診断による健康管理の徹底
- 塗料の剥離作業における健康障害防止対策の徹底
- 金属アーク溶接等作業における健康障害防止対策の徹底
- 特定化学物質障害予防規則等の特別規則、石綿障害予防規則の遵守の徹底
- 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
- スローガン等の掲示
- 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
- 化学物質管理に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他化学物質管理への意識高揚のための行事等の実施
第2回「化学物質管理強調月間」の詳細は、こちら(厚生労働省:第2回化学物質管理強調月間実施要領)を参照ください。
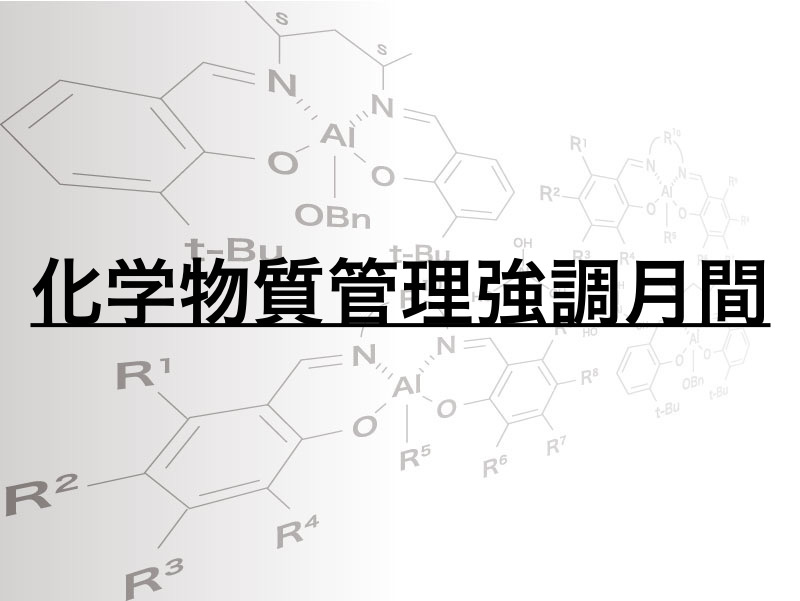



コメント