今回紹介する本は、「幸せになる勇気(岸見一郎、古賀史健 著 ダイヤモンド社)」です。
アドラー心理学について書かれています。
本書は、以下の5部構成になっています。
- 悪い人、かわいそうなわたし
- なぜ「賞罰」を否定するのか
- 競争原理から、協力原理へ
- 与えよ、さらば与えられん
- 愛する人生を学べ
1.悪い人、かわいそうなわたし
「」では、主に以下のことが述べられています。
- アドラーにとっての教育は、中心の課題のひとつであるばかりか、最大の希望。
- アドラー心理学では、カウンセリングのことを「再教育」の場と考える。
- アドラー心理学では、人はみな無力の状態から脱し、より向上していきたいという欲求、つまり「優越性の追求」を抱えて生きる存在。
- 教育とは、「介入」ではなく、自立に向けた「援助」。
- 尊敬のないところに良好な人間関係は生まれない。根源にあるのは、「人間への尊厳」。
- 尊敬とは、人間の姿をありのままに見て、その人が唯一無二の存在であることを知る能力のこと
- 「ありのままその人」を認める。
- 尊敬とは、「勇気づけ」の原点。
- 「他者の関心事」に関心を寄せる。これはあらゆる対人関係で求められる、尊敬の具体的な第一歩。
- われわれに必要なのは、「他者の目で見て、他者の耳で聞き、他者の心で感じること。」
他者の目に映るものを想像し、耳に聞こえる音を想像する。 - まずは、「もし、わたしがこの人と同じ種類の心と人生を持っていたら?」と考える
→「共感」- 共感とは、他者に寄り添う時の技術であり、態度。技術である限り、身につけることができる。
- 共感の第一歩は、「他者の関心事」に関心を寄せること。
- 自分の言動、そして他者の言動を見定めるときは、そこに隠された「目的」を考える。
- 人間は、過去の「原因」に突き動かされる存在ではなく、現在の「目的」に沿って生きている。
- われわれは、過去の出来事によって決定される存在ではなく、その出来事に対して「どのような意味を与えるか」によって自らの生を決定している。
- 自分の人生を決定するのは、「いま、ここ」に生きるあなた。
- アドラーの思想は、「人間はいつでも自己を決定できる存在である。」という、人間の尊厳と人間が持つ可能性への強い信頼に基づいている。
- 「いま」を肯定するために、不幸だった「過去」をも肯定する。
あなたの「いま」が、「過去」を求めている。 - トラウマは、その不幸に彩られた過去を、自らが必要としている。
悲劇という安酒に酔い、不遇なる「いま」の辛さを忘れようとしている。 - アドラー心理学では、「こらからどうするか」を語り合う。
- 建設的で科学的な人間への尊厳に基づく、人間知の心理がアドラー心理学。
※人間知:「わたし」を知り、「あなた」を知ること。
人間の本性を知り、人間としての在り方を理解すること。
2.なぜ「賞罰」を否定するのか
『なぜ「賞罰」を否定するのか』では、主に以下のことが述べられています。
- アドラーは、賞罰を禁じる。叱ってはいけないし、ほめてもいけない。
- 問題行動の「目的」。いかなる目的を持って、問題行動に出ているのか。
- 問題行動の第1段階は、「賞賛の要求」。
→「私をほめてくれ」ということ。- 彼らの目的は、あくまでも「もめてもらうこと」であり、さらに言えば、「共同体のなかで特権的な地位を得ること」。
- 彼らはただ、「ほめられること」をしているだけ。
- ほめてくれる人がいなければ、こんな努力意味がない。途端に意欲を失う。
- 彼らは「ほめてくれる人がいなければ、適切な行動をしない」のだし、罰を与える人がいなければ、不適切な行動もとる」というライフスタイル(世界観)を身につけていく。
- なにか「いいこと」をしたときに注目するのではなく、もっと日頃のささいな言動に目を向け、その人の「関心事」に注目し、共感をよせていく。
- 問題行動の第2段階は、「注目の喚起」
- 「いいこと」をしたのに、ほめられない。特権的な地位を得るまでには至らない。若しくはそもそも「ほれられること」をやり遂げるだけの勇気や根気が足りない。
そういう時は人は「ほめられなくてもいいから、とにかく目立ってやろう」と考える。
- 「いいこと」をしたのに、ほめられない。特権的な地位を得るまでには至らない。若しくはそもそも「ほれられること」をやり遂げるだけの勇気や根気が足りない。
- 問題行動の第3段階。目的が「権力争い」に突入する。
- 誰にも従わず、挑発を繰り返し、戦いを挑む。戦いに勝利することで、自らの「力」を誇示しようとする。特権的な地位を得ようとする。
ひと言で言うなら「反抗」。 - 消極的な場合は、「不従順」によって、権力争いに挑んでくる。
不従順によって、「力」を証明したい。
- 誰にも従わず、挑発を繰り返し、戦いを挑む。戦いに勝利することで、自らの「力」を誇示しようとする。特権的な地位を得ようとする。
- 問題行動の第4段階。ここで人は「復讐」の段階に突入する。
- 権力争いに勝利を収められなかったり、相手にされず敗北した場合は、「復讐」を画策する。
- 「わたし」を認めてくれなかった人、愛してくれなかった人に愛の復讐をする。
- 増悪という感情のなかで、わたしに注目してくれ。そう考えるようになる。
- 自傷行為も、引きこもりも、アドラー心理学では、「復讐」の一環。
- 問題行動の第5段階は、「無能の証明」。
- 「これ以上は期待しないでくれ」という思いが、「無能の証明」。
- 問題行動の5段階の全ては「所属感」。つまり「共同体のなかに特別な地位を確保すること」という目的に根ざしている。
- 最後に選択するコミュニケーションの手段は、「暴力」。
- 問題行動に対してやるべきことは、裁判官の立場ではなく、再教育。
- アドラーは、「怒りとは、人と人を引き離す感情である」と語っている。
- 幸福の本質は、「貢献感」。
- 決断を尊重し、その決断を援助する。そしていつでも援助する用意があることを伝え、近すぎない援助ができる距離で見守る。
3.競争原理から、協力原理へ
「競争原理から、協力原理へ」では、主に以下のことが述べられています。
- ほめられることを目的とする人が集まると、「競争」が生まれる。
そして共同体は褒賞を目指した競争原理に支配される。 - 民主主義は競争原理ではない。「協力原理」に基づいて運営される共同体。
- 問題行動を起こす「個人」ではなく、問題行動が起きる「共同体」に目を向ける。そして共同体そのものを治療していく。
- 「横の関係」は、協力原理。
- アドラー心理学は、横の関係に基づく「民主主義の心理学」。
- 「われわれ人間は、子供時代、例外なく劣等感を抱えて生きている」、これがアドラー心理学の大前提。(大人と比べて、自分にはできないことがあるという劣等感)
- 人間は単独では生きていけないほど弱いので、共同体をつくり、協力関係の中に生きている。
- 共同体感覚は、常に身体の弱さを反映したものであり、それとは切り離すことはできない。
- アドラー心理学では、人間の抱えるもっとも根源的な欲求は、「所属感」だと考える。
- 共同体の中で特別な存在として、他者からの承認を求めるのではなく、自らの意思で、自らを承認する。
- 「わたし」の価値を自ら決定すること。これを「自立」と呼ぶ。
- 「人とちがうこと」に価値を置くのではなく、「わたしであること」に価値を置く。これが本当の個性。
- 他者と自分を比べ、その「違い」ばかり際立たせようとするのは、他者を欺き、自分に嘘をつく生き方。
- アドラー心理学では、人間のあらゆる言動を対人関係のなかで考える。
あらゆる言動とは、それが向けられる「相手」がいると考えられる。 - 他者を救うことによって、自らが救われようとする。自らを一種の救世主に仕立てることによって、自らの価値を実感しようとする。
- 優越コンプレックスの一形態であり、一般に「メサイヤ・コンプレックス」と呼ばれている。
4.与えよ、さらば与えられん
「与えよ、さらば与えられん」では、主に以下のことが述べられています。
- 「すべての悩みは、対人関係の悩みである」という言葉の背後には、「すべての喜びもまた、対人関係の喜びである」という幸福の定義が隠されている。
だからこそ、「人生のタスク」(仕事、交友、愛のタスク)に立ち向かわなければならない。 - 交友について、「われわれは交友において、他者の目で見て、他者の耳で聞き、他者の心で感じることを学ぶ」。→共同体感覚の定義。
- 「交友」に踏み出せない人は、共同体に居場所を見出せない。
- 仕事の関係は「信用」の関係であり、交友の関係は「信頼」の関係。
- 仕事は、「生存」に直結した課題。
- われわれは、集団生活を選んで外敵から身を守ってきた。ここで人間は、「分業」という画期的な働き方を手に入れた。
「分業」とは、人類が身体的劣等性を補償するために獲得した、類まれなる生存戦略。 - 「仕事のタスク」は単なる労働タスクではなく、他者とのつながりを前提とした「分業のタスク」。
- 他者とのつながりを前提としているので、「仕事」は対人関係の課題。
- 他者と「分業」するためには、その人のことを信じなければならない。
→「信用」の関係。選択の余地はない。 - まず仕事の関係に踏み出す。他社や社会と利害関係で結ばれる。そうすれば利己心を追求した先に「他者貢献」がある。
- すべての仕事は、「共同体の誰かがやらなければならないこと」であり、われわれは、それを分担しているだけ。
人間の価値は、「どんな仕事に従事するか」によって決まるのではない。その仕事に「どのような態度で取り組むか」によって決まる。 - 他者のことを「信頼」できるか否かは、他者のことを尊敬できるか否かにかかわっている。
尊敬できない相手のことを「信頼」することはできない。 - 大切なのは、何が与えられているかではなく、与えられたものをどう使うかである。
どんな相手であっても、「尊敬」を寄せ、「信じる」ことはできる。 - われわれは心を豊かに持ち、その蓄えを他者に与えていかなければならない。
他社からの尊敬を待つのではなく、自らが尊敬を寄せ、信頼を寄せなければならない。 - 与えるからこそ、与えられる。「与えてもらうこと」を待ってはならない。
5.愛する人生を学べ
「愛する人生を学べ」では、主に以下のことが述べられています。
- アドラーは愛について、「愛とは一部の心理学者が考えているような、純粋かつ自然的な機能ではない」と語っている。
- 意思の力によって何もないところから築き上げるものだからこそ、愛のタスクは困難。
- アドラーが一貫して説き続けたのは、能動的な愛の技術、すなわち「他者を愛する技術」。
- アドラーは二人が結ばれた後の「関係」に注目している。
- 幸福とは、貢献感。
- われわれはみな、「わたしは誰かの役に立っている」と思えた時にだけ、自らの価値を実感できる。
- 「わたしは誰かの役に立っている」という主観的な感覚があれば、すなわち貢献感があればそれでいい。
それ以上の根拠を求める必要はない。
貢献感の中に、幸せを見出す。貢献感の中に、喜びを見出す。 - 「わたしの幸せ」を突き詰めていくと、結果として、誰かの幸せにつながっていく。
分業の関係が成立する。ギブアンドテイクが働く。 - 交友関係を成立させるのは、「あなたの幸せ」。
相手に対して、無条件の信頼を寄せる。ギブアンドテイクの発想はない。
ひたすら信じ、ひたすら与える利他的な態度によって、交友関係は生まれる。 - 「わたしの幸せ」を追求することによって分業の関係を築き、「あなたの幸せ」を追求することによって交友関係を築いていく。
- 不可分なる「わたしたちの幸せ」を築き上げること。それが愛。
「わたし」や「あなた」よりも上位のものとして、「わたしたち」を掲げる。 - 自立とは、「自己中心性からの脱却」。
甘やかされた子供時代のライフスタイルから脱却しなければならない。
自己中心性から脱却できたとき、われわれは自立を果たす。 - 愛は「わたし」だった人生の主語を、「わたしたち」に変える。
- われわれは、他者を愛することによって、ようやく大人になれる。
- 愛は自立。大人になること。だからこそ、愛は困難。
- アドラーは「運命の人」をいっさい認めない。
→すべての候補者を排除するため。 - 運命とは、自らの手でつくり上げる。
- われわれは、他者を愛することによってのみ、自己中心性から解放される。他社を愛することによってのみ自立を成し得る。そして他者を愛することによってのみ、共同体感覚にたどり着く。
- 「幸せになる勇気」があれば、誰かを愛せ、本当の自立を果たせる。
- 人生は何でもない日々という試練は、「最初の一歩」を踏み出したあとから始まる。
本当に試されるのは、歩み続けることの勇気。
最後に
以前、著者の「嫌われる勇気」(ダイヤモンド社)という本を読んで、もう少しアドラー心理学を知りたく読んでみました。
人間関係について、競争から協力へと縦の関係ではなく、横の関係から自分の価値を見いだすことも大切な一つかと感じました。
また、『人間の価値は、「どんな仕事に従事するか」によって決まるのではない。その仕事に「どのような態度で取り組むか」によって決まる』という言葉は、今後の仕事を進めていく上もで、重要だろうと思います。
さらに、今後、独立して仕事をしていくうえでは、まず最初に信用を得て、その後仕事を通じて信頼関係を築けるようになることを目指したいと思いました。
アドラー心理学に関する本を2冊読みましたが、私の頭の中ではまだかみ砕けていないことが多くあり、まだまだ理解は不十分な状態です・・・。
アドラー心理学に興味なある方は、読んでみてください。
なお、著者の「嫌われる勇気」(ダイヤモンド社)に関する私の書評はこちらを参照ください。
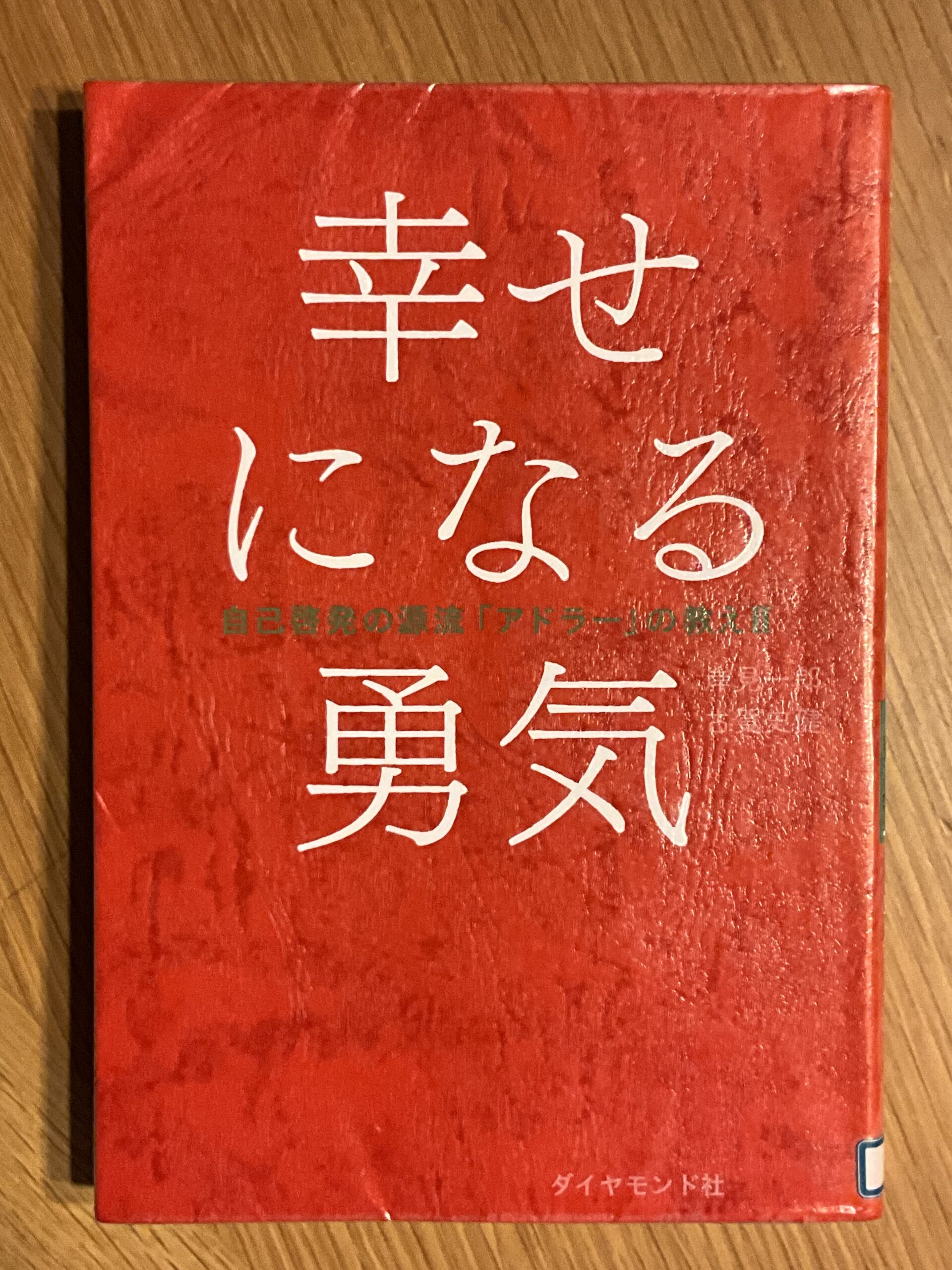
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/474bc9b5.aae640e7.474bc9b6.8b0594b0/?me_id=1213310&item_id=17754919&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6119%2F9784478066119.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

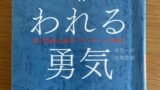
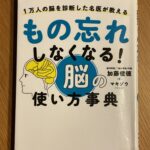
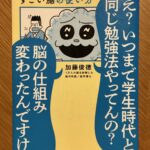
コメント