今回紹介する本は『新・貧乏は金持ち-「雇われない生き方」で格差社会を逆転する(橘 玲著 プレジデント社)』です。
この本では、マイクロ法人の設立とその利点について主に書かれています。
本書は、以下の5部構成になっています。
- 楽園を追われて-フリーエージェントとマイクロ法人の未来
- もうひとつの人格-マイクロ法人という奇妙な生き物
- スター・ウォーズ物語-自由に生きるための会計
- 磯野家の節税-マイクロ法人と税金
- 生き残るためのキャッシュフロー管理-マイクロ法人のファイナンス
1.楽園を追われて-フリーエージェントとマイクロ法人の未来
「楽園を追われて-フリーエージェントとマイクロ法人の未来」では、主に以下のことが述べられています。
- 日本はバブル崩壊後、年功序列から成果主義に移行。
日本企業が成果主義に追い込まれたのは、低成長のデフレ経済では日本型雇用が維持できないため。 - 企業が人員整理を行う際は、➀人員削減を行う経営上の必要性 ➁十分な整理解雇の回避努力 ③解雇対象者の選定の妥当性 ➃解雇手続きの妥当性を満たす必要がある。
➁には新規採用の抑制が含まれていると解されている。 - 格差問題は、規制緩和やグローバル資本主義によって引き起こされたというより、日本的な雇用慣行をめぐる「世代間闘争」であることが明らかになってきた。
年功序列と終身雇用を固守している限り、割を食うのは若者。 - 日本では、非正規労働者が人口三倍のアメリカとほぼ同数で割合が突出して高い。それに対してフリーランスやマイクロ法人は5%にも満たない。
- いまやサラリーマンは、中国やインドの若いサラリーマンによってエデンの園を追われつつある。今後十数年で1,000万人のフリーエージェントが誕生しても不思議ではない。
2.もうひとつの人格-マイクロ法人という奇妙な生き物
「もうひとつの人格-マイクロ法人という奇妙な生き物」では、主に以下のことが述べられています。
- 個人だと採用する際、履歴書等を提出し、人的資本(稼ぐ力)が問題になるが、会社だと新規に取引を始める際、社長や社員の学歴等は問われない。
- 会社は法的には「ひと」だが、株主という自然人(ひと)に所有される「もの」である。
法人は「ひと」であると同時に「もの」でもある。 - アメリカのフリーエージェントがマイクロ法人を設立する一番の理由は、株主の責任は出資金のみに限定される有限責任。
(個人事業主の場合は、無限責任) - 新会社法では、マイクロ法人は大企業と同様に、法人として全ての権利を保障されている。
- マイクロ法人では、自分を会社経営者として、ただ1人の社員である自分に給与を支払う。
自分で自分に給与を支払うので、自分にとって都合のいい額を決めることができる。
3.スター・ウォーズ物語-自由に生きるための会計
「スター・ウォーズ物語-自由に生きるための会計」では、主に以下のことが述べられています。
- スターウォーズを例にエンロンの破産について書かれている。
- 会計の世界に一大変革が起きたのは、ルネサンス期のベニスの商人たちが使い始めた複式簿記が体系されたとき。
- 会計の効用
- 投資のための会計(財務会計)
株主などの投資家に会社の財務内容を開示するための会計規則 - 納税のための会計(税務会計)
- ビジネスのための会計(管理会計)
会社の意思決定や実績評価のために用いる内部会計 - 夢を実現するための会計
- 管理会計のうち、特に中小企業の経営者を対象とした会計技法
- ビジネス体質を改善し、会社を再生させるなどの経営者の「夢を実現する」ためのもの
- 自由に生きるための会計
- フリーエージェントやマイクロ法人のための会計技法
- 成長ではなく安定を目指し、事業の拡大を最終目標にしない。
- 他の会計との違いは、法人(企業会計)と家計(個人会計)を連結決算し、ビンボーを冨に変えること。
- 投資のための会計(財務会計)
- マイクロ法人とは、個人が持つもうひとつの人格で、法人(マイクロ法人)と個人(家計)を連結決算しないと資産や損益の実態は見えてこない。
- 企業会計には、財務会計と税務会計の二種類あり、財務会計上の「収益・費用・利益」と税務上の「益金・損金・所得」は異なるから、企業の財務戦略では税務上の所得を最小にしつつ、会計上の利益を最大化することが求められている。
マイクロ法人を利用すれば、個人でもそれと同じことが可能になる。 - 個人企業家にとって、会計上の理想状態
- マイクロ法人と個人(家計)で税務上の所得がない。
- マイクロ法人若しくは個人(家計)で財務上の利益が計上できる。
※財務上の利益は、税務上の所得ではないので、無税で投資できる。
ー これがマイクロ法人の会計戦略
- 損益計算書を連結する(法人と個人のPLを連結する)
- マイクロ法人のPLで、売上と人件費+経費の会計が同額だと、法人の課税所得はゼロになる。
- 個人の税務会計で、マイクロ法人から支払われる給与と所得控除(給与、配偶者、扶養の各控除)+社会保険料の合計が同額になると、個人の課税所得はゼロになる。
- 個人の税務会計のうち、各種控除は税法が生活のために必要経費と認めたもので、いわば架空の支出。
実際に支払いが発生するのは社会保険料だけなので、それ以外は全て生活費に使える。 - さらにマイクロ法人では、生活費の一部を経費にできる(家賃やその他の経費等)
家計の実質収入は、給与(人件費)にこの額を加えたものになる。 - 家計の目的は、この無税の利益を貯蓄や投資に回し、将来に向けて富をたくわえることにある。
- 個人の税務会計のうち、各種控除は税法が生活のために必要経費と認めたもので、いわば架空の支出。
- 貸借対照表を連結する(バランスシートの時価と簿価)
- PLが1年間の収支を把握するものだとすると、バランスシート(BS)は事業(家計)の資産と負債の状況を一覧するための仕組み。
- 現金をどのように調達(ファイナンス)したかが、バランスシートの右側の負債・純資産(資本)の欄に記載され、その現金で購入したものが左側の資産の欄に記載される。
- マイクロ法人と家計のバランスシートを連結する。
- 冨を獲得する方法
- 売上(収益)を増やす。
- 費用(コスト)を減らす。
- 資産の運用利回りを上げる。
4.磯野家の節税-マイクロ法人と税金
「磯野家の節税-マイクロ法人と税金」では、主に以下のことが述べられています。
※磯野家を例に、マスオさんがマイクロ法人を設立したとして、述べられている。
- サラリーマン法人化とは、会社との雇用契約を業務委託契約に変え、同時にマイクロ法人を設立して、これまでと同じ仕事を続けながら、委託費(給料)を法人で受け取ることをいう。
- 個人の所得税と法人の法人税は税率が違うため、おおよそ年収300万円を超える分は法人で受け取った方が有利になりそう。
- 法人では、年度の最初に決めた役員への報酬=給与は損金算入できるが、賞与=ボーナスは損金算入できない。
- 法人を使った節税術
- 法人で生活経費を損金とし、個人で給与所得控除を受けることで、経費を二重に控除する。
- 家族を役員や従業員にして、役員報酬や給与を法人の損金にしつつ、給与所得控除を得る。
- 自営業者や中小企業向けに、日本国が用意した優遇制度を活用する。
- 自宅にマイクロ法人を登記したケースでは、家賃、水道光熱費、の二分の一はほぼ損金にできる。
同様に通信費、インターネットの接続料なども経費になり、仕事に関係すれば接待交際費や慶弔費も経費にできる。 - 事業に必要な資産(不動産、建物、機械類)は経費にならず、資産として減価償却することになるが、中小企業は30万円未満の資産を一括して経費処理できる。
- マイクロ法人から役員報酬を受け取る。
- 家族を従業員として雇用し、課税が発生しない年103万円以内で給与を支払う。
- 法人側が赤字になっていると、家計の余裕資金をさらに法人に貸し付けることで、さまざまな特典を享受できる。
- 法人に200万円貸付、法人が株式やファンドを購入したとすると、金融所得をその他の損益と通算できる。
個人では、利子20%の源泉徴収されるが、法人だと利子収入も損益通算され、決算が赤字なら源泉徴収された分は全額払い戻される。
株式の配当は、個人では配当所得で課税されるが、法人で受け取れば、「受取配当金の損益不算入」が適用される。 - 法人だとあらゆる金融商品のインカムゲイン(利子、配当所得)とキャピタルゲイン(譲渡所得)を合算できる。
- 法人だと収入が例えば200万円あって、200万円を投資し、200万円の損金を計上したとすると、損益は差し引きゼロになって税金はかからない。
- 合理的なの納税者は次のように行動する。
- 説明できない(アカウンタブルでない)ことはしない
- 説明できる(アカウンタブルな)ものは、すべて経費として損金計上する。
- そのうえで、税務調査で否認されたものだけ訂正する。
※この究極な姿が白色申告。
5.生き残るためのキャッシュフロー管理-マイクロ法人のファイナンス
「生き残るためのキャッシュフロー管理-マイクロ法人のファイナンス」では、主に以下のことが述べられています。
- ファイナンス:バランスシートを最適化するための財務戦略
- ファイナンスにおいて最も大事なのは、いったん借りたお金を約束通りきちんと返すこと。
これが信用となって、次はさらに大きな資金を借りられるようになる。 - ”奇跡のファイナンス”を実現する秘密は、信用保証協会と自治体の産業融資斡旋制度にある。
- キャッシュフロー計算書について
- 日本政策金融公庫の融資制度について
最後に
本のタイトルを見て面白そうだったので読んでみましたが、マイクロ法人を設立することが前提の話でした。
私の場合は、社会保険労務士法人を設立しても、一般的な法人とは違い業務内容には制約があるので、当てはまらない点も多々あると思います。
関心のある方は読んでみてもいいかと思いますが、本の内容を実践される場合はあくまでも自己責任でやってみてください。
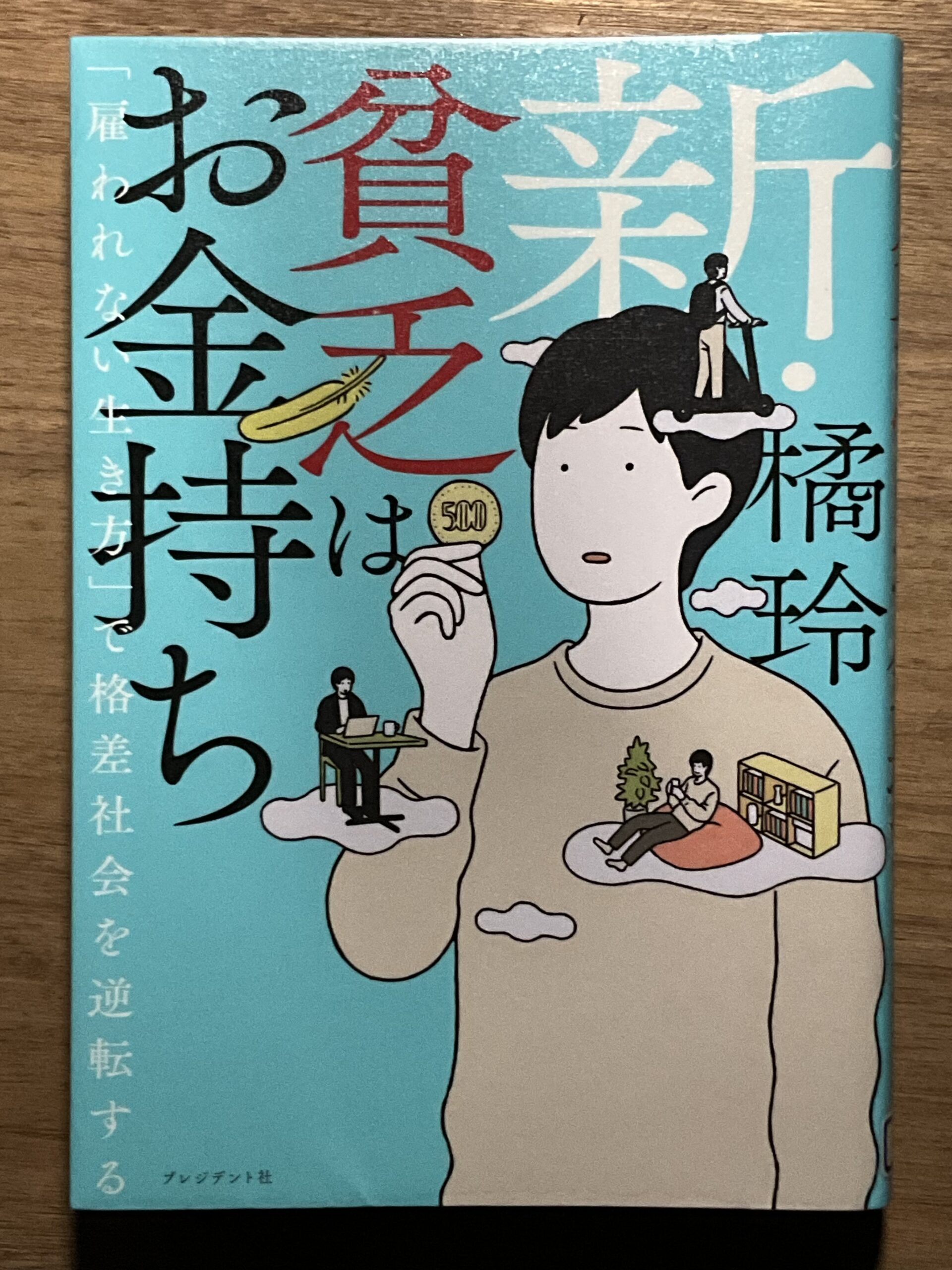
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47eed202.05b8d637.47eed203.a86b7738/?me_id=1278256&item_id=24640709&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F2181%2F2000017362181.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

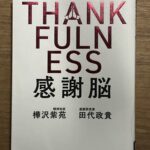
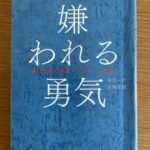
コメント