今回紹介する本は『「感謝脳」‐なぜ「感謝する人」だけが夢を現実にするのか(樺沢 紫苑、田代政貴著 飛鳥新社)」です。
本書は、以下の7部構成になっています。
- 感謝の正体
- 感謝のすごい効果
- 間違った感謝
- 感謝の分類
- 感謝のつくりかた
- 「感謝脳」実践ワーク
- 「感謝脳」が人生を変える
- 幸福心理学の研究と通して、親切や感謝をすることで、「実際に仕事のパフォーマンスが上がった」「メンタルが改善した」「睡眠が改善した」「体調が良くなった」「幸福度が上がった」というデータが蓄積されている。
- 感謝の3つの段階
- 一番下:「何かしてもらったら、ありがとう」という「親切への感謝」
- 真ん中:「当たり前のことに、ありがとう」という「日常への感謝」
- 一番上:「何が起きてもありがとう」という「逆境への感謝」
※一番上まで辿り着けたら「感謝脳」の完成。
- 普段から「感謝思考」を心掛けることで、誰でもステップアップし、「感謝脳」を持つことが出来る。
1.感謝の正体
「感謝の正体」では、主に以下のことが述べられています。
- どんなピンチに直面しても感謝できる「何が起きてもありがとう」の状態が「感謝脳」。
- 感謝とは、「ありがとう」や「ごめんなさい」という「言葉を射る」こと。
よって緊張した状態を緩め、相手の中に存在する神の心をも動かすという意味。 - 心を動かす行為そのものを感謝と言い、「ありがとう」は有り難いという感謝の気持ちを相手に伝えるために用いられる具体的な表現。
- 人が感謝を感じる4つの心理的な条件
- 恩恵の認識
自分が受け取った「良いこと」、恩恵が自分以外の人や自然界など、外から与えられたと理解していること。 - 恩恵の価値認識
自分が得たものや享受している恩恵の価値を高く認識していること。 - 恩恵の好意認識
恩恵をもたらした相手の優しい気持ちや好意を感じ取れていること。 - 見返りの不安認識
その「良いこと」は義務ではなく、見返りを求められていないと感じられること。
- 恩恵の認識
- 恩恵の認識と価値認識は、「モノや情報」が感謝の対象になっている。
- 恩恵の好意と見返りの不要認識は、「相手」が感謝の感謝の対象になっている。
- モノや価値に加え、与えてくれた人の親切な気持ちを理解することが、心からの「ありがとう」を感じるようになる大事な要素になる。
この心理的な積み重ねで「感謝脳」がつくられていく。 - 感謝は結果に対してするのではなく、瞬間瞬間の選択。
- 「感謝しています」と言うまでもなく、感謝反応が日常化しているのが感謝脳を持つ人。
- 感謝が多い人の3つの共通点
- 朗らかで、笑顔が多い、雰囲気が明るい。
- 人当たりが良く、その周りに人が集まる。
- エネルギッシュで活動的
- 感謝が多い人、「何が起きてもありがとう」と言える人の脳の状態を「感謝脳」と名付ける。
2.感謝のすごい効果
「感謝のすごい効果」では、主に以下のことが述べられています。
- 日常の当たり前なっていることにも「ありがとう」は多くある。
日常が「ありがとう」であふれていることに気づくことができると、特段よいことが起きていなくても、感謝できるようになる。 - 感謝はするものではなくて、心から込み上げてくるもの。
- 感謝の効果を最大限にする秘訣は、機嫌よく過ごすこと。
- 感謝には主に4つの効果がある(感謝の四大効果)
「心の健康」「身体の健康」「仕事の向上」という個人的な効果、会社や組織、チームなどに感謝が広がる集団的感謝によって「会社の改善」の効果が得られる。 - 心の健康の効果
- 睡眠の改善
- 健康になるために最も重要なコツは「睡眠、運動、朝散歩」
その中で最も重要な健康習慣が「睡眠」 - 「感謝の気持ち」は睡眠の質、時間、寝付きなど、睡眠を全般的に改善する。
(1~2週間、感謝を実践して日記を書くと睡眠が改善する。)
- 健康になるために最も重要なコツは「睡眠、運動、朝散歩」
- ストレス、うつ、不安の軽減
感謝の日記を3~4週間書くだけで、ストレス、うつ、不安が軽減する。 - 自己肯定感、自己効力感が高まる
- 感謝すると自己肯定感、自己効力感、幸福感などのポジティブ感情が高まる。
感謝する→自己肯定感UP→幸福度UP という流れ。 - 感謝の表現は、「自己効力感」を高める。
人から感謝の表現受けることで自己効力感が向上し、それがさらに「行動しよう」という気持ちを高める。
- 感謝すると自己肯定感、自己効力感、幸福感などのポジティブ感情が高まる。
- 人間関係が深まる
- 感謝の表現は、新しい人間関係の形成を促進する。
- 初対面の相手との関係形成を促進する。
- 感謝の気持ちは、親子関係や恋愛関係も向上させる。
- レジリエンスが高まる
- レジリエンス:「心の回復力」「心のしなやかさ」
- レジリエンスが高いとショックな出来事を体験しても、それを引きずらないですぐ回復できる。
- 感謝の気持ちが強い人ほどレジリエンスが高く、学業成績がよかったという研究結果がある。
- 学業成績がよくなる
- 感謝日記をつけると、学習へのやる気、モチベーションも高まる。
- 感謝の気持ちが強ければ強いほど、成績が良い。
- メンタル疾患に効果がある
- 感謝することで、ポジティブ感情が増えて、ストレスが減り、うつ症状、不安症状も減ることが示されている。
- 早く回復したい場合は、感謝日記も有効。
- 幸福度が高まる
- 感謝日記や感謝の手紙を書いたりする「感謝の介入」によって、幸福度がUPすることが、数多くの研究で示されている。
- 睡眠の改善
- 身体の健康の効果
- 心血管系の健康
- 感謝は身体の健康を促進し、血圧を下げ、ストレスを低減し、心臓患者の生活の質を向上させる。
- ロンドン大学の研究では、2週間の感謝日記を書くことで、ポジティブ感情が増加し、睡眠の質を改善し、最低血圧が低下した。
- 感謝は「心臓」によい!
- 痛みの軽減
- 感謝は慢性的な痛みを軽減する。
- 米国アラバマ大学の研究によると、2週間感謝日記を書くことで、慢性的な膝や股関節の痛みがある高齢者の健康状態が改善し、幸福度も高まった。
- 感謝は「痛み」に効く!
- 病気の苦痛の改善
- マレーシアのマラヤ大学の研究では、感謝日記を1週間書いたところ、苦痛スコア、病院への不安、抑うつスコ、慢性疾患治療の総合機能評価が大幅に改善し、幸福度スコアもUPした。
- 感謝は「病気の苦しみ」を取り除く。
- 健康的な行動の促進
- 感謝の気持ちを表現することで、「ジャンクフードはやめよう」といった健康的な食行動が促進されることが示されている。
- 感謝は「健康になりたい」という気持ちを強める。
- 死亡率の低下、寿命を延ばす
- ハーバード大学の研究によると、感謝が多いグループは、少ないグループに比べて、死亡率が9%低かった。
- 感謝は身体的健康に役立ち、死亡率を減らし、寿命を延ばしてくれる。
- 心血管系の健康
- 仕事の向上(個人)の効果
- 仕事のモチベーションの向上
- 感謝によって、自分の貢献が認められたと実感し、仕事に対する意欲が向上する。
自分にはできるという自己効力感、自分を律することができるというコントロール感が高まり、仕事へのモチベーションが向上する。
- 感謝によって、自分の貢献が認められたと実感し、仕事に対する意欲が向上する。
- 仕事のパフォーマンスの向上
- 感謝によって、活力やモチベーションが高まり、個人のパフォーマンスが向上する。
- 職場の人間関係の改善
- 感謝によって、人間関係が深まる。
職場においても実際、感謝の気持ちが強い従業員は、リーダーや同僚との関係が良好。
- 感謝によって、人間関係が深まる。
- 職場ストレスの減少
- 職場のストレスの9割が人間関係と言われている。
職場の人間関係が改善されれば、職場のストレスも減少する。 - 香港教育大学の研究では、感謝日記を週に2回、4週間書いたグループでは、ストレスとうつ症状の改善が認められた。
- 感謝の表現は、職場での相互性、ポジティブな評価、活力を高める。
- 職場のストレスの9割が人間関係と言われている。
- 仕事の満足度の向上
- 「教育」を対象とした感謝の介入により、仕事の満足度が17.9%向上し、離職率も低下した。
- 仮に全く人から評価されたり、感謝されたりしなくても、自分からの感謝で、仕事の満足度を高めることができる。
- 自己成長の促進
- 感謝を自己表現することで、自己改善、自己成長の意欲が高まる「自分にはできる」という自己効力感が高まる。
- 自分の成長を期待されていると感じ、より高い目標に向かって努力するようになる。
- 向社会的行動が増える
- 向社会的行動:他者や集団のために、自発的に行う行動で、思いやり行動とも呼ばれる。
- 感謝によって、他者貢献の行動が増える。
- 感謝されると、社会貢献がしたくなる。
- 仕事への幸福感の増大
- 仕事へのモチベーション、パフォーマンスの向上、所属感の向上、ストレスの減少によって、ワーク・エンゲージメントが増大し、仕事に「やりがい」を感じ、仕事が楽しくなる。結果として、幸福度が増大する。
- 仕事のモチベーションの向上
- 会社の改善(集団での仕事)の効果
- 感謝が会社の部署内、チーム内でも広がっていくと、お互いに感謝し合うようになる。そうすると会社の雰囲気も良くなり、仕事の効率も上がり、会社の業績UPにもつながる。
- 集団的感謝が引き起こす7つの効果
- 生産性の向上
- 感謝の気持ちは、従業員の効率、成功、生産性に非常に重要で、良好な人間関係と社会的支援を増加させる。
- 従業員個人のモチベーション向上、生産性向上にともない、組織全体の生産性も向上する。
- 会社への帰属意識、愛着の向上と離職率低下
- 感謝が多いほど、会社、組織への愛着が深まる。
- 感謝の気持ちが強い従業員は、リーダーや同僚との関係が良好で、幸福感と組織へのコミットメント(愛着)を高める。
- 組織に対する感謝の気持ちは、組織の目標達成したいという欲求を刺激し、帰属意識も高める。
- 会社への愛着が高まることで、離職率を下げる効果も得られる。
- 助け合いの行動の促進
- 職場の中での集団的感謝が進むほど、「助け合い」の行動を促進する。
- 人間関係が改善され、助け合い行動が促進され、コラボレーションが増え、チームワークと協力が強化される。
- 不正行為の減少
- 感謝によって道徳性が向上し、不正行為を控える行動をとることが、実験で明らかになっている。
- 企業内に「感謝の風土」を作ることが、不正行為の抑止につながる可能性がある。
- イノベーション促進
- 安全な心理状態の中では、新しいアイディアや意見が出やすくなり、イノベーションが促進される。
- 社内に集団的な感謝の気持ちがあると、組織内の人々の「質の高いつながり」を強化し、サービスの革新性を高め、企業の財務実績を高めることがわかった。
- 企業イメージの向上
- 感謝を大切にする企業は、従業員だけでなく、顧客からも良い印象を持たれ、企業イメージが向上する。
- ワーク・エンゲージメントが高まる
- ワーク・エンゲージメント:「仕事から活力を得ていきいきとしている」(活力)、「仕事に誇りとやりがいを感じている」(熱意)、「仕事に熱心に取り組んでいる」(没頭)の3つが揃った状態。
- ワーク・エンゲージメントが高まると、以下の効果が期待できる。
- 離職率の低下
- 生産性の向上
- 従業員と会社の関係性の改善
- 職場の運息の改善
- 従業員にとって働きやすい環境の確保
- 組織の活性化
- 職場で集団的な感謝の生酛を育むと、ワーク・エンゲージメントが大幅に向上する。
- 「集団的な感謝」:職場の中で「感謝の言葉」が日常的に飛び交う状態。
- 生産性の向上
- まず、自分から「感謝する」「ありがとうと言う」ことで、満足度が上がり、仕事が楽しくなり、パフォーマンスも上がり、仕事で評価されるようになる。
- 感謝は伝染する。
他人の感謝を目撃することで、「自分も人を助けたい」という感情が湧き上がる。
3.間違った感謝
「間違った感謝」では、主に以下のことが述べられています。
- やってはいけないこと
陰口は相手に伝わる。表で「ありがとう」と言いながら、陰口をたたいて相手に伝わると、関係が悪くなる、 - 感謝できない人の共通点
- 自己肯定感が低い
自分の成果や他人からの親切な善意を受け入れることが難しい。 - ネガティブ思考
ネガティブ思考が強いと、人から親切にされてもネガティブに捉え、感謝の念が生まれない。 - 人のせい、環境のせいにする(他責)
他責にする人は、自己成長もなければ、感謝もないので、人が離れていく。 - クレクレ星人
- 自己中心思考で自分が得をすればいいという世界で生きている人。
一時的にうまくいっても関係を続けることは不可能。長い目でみるとうまくいかず人も離れていく。 - クレクレ星人の逆は「与える星人」
- 自己中心思考で自分が得をすればいいという世界で生きている人。
- ポジティブすぎて反省しない
度合いが過ぎると問題。ミスをしてもポジティブでいられると、次から頼られなくなり、感謝も生まれない。 - 功績を自分ひとりでやった実績のように語る
たったひとりで成し遂げられる大きなことなど存在しない。感謝の心が周囲に伝わることで、更なる大きなことを成し遂げられるようになる。 - 完全主義者
「完全主義者」は、完璧を求めるあまり、自分の成果や他人の努力を評価することが難しくなり、感謝の意識が希薄になる傾向がある。
- 自己肯定感が低い
- 「悪口」が多い人は、脳と身体のストレスが増えて、健康に悪い。
認知症リスクが3倍に高まり、寿命も縮まる。 - 東フィンランド大学の研究によると、世間や他人に対する皮肉・批判度の高い人は、認知症リスクが3倍という結果になった。
- 「ポジティブ思考」の人は、「ネガティブ思考」の人より、10倍以上長生きをする。
- 悪口はストレス発散にならない。科学的には完全に間違い。
悪口を言うと、ストレスホルモンのコルチゾールが高まる。
「悪口を言う」ことは、ストレスを減らすのではなく、ストレスを増やす。 - 屈辱の言葉、ネガティブな言葉を発すること自体、脳への害になる。
他人の悪口を言っているつもりでも、自分が悪口を言われているのと同じ悪影響を自分自身が受けてしまう。 - ネガティブ思考の人は、偏桃体が肥大している。
- 「ネガティブ言葉」を1回言うと、「ポジティブ言葉」を3回言って、ようやくバランスが取れる。
悪口が感謝の効果を相殺する。 - 悪口が多い人には、感謝の効果は出ない。
4.感謝の分類
「感謝の分類」では、主に以下のことが述べられています。
- 感謝の3つのステージ
- 第1ステージ:「親切への感謝」のステージ
- 第2ステージ:「日常への感謝」のステージ
- 第3ステージ:「逆境への感謝」のステージ
※第3の「逆境への感謝」のステージが感謝脳に変わった状態。 - 第1ステージ:親切を受けたり、良いことがあったら感謝する状態。
(自分の外側から来るものへの感謝)- 口に出して「ありがとう」を伝えて、第1ステージクリア。
- 第2ステージ:当たり前のことに感謝できること。
(自分の内側から起こる感謝)- 「当たり前のことに、ありがとう」が身についた状態は、まさに無限に運が良くなる状態。
- 第3ステージ:あらゆるものへの感謝、万物への感謝と呼べる最終ステージ
- このステージに来た人、何が起きてもありがとうが言える人は、「感謝脳」の完成を意味する。
- 心の3つのステージ
- 第1ステージ:「不安」のステージ
- 第2ステージ:「自立」のステージ
- 第3ステージ:「太陽」のステージ
- 「不安」のステージ:ぐちや不平不満ばかり言いながら、不安の中で生きているステージ。「他責」のステージでもある。
- ぐちや不平不満を周囲や環境のせいにすることから生じる。
- 「自立」のステージ:「自分は何のために生まれてきたのか?」「自分の使命は何か?」など、自分のことを知っていくステージ。
- このステージになるとぐちや不平不満に生きるのではなく、「すべての出来事は自分に必要だから起きている」と解釈できるようになる。
- 「太陽」のステージ:全ての出来事に感謝できるようになり、感謝脳で生きるステージ。
- 幸福度も上がってくる。
- 感謝によってセロトニン、ドーパミンが活性化する。
- 「感謝」で脳は喜び、そのプロセスにドーパミンが関与していると考えられる。
- 「感謝」の効用のひとつとして、「不安、うつの減少」がある。
感謝はセロトニンを活性化する。 - 「感謝の感情」や「幸福な気持ち」などのポジティブ感情を抱くときにエンドルフィンなどのオピオイド系が活性化させる。
エンドルフィンには、鎮痛効果に加えて、ストレス解消効果がある。 - 人に親切にすると、親切にした人だけでなく、親切にされた人にもオキシトシンが分泌される。
オキシトシンは3大幸福物質で、コミュニケーションやスキンシップでも分泌され、心と身体の両方に対して、高い癒しの効果を持った物質で「親切」という感情に結びついている。 - 親切にされた人は、多くの人が感謝の気持ちを持つが、感謝によってオキシトシンが分泌される研究も発表されている。
- 感謝による心と身体への癒し効果をもたらすものとして、セロトニン、ドーパミンに加えて、オキシトシンも深く関わっている。
- 親切と感謝によって、セロトニン、オキシトシン、ドーパミンという3大物質の全てがコンプリートする。
- 感謝脳が、セロトニン、オキシトシン、ドーパミンが揃った状態。
セロトニンによって、笑顔が多くなり、雰囲気が明るくなる。
オキシトシンによって、人間関係がうまくいく。
ドーパミンによって、エネルギッシュで活動的になるため仕事でも成功しやすい。
親切と感謝によって、「幸福の連鎖」が引き起こされる。 - 3つの幸福物質が揃うと集中力、判断力、記憶力などの認知機能が高まり、仕事のパフォーマンスも爆上がりする。
- 一方的に相手に「親切」にする。相手に感謝する。それだけで3つの幸福物質が全て揃う。
1日3分感謝日記を書くだけでいい。感謝日記の研究では、2週間でも幸福度UPが認められた。 - 最も即効性があり、最も簡単にできる「幸せになる方法」は、感謝と親切。
5.感謝のつくりかた
「感謝つくりかた」では、主に以下のことが述べられています。
- 「感謝思考」を意識する。
- たとえ仕事で失敗があったとしても、「この経験から何を学べるのか?」「学びと成長の機会をありがとう」と前向きに捉えるのが感謝思考
- 感謝思考は、「良いことに目を向ける」ことで、自然と心も穏やかになっていく。
- 自分の幸せの定義をつくってみる。
- お金、心の状態、役割(仕事)、時間、健康、パートナー・仲間、コミュニティ等、自分だけの幸せの最低基準を作ってみる。(日常にも感謝して)
- しっかり伝わるの感謝の3大法則
- 必ず一度は相手の目を見て感謝を伝える。
- 何に対して感謝しているのか、具体的に伝えている。
- 報恩感謝の姿勢で、相手に感謝されていることを意識する。
- 相手に感謝されることを探してみる。
- ありがとうの5段活用
- 「ありがとう」と思っている。
- 「ありがとう」を声に出して伝えている。
- 何に対して「ありがとう」なのか、具体的に伝えている。
- 対手に感謝されるようなことを意識する。
- 自分がしてもらった「うれしかったこと」を他の人にもしてあげる。
- 「ありがとう」以外の感謝の言葉 5選
- 感謝しています(お礼申し上げます)
- より丁寧に感謝を伝える場合は、「厚くお礼申し上げます」
- おかげさまで(ご配慮いただきまして)
- 助かりました(恐れ入ります/恐縮です/かたじけない)
- うれしいです(光栄です/みょうりにつきます)
- 励みになります(身に余るお言葉です)
- 感謝しています(お礼申し上げます)
- 少し表現を変えることで、感謝を伝えることができる
- 「も」を加えて伝える。
例:「今日のご飯おいしい!」→「今日もご飯おいしい!」
※いつも感謝していると伝わる。 - 相手の名前を加えて伝える。
例:「ありがとう」→「〇〇さん、ありがとう」
- 「も」を加えて伝える。
- 感謝は、時間が経って再度伝えることで、さらに強く伝わる。
- 夢や目標を達成するには、人の協力は不可欠。
実現に向けて動いている時に、周りに感謝しながら、感謝されるような動きが出来る人は、夢の実現が近づいたり、早まったりする。
夢をかなえたい!を思ったそのとき、そこに感謝が生まれるかどうか?
これが実現の可能性を左右する大事な要素になる。 - 仕事において、感謝されないものは成り立たない。
- 幸せだから感謝するのではななく、感謝するから幸せになる。
- 感謝される与え方の基本、3大法則
- 相手の話を笑顔で聞く
聞く行為も立派な「与える」行為 - 自分が与えている相手が喜ぶことを考える。
- 人は自分が求めているものを与えられたら喜ぶ。
喜ぶと同時に、心を開くようになり、信頼関係が築けるようになる。
そのためにも相手のニーズを探ることが大事。 - 経験や知識も与えられる。共有すること。
- 人を紹介することも与える行為。価値観や目標が同じ人同士をつなげることも人から喜ばれるポイント。
- 人は自分が求めているものを与えられたら喜ぶ。
- 見返りは求めない
- 普段から与える姿勢がいつか自分にかえってくる。
- まずは、自分から相手に何ができるか? 考えてみる。
- 相手の話を笑顔で聞く
- 自分から相手に対して、ギブすることも「感謝脳」の状態。
6.「感謝脳」実践ワーク
『「感謝脳」実践ワーク』では、主に以下のことが述べられています。
- 「感謝日記」の驚くべき効果
- 日々の感謝したことを振り返る方法だが、効果は最大級!
- 「感謝日記」を続けることによって、日常への感謝ができるようになれば、人の親切心に気づくことで更なる感謝が生まれる。
- 「感謝日記」は、「感謝を能動化する」ためのツール。
- 感謝日記を10週間書くだけで得られる驚くべき効果
- 身体的効果:「免疫力UP」「痛みの軽減」「血圧の低下」等
- 心理的効果:「ポジティブ感情が高まる」等
- 社会的効果:外交的になる、孤立感、孤独感の低下等
- 感謝日記の最大の良いところは、「相手がいらない」こと
- 「今日も3食ご飯が食べられたことに感謝」「今日1日健康で過ごせたことに感謝」等
- 「感謝日記」の具体的な書き方
- 寝る直前に書く。
- ノート(紙)に書く(アナログ)※手で書いた方が高い効果が期待できる。
- 今日あった感謝の出来事を思い出しながら、3つの感謝を書く。
- 最初は短くていい。1個1行で最低3行でOK。
- 書いた内容をイメージしながら眠る。
- まずは、4週間連続して行う。
- 感謝日記を書いたらすぐに布団に入り、書いた内容をイメージしながら、「感謝の気持ち」のまま眠りにつく。
- 感謝日記を書くこと以上に、「感謝とポジティブな感情のまま眠りにつく」ことが重要。
- 「感謝日記」の「応用編」
※物足りなくなったり、マンネリになった場合- 「ありがとう」を他人にも意識して言う
- 7個の感謝を書く
- 長文で感謝を書く
- 「感謝された」出来事を書く
- 「親切日記」を取り入れる
- 「1日3回」人に親切をして、それを1日の最後に記録する。
- 感謝するとセロトニン、ドーパミンが分泌し、人に親切にするとオキシトシンが分泌される。
- 意識しなくても「逆境への感謝」「万物への感謝」をしている状態が「感謝脳」。
- 万物感謝ワーク
- まずは身の回りのものに「ありがとう」と伝えていく。
- 自然界に「ありがとう」を伝えていく。
- ご先祖さまに「ありがとう」を伝えていく。
- 自分に「ありがとう」を伝えていく。
- 家族、仲間、恩人に「ありがとう」を伝えていく。
- まだ会ってない人に「ありがとう」を伝えていく。
- 対象物を定めず「ありがとう」を伝えていく。
- 「感謝離」:感謝しながら手放す。
- 「感謝の深掘り」5ステップ連想法
- 直接的感謝
直接見るものに感謝 - 関わった人に感謝
- 関わった環境に感謝
- 自分自身に感謝
- 全体を俯瞰して感謝
- 直接的感謝
7.「感謝脳」が人生を変える
『「感謝脳」が人生を変える』では、主に以下のことが述べられています。
- 感謝日記や感謝ワークを実践していくことで、感謝脳への変化ができてくると、さまざまな変化が起きてくる。
- 感謝脳になると、ずべての物事の捉え方が「感謝ベース」になり、人から受けている今まで気づけなかったような思いやりが見えるようになる。
- 小さなことが、気にならなくなったという例が数多くある。
- 感謝のベースが「Being感謝的生き方」(普遍的感謝:どんなことにも感謝を抱いている「逆境への感謝」ステージ、感謝脳の状態)へとシフトする。
- 感謝脳でいることによって、脳がアルファ波を発するようになる。
創造性を高める脳波と言われており、新しいアイディアが浮かびやすくなる。 - 病気を受け入れ感謝できるようになると、自然に治ることが多い。
- 感謝する人は、病気のリスクも下がり、死亡率も下がる。病気も治りやすくなる。多数の研究によって示されている。
- 患者さんに感謝の言葉が増えてくると、急に回復に向かう。
- 感謝や他者貢献しながら良くなっていく
- 感謝の気持ちが湧いてくるとセロトニン、オキシトシンといった、リラックス物質が分泌され、「副交感神経」が優位になる。
- 身体がリラックスした状態、休息モード、回復モードに切り替わる。
- 「回復→感謝」ではなく、「感謝→リラックス→回復」というプロセスをとる。
- 身体がリラックスした状態、休息モード、回復モードに切り替わる。
- 自分が感謝するだけで、セロトニン、オキシトシン、ドーパミンなどの幸福物質がコンプリートする。
最後に
日頃から感謝をすることの重要性に気づかされた本でした。
感謝することにより、さまざまな効果があることが分かりました。
何があっても感謝するということは、容易なことではありませんが、実践しないことには効果を実感することができないので、少しずつ日常のありふれた事柄にも感謝し、「感謝脳」となるべく実践してみようと思います。
感謝がもたらす効果について興味のある方は、一読されても良いかと思います。
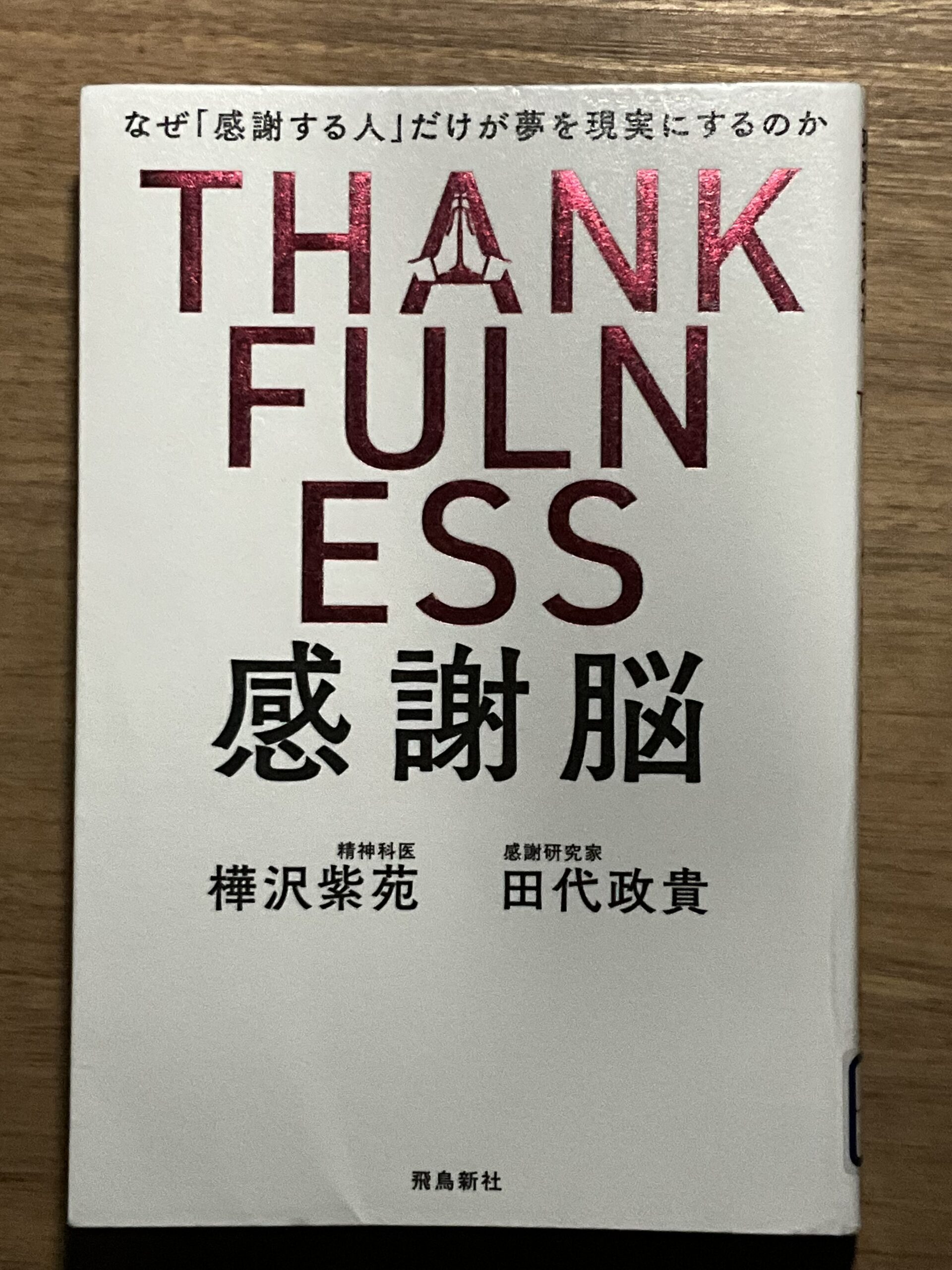
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/474bc9b5.aae640e7.474bc9b6.8b0594b0/?me_id=1213310&item_id=21431119&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0524%2F9784868010524_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

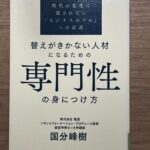
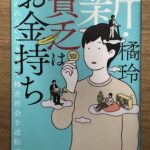
コメント