今回紹介する本は『替えがきかない人材になるための「専門性の身につけ方」(国分 峰樹著 フォレスト出版)』です。
専門性とは、知識をインプットすることではなく、アウトプットでようになることで、「勉強」ではなく、「研究」のやり方を知る必要があります。
本書は、以下の構成になっています。
- 専門性とは何か
- 専門性が求められる時代
- 「専門性の身につけ方」が武器になる
- 専門性を身につける方法を知ろう
- 専門性を身につけるステップ
- 自分らしい問いを立てる
- オリジナリティを発見する
- 多様な意見を尊重する
1-1.専門性が求められる時代
「専門性が求められる時代」では、主に以下のことが述べられています。
- 次の時代に求められるスキルを先読みし、付加価値をつけることが重要。
コモディティ人材では、AIに仕事を奪われることになる。 - 現状維持ではなく、より生産性の高い人材を目指すことが要求されている。
- AIに取って代わられない専門性を身につけることが重要。
- 現状AIが不得意で、人間が優れていると考えられる能力は、「創造性思考」や「社会的知性」。
- 「創造性思考」とは抽象的な概念を整理する能力で、「社会的知性」は交渉や説得といった、高度なコミュニケーション若しくは他者とのコラボレーションをする力。
- 「先を見通し、戦略的に手を打っていく力」(先見性と戦略性)と「どのような変化にも的確に対応していく力」(多様性と柔軟性)が求められる。
- AIなどのテクノロジーの進化を見据えた「先見性と戦略性」のある専門性は何か、ビジネスの劇的な変化に適応できる「多様性と柔軟性」のある専門性とは何かについて考える必要がある。
- 人々がそれぞれの価値を生み出すスタイル・働き方を追求する。
- 成果や生み出した価値、信用度が評価の基軸となる。
- 会社という組織のあり方が、ヒエラルキー型から、ネットワーク型に変化する。
- 「個性的な専門性」の価値が高まっていく。
- 中途半端な専門性では、稼げなくなる。
- リスキリングや社会人の学び直しが大切。
→他人に学びを強要されるのではなく、自ら決めることが大切。 - 特にデジタル・リスキリングは自ら学ぶ意思を持って、自分の時間を使って自主的に練習することが重要。
- ビジネス・パーソンが取るべき選択は、AIが進化してもできないと思われる領域の専門性を身につけること。
1-2.「専門性の身につけ方」が武器になる
『「専門性の身につけ方」が武器になる』では、主に以下のことが述べられています。
- 「専門性を身につけるスキル」がきわめて重要になってくる。
- 専門性が身につかない4つのパターン
- すぐに役立ちそうな知識を吸収しようとする
- ダメな理由
- すぐに役立つことは、すぐに役立たなくなる。
- 「役に立つということの時間軸」を意識しなければならない。
- ダメな理由
- 年収をアップさせるために勉強する
- ダメな理由
- 専門性を身につけてそれをブラッシュアップしていくという観点では、お金をモチベーションにした勉強は、いずれどこかで限界が訪れる。
(インセンティブが効かなくなると、努力する目的や意義を喪失し、努力を停止してしまう)
- 専門性を身につけてそれをブラッシュアップしていくという観点では、お金をモチベーションにした勉強は、いずれどこかで限界が訪れる。
- 「本人がそれを努力だと思っていない」「むしろ楽しんでいる」という状態に持っていくのが一番。
- 「嫌いなことをやらない」という戦略は、専門性を身につけるために欠かせない。
- 自分が好きなこと、やりたいと思うこと、面白いと感じることを見つけて、内発的動機づけ(好きだから)で動いた方が、専門性を身につける近道になる。
- ダメな理由
- 過去の実績や経験に価値を置いている
- ダメな理由
- 学びよりも過去の実績や経験に価値を置いていることで、専門性がアップデートされず、錆びついてしまうといった事態。
- 知識が陳腐化していくことを前提として、専門知識をアップデートしつづけようという気持ちがないと、過去の時点で専門家だったとしても、現在や未来における専門家ではなくなってしまう。
- 自分の専門性が賞味期限切れや旬の時期を過ぎていないか、棚卸しをする必要がある。
- 現代のビジネスでは、「まだ答えがない問題」に取り組むことが求められている。
ビジネスの価値を創出するポイントが「問題を解く」ことから、「問題を発見する」「問題を提起する」ことにシフトする。 - 新しい環境から柔軟に学び続ける人が価値を生み出す。
- ダメな理由
- 仕事に直結する専門分野しか目に入らない
- ダメな理由
- 今の仕事に直結する専門分野しか眼中になく、自分の興味・関心を吟味しないまま手をつけた結果、専門性がなかなか身につかず、アップデートもされていかないことが発生する。
- 専門性を身につけるためには、「やらなきゃ」「やったほうがいい」ということよりも、「やりたい」という気持ちを推進力にして取り組んだ方が断然速い。
- 自分が面白いと思える分野に目を向けて、「専門性の身につけ方」自体を習得することが長い仕事人生においては強力な武器になる。
- ビジネスの世界においては、ルールや制度があっという間に変わっていくことを意識することが重要。
- ゲームチェンジが起こると、前例主義は役立たなくなる。
- ダメな理由
- すぐに役立ちそうな知識を吸収しようとする
- 専門性を身につけるためには、「専門性の身につけ方」を身につけること、「専門性を身につけるスキル」が重要。
専門性の身につけ方は「型化」されているので、専門性を身につける「型」を習得することが極めて重要。 - ビジネスパーソンが「型」を学ぶことで、自分の仕事において「ビジネスの新たな価値となる知識」=「ナレッジ」を創造できるようになる。
1-3.専門性を身につける方法を知ろう
「専門性を身につける方法を知ろう」では、主に以下のことが述べられています。
- 専門性は、専門知識のインプットではなく、専門知識のアウトプット。
専門知識をどんなにインプットしても、それが専門知識のアウトプットにつながらなければ、「専門性」とは呼べない。 - 専門性とは、新しい知識を生み出すことであり、専門知識の「消費者」ではなく、専門知識の「生産者」になることを目指す必要がある。
そのためには、「専門知識をどうやって生み出すことが出来るのか」という生産の仕方を理解することが重要。
その答えは「研究」にある。 - 知識を進化させるのが研究であり、研究は「新しい知識を生み出す技法」、そしてこの技法こそが「専門性の身につけ方」。
- 専門性とは「構造的な知識」。
- 専門知識とは、その構造を把握していることが専門知識たるゆえんで、構造が把握できていない状態の情報をいくら入手しても、それだけでは専門知識と呼べない。
- 重要なのは、自分の頭の中で知識が「構造化」されていること。
- 知識を構造化する軸となる価値感とともに、既存の知識を単に総合するのではなく、その先に例えば自分は何を見たいと思うのか、自分は何を知らないと思うのか、そこが埋まると何ができると思うかを創造する必要がある。
レゴブロックでいうと、自分のなかに何かつくりたいもののイメージがなければ、ひとつひとつの知識を組み立てて構造化していくのは難しいということ。 - 知識は「出現」するものではなく、「進化」するものだということを常に意識する必要がある。
新しい知識はすべてこれまであった知識の進化形。 - 時代は変化するので、かつて専門家だった人が、もう専門家として通用しないといったことも珍しくない。
- 「新しい知識を生み出す」というのは、断片的な情報を集めるのではなく、知識と知識の新たな関係性を発見して、知識の新しい構造をつくっていく行為としてとらえることが出来る。
- 研究は、専門性を身につけるための「型」。
- 今ある専門知識を「勉強する」ことではなく、今はない専門知識を「研究する」ことが、専門家になるための唯一の道。
2-1.自分らしい問いを立てる
「自分らしい問いを立てる」では、主に以下のことが述べられています。
- ポイントは「自分らしい」という点にこだわることと、「問いを立てる」ことの重要性を理解すること。
「問いを立てる」というのは、自分で問題をつくること。 - 問いの形をイメージする。
- 「自分ならではの視点」を、疑問文の形で表現する。
- 専門性を身につける「型」を自分のものにするためには、自分の興味・関心がある領域において、自分が面白いと思うポイントを見つけることが起点となる。
- 自分らしい問いを探し当てられるのは、自分の興味・関心であり、問題意識。
- 何の興味・関心も知的好奇心問題意識ももたないまま、専門性を身につけることはできない。
自分らしい問いがあれば、自分らしさを活かした専門性が身につく。 - 自分ならではの興味・関心・知的好奇心、問題意識を掘り下げると自分にしか生み出せないような、「新たな知識のアウトプット」=「専門性」につながる。
- 専門性とは、「新しい知識を生み出すこと」であり、新しいことを開拓していくためには、自分が面白いと思うことを掘り下げていくことが一番の近道。
自分がやりたいと思えることに目を向けることが起点となる。 - 新たな知識は、知的好奇心から生まれる。
- 自分ならではの面白いポイントが見つかれば、専門性を身につけるための大きな一歩を踏み出せる。
- 自分の考えや思考に変化を与えるような、知識に触れる機会を自分でアンテナと立てて作らないと、考えや思考力がアップデートされないまま残されていくことになる。
- 知識というのは進化していくので、安定ではなく、変化が必要。
- 自分らしい問いというのは、自分の人生にとって重要な意味を持つ問題と考えられる。
- 専門性は、今の仕事や会社で必要に迫られて身につけるような浅はかなものではなく、自分らしさやこだわりを仕事で活かしていこうとする思いに引っ張られて、身につけることが出来る。
- 専門性の出発点となるのは、「仕事で必要だから」ではなく、「自分にしかできないことをやりたい」です。
- アウトプットを意識したインプットをする。
※以下のような問題意識を持つ。- それは本当か?
- 再現性は?
- 他の方法は?
- 納得できない!
- アウトプットを目的として、インプットする。
- 「専門性をつくる」というのは、他の人にはない「自分独自の専門領域をつくること」
- 専門性は、「広く浅い」よりも、「深く狭い」ことが価値を生む。
- 問いを立てることで、専門性を身につけていくためのスタートが切れる。
- まだ答えのない問いを立てることが、専門性の入口。
- 「もっと知りたいのに」「なんかちょっと違うんじゃないか」「こういうことなんじゃないだろうか」といったことを問いの形にすることで、専門性を身につけるための道が見えてくる。
- 本当に役に立つのは、「専門知識そのもの」ではなく、「深堀力」。
- 「深堀力」とは、「見えない構造を明らかにする力」、別の言い方をすれば、「メカニズムを明らかにする」こと。その背景に何があるのかを考える。
- 「深堀力」を習得できれば、専門性を身につけることが出来る。
2-2.オリジナリティを発見する
「オリジナリティを発見する」では、主に以下のことが述べられています。
- 専門性を身につけるためのファーストステップとして、「自分らしい問いを立てる」ということができたら、次は「オリジナリティを発見する」ことがセカンドステップになる。
- セカンドステップは、「すでにある知識の集合」に対して、過去の文献をあたって「すでにわかっていること」を整理することで、自分の立てた問いが「まだわかっていないこと」だと明確になれば完了となる。
自分の立てた問いの「オリジナリティを発見する」必要がある。 - オリジナリティを発見するというのは、「ブルーオーシャン戦略」と言える。
- 専門性は狭くて小さい「自分独自の専門領域をつくること」
- ビジネスにおいて価値ある専門知識とは、「一般的な専門知識」ではなく、「差別化された専門知識」。
- 「この領域はアイツに聞け」というオリジナリティを発見することが、自分の専門性を差別化するゴールになる。
2-3.多様な意見を尊重する
「多様な意見を尊重する」では、主に以下のことが述べられています。
- 世の中にすでに存在する専門知識をインプットするのではなく、まだ答えのない「自分らしい問いを立てる(ステップ1)」ことで、すごく狭くて小さい領域であったとしても、専門領域における空白地帯を見つけて、そこから新規性と独自性のある知見を深堀りすれば、自分ならではの専門性をつくることが出来る。
- 専門性とは、一般的な知識を広く浅く知っているだけで認められるものではなく、少しでも差別化された知識をアウトプットすることによって確立される。
- オリジナリティとは、「すでにある知識の集合」との距離を意味するので、どこまでが既知の領域でどこからが未知の領域なのかをはっきりさせることで、専門領域における自分の「オリジナリティ」を発見する(ステップ2)ことにつながる。
- 最後のステップでは、自分が立てたオリジナルな問いに対して答えを出すこと。
ここで重要なのは「多様な意見を尊重する」(ステップ3)というプロセス。 - 自分が立てた問いに答えていくにあたって、まず認識しなければならないことは、そこには「正解」はないということ。自分の頭で考えるしかない。
- 答えを探し当てることよりも大切なのは、問いと向きあって自分の頭の中で考えることで見につく深堀力だと言える。
- 頼りになるのは、自分自身の思考力。
- 自分の頭で考えているつもりでも、「〇〇会社の社員としての自分」「今の仕事をしている自分」の立場が大前提になって、その目線から物事を見てしまう、そういう視点からしか物事が見られなくなってしまっている。
- 対策のポイント:みんなで一緒にテクノロジーを使って、考える仕組みを作って考える。
- 「私の会社では」「私の仕事では」といった視点でばかり物事を捉えたり、考えたりしていると、個別の事情に左右され「それってあなたの感想ですよね」というレベルの話にしかならず、「見えない構造を明らかにする力」=「深堀力」は身につかない。
- 「抽象的に物事を理解する」ということの大切さを意識する必要がある。
- 専門性を身につける上では、具体的な現象を「抽象化」して認識することが鍵となる。
「少子高齢化」「デジタル化」といった「〇〇化」という形で減少を抽象化すると、一般的な概念として捉えることが可能。 - 小さな問いにブレイクダウンすることで、小さな問いに答えを出していけば、答えにたどり着ける。
- 小さな問いに答えを出していくためには大切なのが、「多様な他者と議論する」こと。自分とは考えが違う人の意見によって、ひとりでは気づかなかった視点や論点が見つかる。
- 最後のステップで重要なのは、多種多様な意見や価値観を交わらせること。
- 専門性は一度身につけて終わりになるものではなく、新境地を開くためにブラッシュアップし続けるもの。
歩みを止めれば失われていくのが、専門性。
最後に
今後、社会保険労務士として活動していくうえでの専門性の身につけ方のヒントになればと思い、この本を手に取ってみました。
現在も行っていますが、法律・制度は絶えず変わっていくので、自分の知識のアップデートの必要性を改めて感じました。
最後の言葉にもありますが、「歩みを止めれば失われていくのが専門性」、この言葉を常に念頭に置きながら自分の専門性をアップデート、ブラッシュアップするとともに、AIに仕事を奪われないような専門性を身につけていかなければならないと感じました。
そのためにも自分のオリジナリティを発見し、自分独自の専門領域つくることが課題だとも感じました。
自分自身の専門性の身につけ方に悩んでいる方は、一読される価値はあるかと思います。
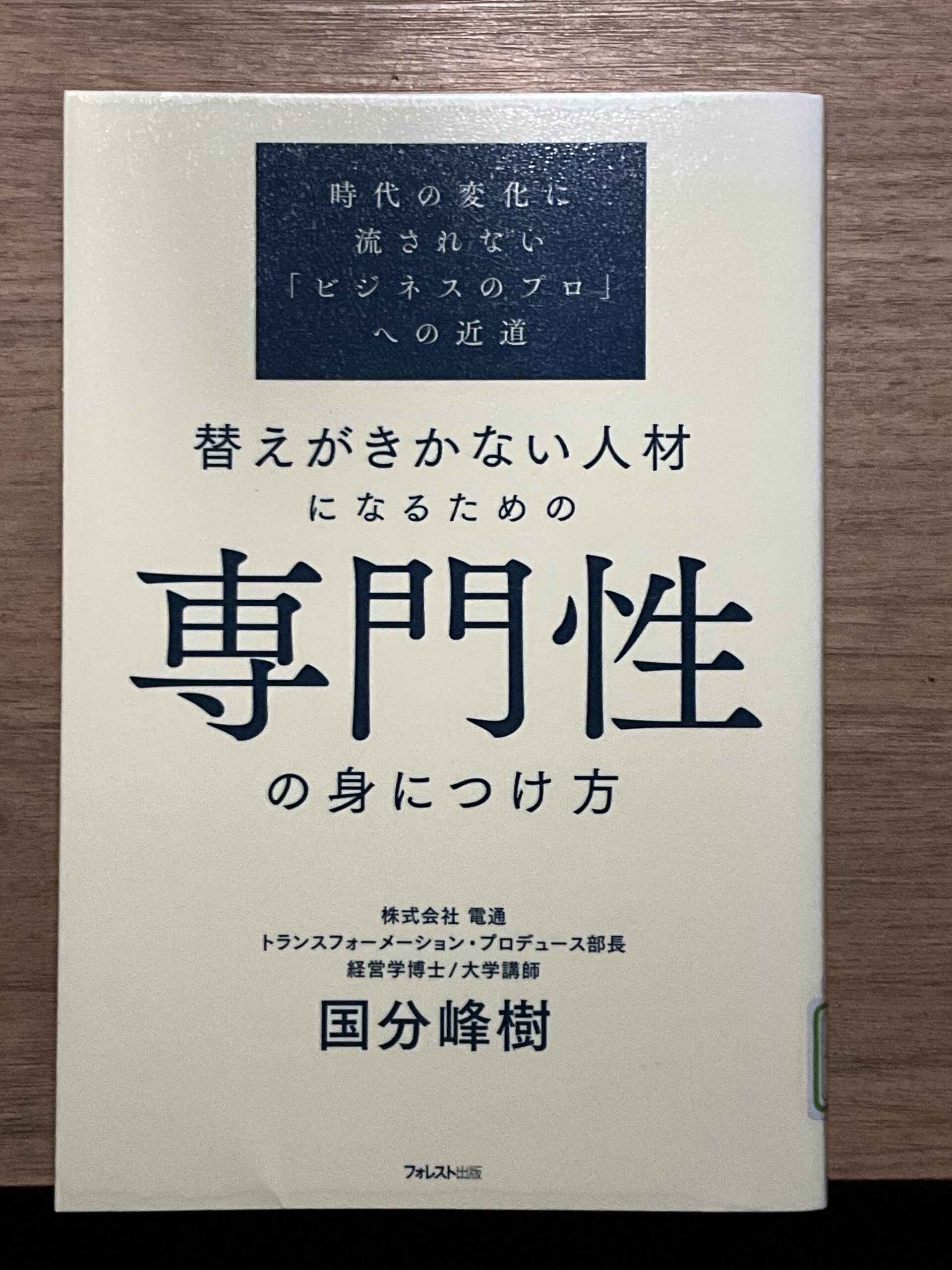
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/474bc9b5.aae640e7.474bc9b6.8b0594b0/?me_id=1213310&item_id=20984595&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2374%2F9784866802374_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

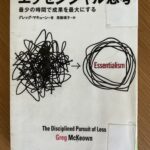
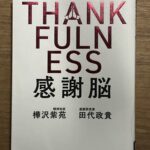
コメント