「アウトプット大全」(樺沢紫苑著 サンクチュアリ出版)の本を読んで、本を読んだらアウトプットが大事ということを学びました。
同著者の「インプット大全」という本がありましたので、興味を持ち読んでみました。
こちらも大変参考になる内容が沢山ありましたので紹介したいと思います。
「インプット大全」(樺沢紫苑著 サンクチュアリ出版)
この本には、アウトプットを高めるためのインプット術が書かれています。
本の中に「貧弱なインプット」の人が、どれだけアウトプットを頑張っても「貧弱なアウトプット」しか出来ないと書かれています。
「インプット」を今一度見直し、アウトプットで自己成長することが書かれています。
本書に書かれている「アウトプットの基本原則」
- 2週間に3回使った情報は、長期記憶
2週間に3回以上アウトプットすると長期記憶として残りやすい。 - 出力と入力のサイクル「成長の螺旋階段」
インプットとアウトプットを繰り返し、スパイラルアップする。 - インプットとアウトプットの黄金比は3:7
研究でインプット:3、アウトプット:7が最も良い結果を出した。 - アウトプットの結果を見直し、次にいかす
フィードバックが重要
→アウトプットの結果を評価して、その結果を踏まえて、次のインプットに修正を加える。
この本は、以下の7部構成になっています。
- インプットの基本原則
- 科学的に記憶に残る本の読み方
- 学びの理解が深まる話の聞き方
- すべてを自己成長に変えるものの見方
- 最短で最大効率のインターネットの活用術
- あらゆる能力を引き出す最強の学び方
- インプット力を飛躍させる方法(応用編)
1.インプットの基本原則
「インプットの基本原則」では、主に以下のことが述べられています
※インプットにおいて大切なのは「質」、次が量。
「量」は後、「質」が優先。
- インプットの制度を高める。インプットの効率を高める。
必要な情報、知識以外は捨てる。 - 記憶にとどめることで、インプットが成立する。
- インプットの基本原則
*なんとなくではなく、注意深く読む。
*インプットは方向性、ゴールを設定する。 - アウトプット前提のインプットを行う。
*インプットしたら2週間で3回以上アウトプットする。
→記憶に残る
*アウトプット前提のインプットをすると、集中力を高め、記憶力、思考力、判断力が高まる。
インプット量も100倍になる。
2.科学的に記憶に残る本の読み方
「科学的に記憶に残る本の読み方」では、主に以下のことが述べられています。
- 深く読む:深読する。
- 他人に説明できるように読む;読書感想を書く。
*重要と思ったら、すぐにアンダーラインを引く
*後から読み直したい、引用したいところに付箋を貼る
*気づき、派生するアイディアなど、何でも書き込みする
*その本の「ベスト名言」を選ぶ
*その本の「最大の気付き」を書く
*今日から実践したい「最大のTO DO」を書く
*本を読んだら、短文でもいいので必ず感想を書く - 自分にとってのホームラン本に出会う確率を高める。
(失敗しない本の選択術が10項目書かれています) - バランスよく読む。
メリットとデメリットの両方を意識する
3.学びの理解が深まる話の聞き方
「学びの理解が深まる話の聞き方」では、主に以下のことが述べられています。
- ノートをとるのは3:7。ノートが3、講師の話を聞くのが7。
- セミナー等は目的を持って聞く。
セミナーの目的を開始前にノートに書く - 質問を前提に聞く
- メモをとりながら聞く。
メモをとりながらきくと脳が活性化する
→*集中力が高まる
*重要点を聞き逃しにくくなる
*内容の理解が高まる
※注意!:メモをたくさんとると記憶力が低下する
気付き、要点、重要ポイントだけメモをすること
4.すべてを自己成長に変えるものの見方
「すべてを自己成長に変えるものの見方」では、主に以下のことが述べられています。
- 観察する
6つのメリットが書かれています。
*コミュニケーションがアップする
*人間関係が良好になる
*情報収集力が上がる
*自己成長のスピードがアップする
*変化に敏感になる
*ビジネスで成功する - OODA(ウーダ)ループを回す
見る(Observe)→わかる(Orient)→決める(Decide)→動く(Act) - 観察力を磨く
(観察力の磨き方が7項目書かれています) - 見直す
2週間で3回以上インプットする→記憶が強化される - メモを見直す
*メモにはアイディアやひらめきを蓄積し、第二の脳として活用する
*メモは困った時に見る
アイディアが思いつかない時の参考になる
*メモは数ヶ月に1回整理する。
整理することで意外な発見、あるいは発想、ひらめきの連鎖が起こることがある - 美術館賞をする(5つのメリットがある)
*学力が上がる
・創造性を鍛えることにより、学力が上がる
・創造性を鍛える効果があるのが芸術鑑賞
*AI時代を生き抜く創造性が養われる
*脳が活性化する
*癒し効果がある
美術鑑賞するとセロトニン、ドーパミンが分泌される
*ビジネススキルがアップする - 自然の風景を見るのも良い
5.最短で最大効率のインターネット活用術
「最短で最大効率のインターネット活用術」では、主に以下のことが述べられています。
- 生産性を最大化するメール術
*朝イチでメールチェックしない
パフォーマンスが高い時間は緊急メールの返信だけにして、
生産的な仕事にあて、残りのメールは後にする。
*迷惑メールを受信しない
*重要メールはフォルダに分ける
*メールはまとめてチェックする
*通知は仕事の邪魔になるので切っておく - Google検索で最短で必要な情報にたどり着く検索方法
- WebページをPDF又はスマホのスクリーンショットで保存する
- 動画で検索する
6.あらゆる能力を引き出す最強の学び方
「あらゆる能力を引き出す最強の学び方」では、主に以下のことが述べられています。
- 人と会う
一緒に成長する(教え、教えてもらう) - 交流術
*何度も会う
100人と1回会うより、10人と10回会う
*今すぐ、アポを入れる
興味がある人にはその場で次のアポを入れる
*与える
受け取るだけでなく、与えることを考える
*全ての人と仲良くしない
気が進まない場合は断る
*1対1で会う
1対1は人間関係が深まる
*つながりを続ける
継続的につながりを続ける
*一緒に成長する仲間を見つける
大きな目標を持っている人は、一緒に成長する仲間を持っている - なりたい人をまねる
まねることが学びの始まり(「学ぶ」の語源は「真似ぶ」) - すごいと思う人は直接会いに行く
- 自分を知る
自己洞察力を高める(自己洞察力を高める方法が7項目書かれている) - 検定を受ける
最強の脳トレになる(メリットが9項目記載されている) - 遊ぶこと、旅に出ること、食べること、料理を学ぶことが良いと書かれている。
7.インプット力を飛躍させる方法(応用編)
「インプット力を飛躍させる方法」では、主に以下のことが述べられている。
- 精緻化して覚える
*「記銘」、「保持」、「想起」の3つのプロセス全てを強化する
*精緻化の方法
・追記:情報を追記する
・関連づけ:他の情報と関連づける
・言い換え:自分の言葉で置き換える。要約する
・ストーリー化:語呂合わせ
・整理、まとめ:図や表を活用する
・視覚化:画像、写真、イラストを活用する。
・省察:自分の意見感想を述べる - インプット直後にアウトプットする
記憶増強効果が得られる - 寝る前を活用する
寝る前15分は記憶のゴールデンタイム - 週2時間以上の運動で記憶力がアップする
*運動をすれば記憶が良くなる
*記憶が良くなる運動法
・運動の種類:有酸素運動
・運動の時間:週に合計2時間以上
・継続時間:1〜2ヶ月
・運動の強度:中程度(ちょっと苦しいくらい)
・簡単な運動よりも複雑な運動をする
脳を使いながら運動をする(ランニングマシンより屋外を走る) - 中程度の有酸素運動を週2時間以上する
- 複雑な運動ほど、継続するほど効果が高い
- 場所を変えて記憶すると記憶力がアップする
最後に
インプットもアウトプット同様に大事なことがわかりました。
インプット次第でアウトプットにも影響を及ぼします。
アウトプットを前提としたインプットが大事です。
「アウトプット大全」とともに本書も読まれることをお勧めします。
アウトプットの仕方も変わってくると思います。
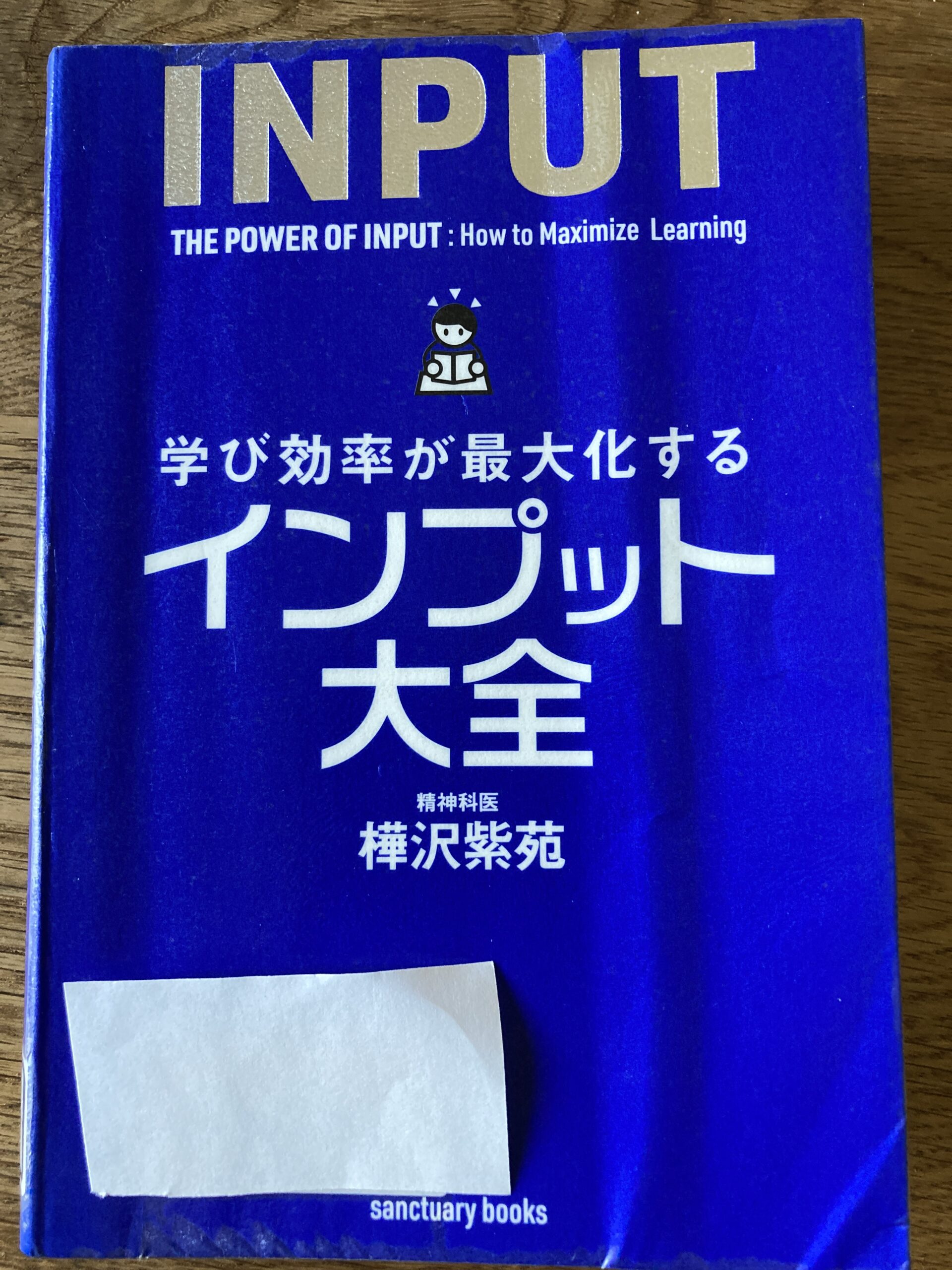


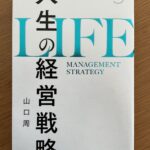

コメント