今回紹介する本は「静かな退職という働き方(海老原 嗣生著 PHP研究所)」です。
本書は、以下の8部構成になっています。
- 日本にはなぜ「忙しい毎日」が蔓延るのか
- 欧米では「静かな退職」こそ標準という現実
- 「忙しい毎日」が拡大再生産される仕組み
- 「忙しい毎日」を崩した伏兵
- 「静かな退職」を全うするための仕事術
- 「静かな退職者」の生活設計
- 「静かな退職」で企業経営は格段に進歩する
- 政策からも「忙しい毎日」を抜き去る
1.日本にはなぜ「忙しい毎日」が蔓延るのか
『日本にはなぜ「忙しい毎日」が蔓延るのか』では、主に以下のことが述べられています。
- 欧州の「標準労働」は日本ならクビになるレベル。
- 基本的に残業しない。金曜日は土日のことで頭いっぱい。
日本ではやる気がない、会社のお荷物と言われるが、欧州ではこれが標準。
- 基本的に残業しない。金曜日は土日のことで頭いっぱい。
- 仕事は「手を抜けば抜くほど、生産性が上がる」
- 日本は不良品が少ないが、わずかの不良率のアップのために、多くの労働時間を費やしていては、大きく生産性が下がる。
- 日本では野菜は形が悪かったら値段が落ちるので、繊細な作業が要求され、労働時間が延び、売上は不良品の分減るが、欧州では普通に商品として並べられている。
- 丁寧にいい仕事をすればするほど、生産性が下がり、手を抜くと上がる。
- 日本人がやってきた「顧客と真面目に向き合う」働き方は、ブルシット・ジョブ(あってもなくても変わらない意味のない仕事の蔑称)の塊と言える。
- 「真面目に良いサービス」というお題目に騙され、ブルシット・ジョブの渦がもがく生活を送っていたのではないか。
- なぜするか
「それが評価につながる」「何かあった時に言い訳になる」、そのため労働時間がいたずらに延び、生産性が下がり、私生活を犠牲にしなければならなかった。
- なぜするか
2.欧米では「静かな退職」こそ標準という現実
『欧米では「静かな退職」こそ標準という現実』では、主に以下のことが述べられています。
- アメリカのギャラップ社の2022~2023年に行った調査では、世界では平均59%の労働者が「静かな退職」に該当する。
(「静かな退職」の働き方が標準なので、そんな不埒な働き方はしていないと、数字が下振れしている可能性がある。7~8割が日本でいう「静かな退職」に該当する可能性がある。) - 欧米では、一般の労働者は歳を重ねても日本ほど給料が上がらない。就ける職業も学歴によって決まってしまう。
だから「給料は上がり続ける。だからそれにふさわしい仕事ができるような能力にしなければならない。」という日本では当たり前のストイックなキャリア感は、欧米では一部のエリートだけの話で、大多数は大して頑張らず、緩く長く今のまま働き続けている。それが世界のデファクトスタンダード。
3.「忙しい毎日」が拡大再生産される仕組み
『「忙しい毎日」が拡大再生産される仕組み』では、主に以下のことが述べられています。
- 日本では、正社員なら誰もが昇給し続けるが、非正規だと低給から抜け出せない。
- 欧米の一般労働者は年収が上がらないが、日本に見られる「シニアのキャリアの危機」(すぐにリストラ対象になる、仕事の割に給与が高い)は全く見られない。
年収が上がらない分、役職定年や定年再雇用などで年収が下がることなく安定した生活を送り続けられる。 - 日本では「上司から受ける能力評価」とその積み重ねで昇級
- が決まり、手抜きはやりづらく、一方で給料は着実に上がり、「昇級した分能力も上がったことになっている」ので、無理難題を引き受けざるを得ない。
結果、快く残業し、有給休暇は取らないという「忙しい毎日」となってしまう。 - 日本人男性が評価が付きまとうので、育休や短時間勤務を取らないが、昇級や昇給もない欧州の一般労働者は全く心配なく、育休や短時間勤務が選べる。
- 日本型賞与も「忙しい毎日」の保全ツールとなっている。
日本の正社員は、ヒラ社員でも結構な額の賞与が支給され、等級が上がれば増えていく。また査定でも変更する。
欧米では、ヒラ社員は日本のような賞与システムはない。あっても1ヶ月分等。
会社の収益によるので、会社の奉仕を強め、長時間労働にもつながる。
また、多くの国では残業代は法律や労使協定で40~50%の割増になっているが、日本では25%と低率であり、サービス残業もあり、これも長時間労働につながっている一因。
4.「忙しい毎日」を崩した伏兵
『「忙しい毎日」を崩した伏兵』では、主に以下のことが述べられています。
- 多くの女性が総合職として勤務し、ある程度のキャリアを積むようになり、女性活躍の機運とあいまって、育児をする女性に関しては、「忙しい毎日」型の労働からは脱し、短時間で会社から帰る権利が確保されるようになった。
加えて直近では、イクメン、カジメンの奨励まで起きるなど、「働き方が変わらざるを得ない」事情となり、「静かな退職」が市民権を獲得し始めたと言える。
5.「静かな退職」を全うするための仕事術
『「静かな退職」を全うするための仕事術』では、主に以下のことが述べられています。
- 「静かな退職」が組織にとって重い荷物であってはならない。
- 基本となるのは、持ち出しが少ないにもかかわらず、最大限のパフォーマンスを残せる行動をすること。
- 心証点を上げる
- まず「身なり」「言葉づかい」「マナー」に気をつける。
- 反論しない、原則ノーを言わない。但し、「自分の業務が増えるような場合」のみ、上手に反論する。
例えば、「賛成します。ただ〇〇のところだけがきになります」、これでひとまず時間を稼ぎ、その間に相手を見ながら「私だと△△の部分で無理がでます。せっかくいい案なのだから、もったいない気がしますねえ」と結ぶ。
- 心証点を稼ぎで重要なのは「空き時間」の有効活用。
- 「本当に効果があるかどうかわからないけど、やっておくべきだ」というような意味のない常識を全て排除する。
- プラスを重ねるよりも、マイナスの排除をする。
- 成果の芽とリスクの芽が並んだら、後者を優先させる。
- 完全なフリーの時間は、「明日への投資より、今日の心証点」を鉄則にする。
- 次の2つを念頭におく
- 「高い確率で業績につながる可能性がみえる」仕事はしっかりとやること。
- 評価や業績に関して、「下位3割には入らないこと」
- 「厄介な仕事」は自分の存在価値を高める。
他者が敬遠するから自分だけの聖域となり、業務をブラックボックス化させることが可能。 - 重要ミッション、特定の厄介な業務に注力する。
- 「将来への保障=副業の芽」作りを行う。
- 外注企業とは仲良くし、「会社を辞めたので、仕事を下さい」と言えば、色よい返事がもらえることも少なくない。
6.「静かな退職者」の生活設計
『「静かな退職者」の生活設計』では、主に以下のことが述べられています。
- 「静かな退職者」のキャリアの後半の年収は、大手なら750万円前後、中堅なら600万円台の期間が長くなる。
- 「静かな退職者」におすすめのモデル節税コース
- 4~6月期の残業を抑制する。
- iDecoを上限まで積み立てる。
- お金に余裕があれば、養老保険で返礼率の高いものを選び、1商品年8万円を上限に3本まで積み立てる。
- 欧州では、「お金がないから結婚(同棲)しよう」となる。
「結婚(同棲)することは、最大の生活費の切り詰め」
男性が大黒柱で一家を食わせるという生活感がない。 - 「家事・育児も生活費も男女分担」という生き方で生活を合理化するのが、欧州型の夫婦(同棲)の生活スタイル
7.「静かな退職」で企業経営は格段に進歩する
『「静かな退職」で企業経営は格段に進歩する』では、主に以下のことが述べられています。
- 起業に「静かな退職」コースを設ける等が提唱されている。
8.政策からも「忙しい毎日」を抜き去る
『政策からも「忙しい毎日」を抜き去る』では、主に以下のことが述べられています。
- 「静かな退職」を念頭に置いた制度等が提唱されている。
最後に
話題になっている、「静かな退職」について書かれているので、興味があり手に取ってみました。
欧米では、この働き方が標準ということでした。
この働き方に興味があるが場合は、若いうちからの方が取り組みやすいかとは思います。
実際に自分がこの働き方を行うには、心証点を稼ぐという点も含めて、かなり要領よくやらないといけないなと感じました。但し、自分にできるかは疑問ですが・・・。
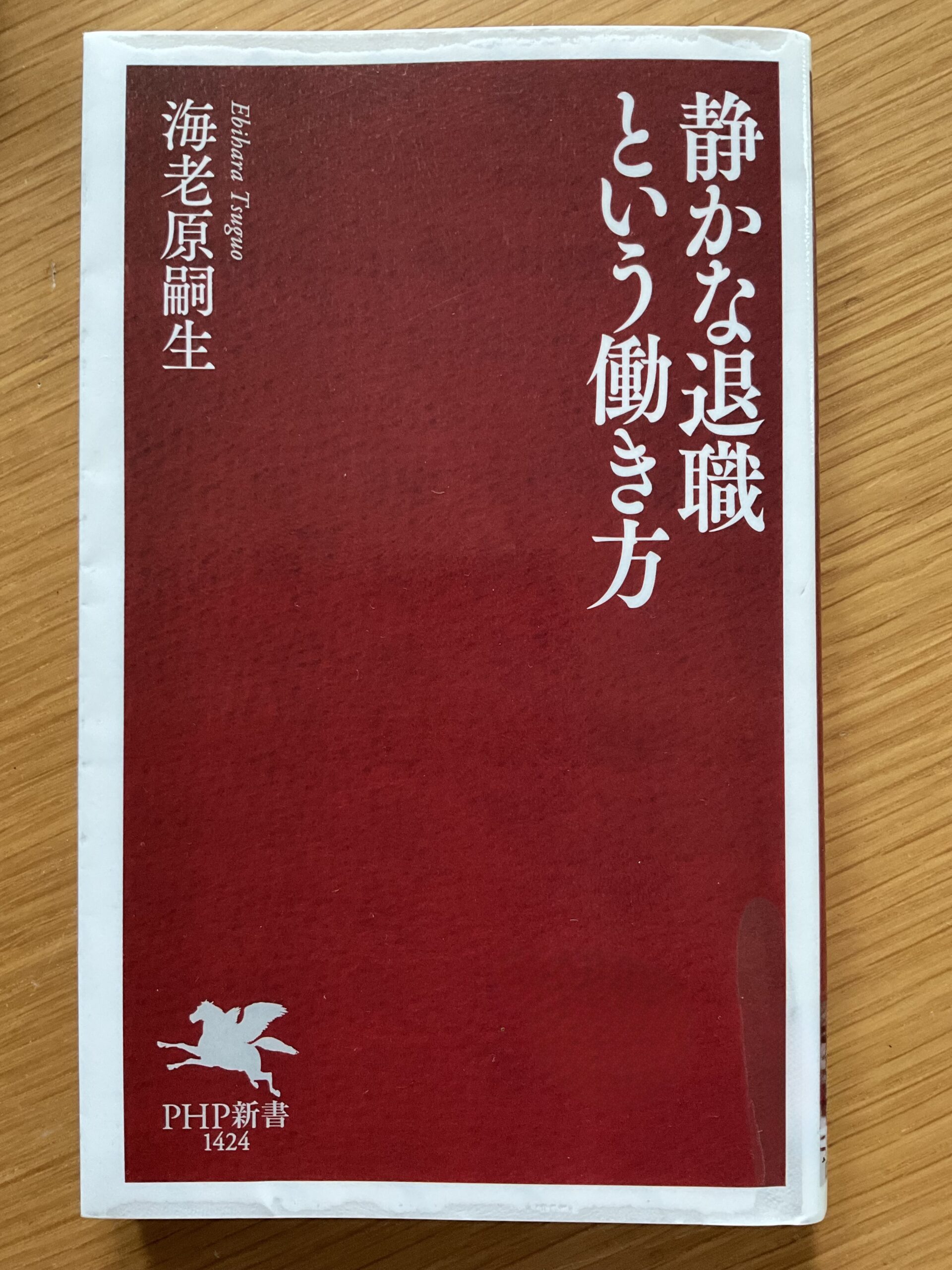
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/474bc9b5.aae640e7.474bc9b6.8b0594b0/?me_id=1213310&item_id=21475714&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8791%2F9784569858791_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


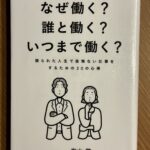
コメント